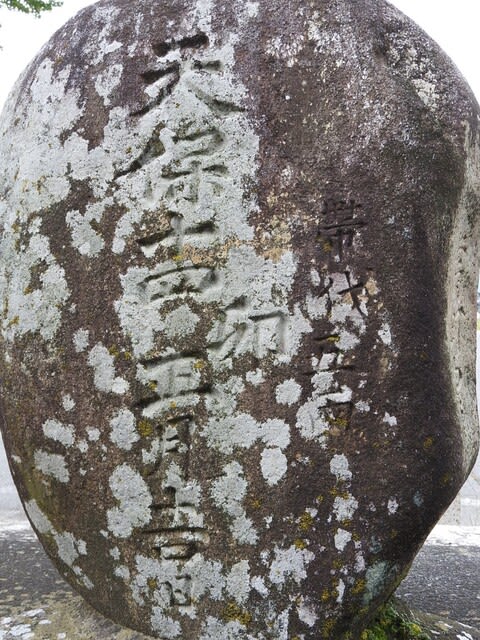第1巻からずーっと読み続けてきたから、最後まで読む。 360
360
■ 『本所おけら長屋』畑山健二(PHP文芸文庫2021年)の最新第16巻に収録されているのは「くらやみ」「ねんりん」「せいひん」「あいぞめ」の4編。例によってひらがな4文字のタイトル。第1巻からずっとひらがな4文字だが、これは作者の単なることばあそびだと僕は思っていた。ブログ友だちのtamiさんはこのことについて**おけら長屋のみんなの為?**と書いている。なるほど、江戸時代、市井の人たちがみんな漢字まで読めたわけではなく、ひらがなしか読めなかった人たちも少なくなかったということを思い合わせると、これは納得できる推測だ。
「せいひん」は、そう「清貧の思想」の清貧(過去ログ)。ストーリーの紹介は省略するけれど、見世物小屋で「貧乏神のご開帳」という興行を打って、飲み代を稼いだおけら長屋の万造と松吉、万松コンビが次に打ったのは「大黒天ご開帳」。大黒天に扮したのはやはりおけら長屋の住人、金太。**「ば、馬鹿野郎。そんなとこをご開帳してどうすんでえ。隠せ。早く隠せ。(後略)」早朝のスタバで、キンタ、いや金太のご開帳に声を出して笑ってしまった。
「あいぞめ」はこのブログを書く前に読んだが、万造の次のせりふが好い。**「(前略)人は追いつめられたときに真価が問われるんでえ。人としての値打ちがよ。つまり、ここから本当の勝負が始まるってこった」**
このストーリーの紹介も省略するけれど、お満さんを絶体絶命の大ピンチから救った万造。その万造に向かってお満さんが言う。
**「必ず、助けに来てくれるって信じてた・・・・・・」**
**「ああ。どこまでだって走ってやらあって言ったじゃねえか」**と返す万造。このふたりの会話を読んで涙が出た。一昨日は寅さんで泣き、今日は「本所おけら長屋」で泣き・・・。
さて、『夜明け前』の第3巻、第二部(上)を読み始めるか。















 360
360