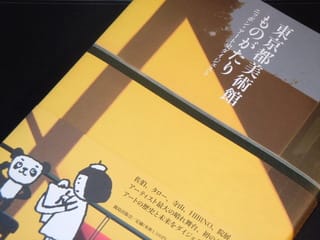306
■ 火の見櫓のフォルムの魅力として末広がりでなだらかな曲線の脚部を挙げることができる。あの曲線には魅せられる。
松本から三才山トンネルを抜けて上田市丸子(旧丸子町)に入ると、火の見櫓が国道沿いに何基か立っている。それらは皆細身で、脚部は直線的という特徴がある。
他にも櫓上部のブレースにはターンバックルが付いていないこと、櫓が細身なので途中の踊り場は櫓の外に付けられていることなども特徴として挙げることができる。
立科町からの帰路、この火の見櫓を見つけた。やはり上記の特徴を備えている。端正で美しいフォルムが魅力的だ。見張り台のところに余分なものが一切ついていないのもいい。
屋根の4隅には控えめに蕨手が付けられている。

久しぶりの評価
1 櫓のプロポーション ★★★★
2 屋根・見張り台の美しさ ★★★★★
3 脚の美しさ ★★★

























































 ②
②  ③
③