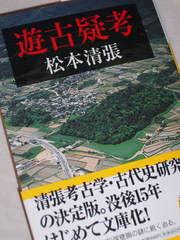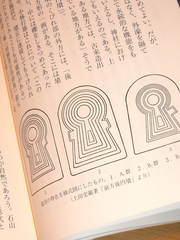↑ はてなブログにブログを開設しました。閲覧いただければ幸いです。
「U1さん、ブログに載せる会話ってフィクションだっていつか断っていましたけれど、私との会話ってほとんどそのままでしたね」
「そうだっけ」
「別にかまいませんけど・・・。よく覚えているな、って感心してました。別にメモしているわけでもないのに・・・」
「まあ、会話の流れを覚えていれば、再現できるんじゃないかな」
「そうですか・・・。もしかして、プロ騎士が対局を最初から再現できるのと同じなんでしょうか」
「う~ん、あんな能力はないけれど・・・」
「あの、これ」
「何? もしかしてチョコ?」
「少し早いんですけど」
「義理堅いね、今はもう義理切り、だよ」
「でも、本命って今いませんから・・・」
「そう? ま、義理が廃れりゃ この世は闇、だからね」
「え?なんだか演歌みたいですね」
「そう。でもKちゃん若いのに知ってるの」
「ええ、父が歌ってましたから。あの、この本って、この間の直木賞受賞作ですよね」
「そう」
「利休ですか・・・。あの侘び茶の」
「そう。Kちゃん、さすがだね。侘び茶ってよく知ってるね」
「ええ。私、高校で茶道部でしたから」
「そう? そういえば和服が似合うかも」
「あ、いえ、成人式の時しか和服は着たことないです」
「そうなんだ。すごく和服が似合いそう」
「そうですか、しとやかに見えます? で、どんな小説なんですか、これ」
「利休って19歳の時、高麗出身の超美人と駆け落ち同然のことをしようとしたんだね。未遂に終るんだけど」
「そうなんですか・・・」
「ン、史実なのかどうかしらないけれど。この小説ではね。で、え~と、どこだっけな。あ、ここ。**あの女(ひと)に茶を飲ませたい―。それだけを考えて、茶の湯に精進してきました。**ってあるでしょ。利休の台詞。どうも、その高麗の女性のため精進したってことらしいよ」
「初恋かどうかわかりませんけど、その女性のために茶道を極めたってことなんですか」
「そう。案外男なんてそんなかもね。で、ここ。**あなた様には、ずっと想い女(ひと)がございましたね**ってあるでしょ。利休は奥さんにこう訊かれるわけ。小説の冒頭でね」
「ふ~ん。利休はその女性のために一生・・・? 最後は切腹したんですよね。それまでその女性のために茶道を極めたんだ。奥さん気の毒・・・」
「そう、そういう小説。小説は利休切腹の朝から遡っていくんだけどね。で、高麗の娘と知り合う経緯を書いて、最後にまた元に戻って、利休が切腹して・・・」
「へ~」
「で、その高麗の女性は不幸な死を遂げるんだけど。その形見を利休はずっと大切にしていて・・・。その形見の交合を奥さんが石灯籠に投げつけるところで小説は終っている。嫉妬だよね」
「そうですか。読んでみたいな」
「貸してあげるよ」
2009年2月11日投稿記事再掲











 乾杯!
乾杯!