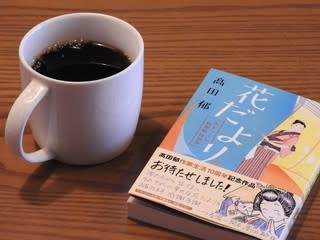1081 松本市笹賀 松本短期大学の近く 3脚86型 撮影日180928
■ 火の見櫓めぐりを始めた時から先を見通してせめて通し番号を付けるくらいのことはきっちりしておくべきだった。基礎的なデータの管理は基本中の基本なのに・・・。この火の見櫓は初見ではない。2010年の6月6日に撮影した写真がある(下、左)。だが、過去ログを当たってもこの火の見櫓は出てこなかったので番号を付けた。ブログにアップしなかった、としか考えられない。

左 撮影日20100606 右 撮影日20180928
少しアングルが違うが同じ火の見櫓だということは分かる。火の見櫓だけでなく、後ろの建物や架線の様子も同じだ。
8年の間にモーターサイレンが設置され、脚元に消火ホース格納箱も設置された。屋根を比べれば分かるが、塗装もされてサビサビからピカピカへ。これはうれしい。

3角形、柱が3本の櫓に8角形の屋根を載せている。見張り台は6角形。3脚86、このような組み合わせは多くはない。

脚元に咲くコスモス。