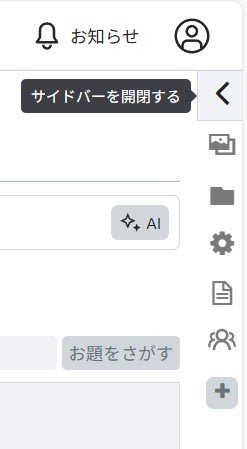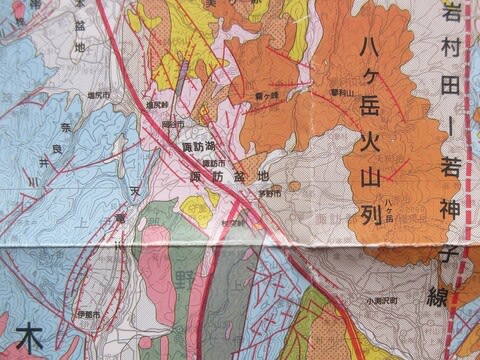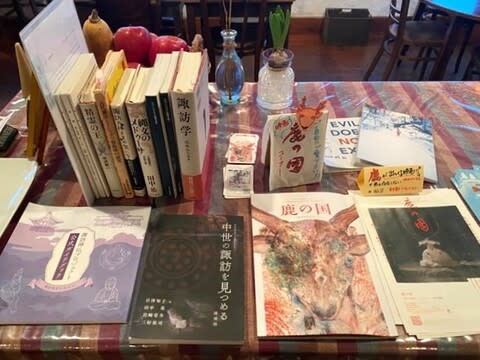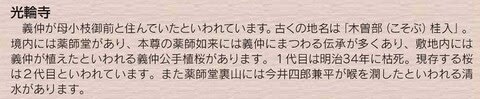■ 手元の広辞苑で付け焼刃の意味を知らべると、**一時その場を間に合わせるために俄かに習い覚えること。また、その覚えた知識。**とある(第二版補訂版(1979年))。
「付け焼刃」即ち「短期間で俄かに得た知識や対応」は好ましくないという考え方は、時に今の時代に合わない見方にもなるのではないだろうか。
俄かに得た知識は確かに軽視されがちだが、今やインターネットを適切に使えば、すぐに様々な質の良い知識を得ることも可能な時代だ。むしろ、現代の目まぐるしい情報社会では効率的に知識を得ることが重要視され、またそのような必要に迫られることも少なくない。昔のように、例えば図書館に通い詰めて、苦労していろんな文献をじっくり調べ、時間をかけてようやく必要な知識に辿り着くことが必ずしも優れた方法ではなくなってきている。
冷凍食品を使ったお弁当のおかずを例に挙げよう。かつては手間隙かけた例えば手作りハンバーグに比べて、冷凍食品のハンバーグを使ったお弁当は愛情不足などと、否定的な考え方が間々あった。しかし今ではその手軽さが多くの家庭に受け入れられ、重宝されている。同様に知識の入手方法についても今は効率が重視され、短期間で有用な情報を収集することが求められるケースが多い。医師から聞いたこともないような病名を告げられ、インターネットでその病気について調べて、次の診察の際、医師に訊く。小説を読んでいて、行ったことのない地方の町が出てきたので、その町についてネットで調べて情報を得る。このように俄か勉強で知識を得ることは日常生活でもよくする。
加えて、俄か勉強で情報を得て対応する他ない、というケースも時に起こる。もう何年も前のことだが、ある設計プロポーザルに取り組んでいた時のこと。プレゼンテーション当日の朝、説明にパワーポイントを使っても構わないという情報が急にもたらされた。午前中の短時間でそれこそ付け焼刃でなんとか準備したパワーポイント、資料を用いて、私たちはぶっつけ本番で午後のプレゼンに挑んだ。練習する時間は無かった。じっくり時間をかけて資料を集めて、パワーポイントをつくることなど、とてもできる状況ではなかった。だが、むしろその場に応じた迅速かつ柔軟な対応が功を奏したと思われる。私たちの提案が採用された。
このように、短時間で得た情報・知識を用いての対応がどのようなケースでも好ましくないということはないのだ。
付け焼刃はとにかくダメ、という一面的な考え方には異を唱えなければならない。残念ながら付け焼刃にはネガティブな、そう否定的なイメージがある。ものは言いようだ。なにか別の呼び名はないものだろうか。
「所詮は付け焼刃」などと否定的な見解を示す前に、前述した迅速かつ効率的な情報収集や状況への柔軟な対応が求められるケースにおいて、その価値、その有用性を改めて考えるべきではないか。
拙ブログでは引用箇所を**で示している。
















 ①
① ②
②