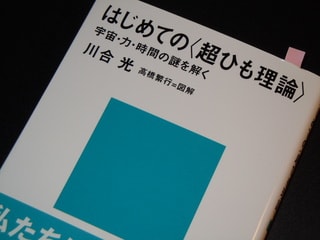『蜩ノ記』 葉室 麟/祥伝社 を読み終えた。小説をどう読むかは読み手に委ねられている。この作品は恋愛小説としても読むこともできるし、サスペンスミステリーとしても読むことができる。清廉、高潔な生き方の指南書としても読むことができる。
*****
「兄やん、笑うちょるね」
(中略)
「源吉の奴、お春坊に悲しい思いをさせたくなかったんだ。だから命の際まで笑い顔を見せて――」
(中略)
「まことに武士も及ばぬ覚悟だ」(262頁)
自分が死んだら妹が悲しがるに違いないと思って、命の際まで笑顔を作った源吉。彼は今でいえばまだ小学生くらいの子ども、そんな子どもが厳しい取り調べに耐えに耐えて妹のお春を想ってこんなことまでして・・・。
*****
「薫の祝言と郁太郎の元服も見届けることができ申した。もはや、この世に未練はござりませぬ」
「さて、それはいかぬな。まだ覚悟が足らぬようじゃ」
慶仙は顔をしかめた。秋谷は片頬をゆるめた。
「ほう、覚悟が足りませぬか」
「未練がないと申すは、この世に残る者の心を気遣うてはおらぬと言っておるに等しい。この世をいとおしい、去りとうない、と思うて逝かねば、残されたものが行き暮れよう」(318、319頁)
(中略)
「そなたの未練はほかにもありそうじゃな。茶室に参り、心行くまでゆるりと一服喫されるがよろしかろう」(319頁)
この先を読み進んで、涙が出た。こんな状況設定をされたら泣く・・・。 これは優れた恋愛小説だ。
映画化されるなら、炉の傍らに座っていたひとは誰がいいだろう・・・。
*****
前藩主の側室との不義密通の嫌疑で、10年後の切腹と家譜編纂を命じられて幽閉された元郡奉行・戸田秋谷(しゅうこく)。期限付きの命、どう生きるか・・・。
城内で刃傷沙汰に及んだが、切腹を免れた檀野庄三郎。彼は家老の命により秋谷の監視をするために幽閉先の向山村に出向く。そこで彼もまた、生き方を問われることになる。
*****
**山々に春霞が薄く棚引き、満開の山桜がはらはらと花びらを舞い散らせている。昨日まで降り続いた雨のせいか、道から見下ろす谷川の水量が多い。流れは速く、ところどころで白い飛沫(しぶき)があがっている。**
この小説を書店で手にして、書き出しのこの風景描写を読めば、続きを読もうという気になるだろう。
秋谷の妻の名前は織江。織江という名前は懐かしい。五木寛之の『青春の門』の主人公・信介の幼なじみが織江だった。織江にある人を重ねて読んだ遠い昔のことを思い出した。
時代小説はあまり読まないが、この作家の他の作品も読んでみようと思う。



















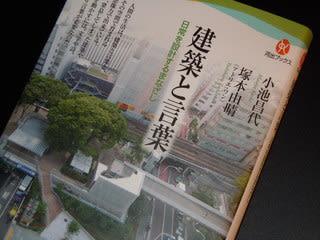
 ①
① ②
② ③
③ ④
④