
■『東と西の語る日本の歴史』網野義彦/講談社学術文庫読了。日本は東西で政治も経済もそして文化も違っていた・・・。
東西という視点から観る日本通史。植生、動物相の東西の違いに求める石器文化の相違、二万年の昔から近代史の東西相違まで。
さて、年越し本は『神社霊場 ルーツをめぐる』武澤秀一/光文社新書。この著者の『法隆寺の謎を解く』に魅せられて、『マンダラの謎を解く』、『空海 塔のコスモロジー』を読みました。グレーゾーンなど残すことなく、スパッと歯切れよく自説を展開するこれらの著書。
大晦日、2009年は今日でオシマイ。では、皆さん良いお年を!!
元日、このブログは例の書籍のタイトルによる新年の挨拶から始めます。
■ 松本清張の代表作に私は『点と線』『砂の器』『ゼロの焦点』を挙げます。清張作品の多くがテレビドラマ化、映画化されていますが、これらの作品もテレビドラマにも映画にもなっています。
今年は清張生誕100年、先日はNHKで『天城越え』が、民放で『火と汐』が放送されました。『顔』も放送が予定されています。
『天城越え』は再放送で清張自身も出演していました。清張がちょい役で出演するシリーズの1作品でした。このシリーズを観た記憶があります。
映画『砂の器』は邦画の中では一番印象に残っている作品です。ハンセン病の父親とまだ小さい息子が故郷を離れて全国各地を放浪する(北陸から山陰だと思いますが、ロケは別の場所でも行われたのでは)後半のシーンはとても切なくて泣きました。美しい風景も音楽も印象的でした。
清張作品の主人公は孤独な人が多いです。芥川賞受賞作の『或る「小倉日記」伝』の主人公の青年 田上耕作がそうです。『砂の器』の主人公 和賀英良も、『ゼロの焦点』の室田佐知子もそうです。『球形の荒野』にもやはり孤独な外交官 野上顕一郎が登場します。タイトルが孤独な世界を暗示しています。
『砂の器』を読んだのは中学生のときでしたが、『ゼロの焦点』もたぶんそうだったと思います。『球形の荒野』は高校生の頃かな。
『ゼロの焦点』は71年(昭和46年)にNHKでドラマ化されています。このドラマも観ました。主な登場人物は女性3人。見合い結婚した直後、夫が失踪してしまう主人公鵜原禎子を演じたのは十朱幸代、金沢の煉瓦製造メーカーの社長夫人 室田佐知子を演じたのは奈良岡朋子。その会社で働く田沼久子は誰だったか名前を忘れてしまいましたが、ネットで調べて「渡る世間は鬼ばかり」に出ている長山藍子だったと分かりました。
今秋『ゼロの焦点』が映画化され、現在公開中です。先のテレビドラマと配役を対応させると十朱幸代が広末涼子、奈良岡朋子が中谷美紀、長山藍子が木村多江となります。
テレビドラマ化や映画化される場合、時代の設定を現在に変えることもよく行われますが、『ゼロの焦点』は小説と同じ、もはや戦後ではないと言われた昭和32、3年です。
この作品の場合、終戦直後の立川での出来事が重要な意味を持っていますから、時代の設定を変えるわけにはいかないでしょう。上野駅を発車して行くSL、雪の金沢の街、路面電車やバス、車。映画では昭和が実にうまく再現されていました。
期待して観た映画でしたが・・・。残念だったのは、なんだかホラー映画に思えてしまったことです。再現された昭和の金沢でホラーな演技の中谷美紀。リアルな舞台から遊離した演技。原作とは全く別の世界です。これは彼女のせいではもちろんありません。原作をどのように理解しても、どのように映画化してもいいとは思いますが・・・。ただ、好きな役柄を演じた木村多江はよかったです。
終戦直後、占領下で生きるのに必死だった室田佐知子。過去との突然の遭遇、そして悲劇。それは田沼久子にも鵜原禎子にも及んで・・・。
私には野村、橋本コンビの『砂の器』の印象が強く残っているせいか、どうも馴染めないままラストシーンへ。小説では印象的なラストシーンが映画では上手く描かれてはいませんでした。
エンドロールに流れる曲がなぜ中島みゆきなのか、私の感性では分かりません。静かにバッハでも流れてきたらよかったのに・・・、荒涼とした海の底から響いてくるように。

民家 むかしの記録 戸狩にて8008
戸狩へは学生のときスキーに出かけたことがあります。北信濃に位置する戸狩は多雪地域です。
この写真、もう30年近く前、東北旅行の帰路、寄り道をしたときに撮影したものです。
雨や雪を防ぐことと室内の煙を外に出すこと・・・。相反する条件ですが、長い年月がこのような形を導き出したのですね。
民家の外観ではやはり屋根に注目です。大きな棟(漢字変換をまちがえないように)は「雪割り」の役目も果たしていると思います。棟の両端に小棟が付いているのが分かります。以前も紹介しましたが、長野(特に北部)から群馬にかけて見られる特徴です。
このころ既に鋼板で屋根を包んでしまっている民家が多かったのですが(下の写真)、茅葺の屋根を見ることが出来たのは幸いでした。ただ、やはり棟廻りは傷みやすいのでしょう、鋼板瓦棒葺きになっています。

上の写真と同日に撮影 戸狩にて

 『東と西の語る日本の歴史』網野善彦/講談社学術文庫
『東と西の語る日本の歴史』網野善彦/講談社学術文庫
久しぶりに書店へ出かけた。古今南北ではなく、古今「東西」なのはなぜだろう・・・、と先日書いた。「東西」を意識しだすと不思議、こんな本が見つかった。普段はチェックしない講談社学術文庫の棚、この本が私を呼んでいた。
目次を見ると3章「考古学からみた東と西」、8章「東国国家と西国国家」、13章「東と西を結ぶもの」、15章「東の文化と西の文化」
歴史には疎い。でもこの内容なら面白く読むことが出来そうだ。やはり「東西」には何かある!

■『住まい方の思想』渡辺武信/中公新書 84年初読、88年再読。
サブ・タイトルに「私の場をいかにつくるか」とあるように、住宅では私的な領域がいかに大切か、そしてその領域をつくるにはどうすればよいか、が主に論じられています。
映画評論家としても知られている建築家 渡辺武信さんの著書には映画のシーンがよく引用されています。この本にも例えば第2章「居間」にはオーソン・ウェルズの「市民ケーン」に登場する居間、第3章「食堂」には「家族の肖像」の食事の場面、第4章「厨房」にはダスティン・ホフマン主演の「クレイマー、クレイマー」の食事の場面などが写真と共に載っています。
渡辺さんは**宇宙船と同じように、内部の私性を外部に洩らさず、外部の公共性を内部に持ち込まないために、なんらかのエア・ロック的媒介空間が必要なのである。**と説いています(エア・ロックは宇宙船の出入口に必ず設けられていますね)。
**人間が一つの空間から他の空間へ移る場合を考えると、その際の心理的移行に効果的に対応するためには、二つの空間の間にヴォリュームのある媒介空間を置く必要がある。**とも説いています。渡辺さんは更にこの媒介空間について**住宅に足を踏み入れた瞬間に、視線がすぐ近くで跳ね返されることなく奥へ引き込まれ、到達目標となる居間の入口が、かなり遠くにあるか、または屈曲するルートの蔭になって見えないような空間である。**と具体的な説明を加えています。
ときどきお邪魔するカフェ・マトカ。玄関で脱靴するという行為によって意識する公的空間から私的空間への転換、ハイカウンターに隠されて見えない「奥」の席、渡辺さんの説明に合致する奥性のある空間。
公的空間とカフェという私的空間との間にも必要な媒介空間、更に私的空間の中に欲しい「奥性」。
このことを先日オーナーに話しました。そのとき、ちょっとした設えを検討中だと聞きました。その設えが空間の奥性を更に増すと思います。後は実行あるのみ・・・。
* 奥性という概念は建築家の槇文彦さん他の『見えがくれする都市』SD選書に出てきたと思います。また媒介空間は黒川紀章さんの中間体と同義。
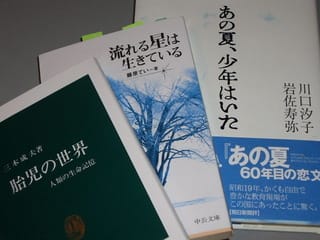
流れる星は生きている 藤原てい/中公文庫
生きて故郷まで帰るという強い意志。子どもを死なせてなるものかという執念。
あの夏、少年はいた 川口汐子、岩佐寿弥/れんが書房新社
淡い恋慕の情を抱きつづけて60年。その相手との奇跡の再会が生んだ本。
胎児の世界 三木成夫/中公新書
生物の進化のプロセスを短期間で再現する胎児の不思議な世界。
書名をクリックすると過去ログへ。

■ 今朝、久しぶりに書店へ。川上弘美の掌篇小説集『ハヅキさんのこと』が文庫になっていた。川上弘美初の講談社文庫、たぶん。単行本が文庫化されるとき、カバーデザインは変わることが多い。が、この小説は同じだ。どっちがいいかな。変わっていたほうがいいかな。
少しだけ立ち読みした。このところ小説を読んでいないがこれなら読める、そう思って購入した。翻訳家の柴田元幸さんは解説で**一気に読むより、一ページずつ、一本ずつじっくりゆっくり読むにふさわしい本だと思う。**と書いているが、午前中一気に再読した。
表題作。私とハヅキさんは元教師、同僚。ふたりとも教師には向いていなかった。よくふたりで酒を飲んで、教師業のうっぷんを晴らしたあとは、お互いの恋愛についてああでもないこうでもないと言いあっていた。この辺は実体験にもとづいているのかもしれない。川上弘美は高校で生物を教えていたことがあるから。ちなみに主人公の私は理科の、ハヅキさんは国語の教師だった。
それにしても彼女の小説には居酒屋がよく出てくるような気がするがどうだろう。テレビドラマは小泉今日子が主演して話題になった、なったかな、『センセイの鞄』は居酒屋カウンター小説だった(と言い切ってしまおう)。
あるとき、私とハヅキさんはお互いふられたことを打ち明けてハシゴ酒。気がつくとラブホの大きなベッドの上。ふたりとも女性、念のため、まあこの辺がこの作家の理性というか文学。ハヅキさんが男だったら通俗的だろう。
**「どっちが入ろうって言ったの」
「よく覚えてないけど、わたしのほうが面白がって入ろうとしたような気がする」
「ばかっ」とハヅキさんは叫んだ。
「私が相手だったからいいようなものの、誰か知らない男だったらどうするのっ」
ハヅキさんはこんこんと私を叱った。ラブホテルのスプリングのきいたマットレスの上で、こんこんと、私を叱りつづけた。**
あれから十数年、わたしは入院中のハヅキさんを見舞いに行くためにバスに乗っている。バスの座席のスプリングが、あのときのラブホテルのマットレスと同じような音をたてて鳴る・・・。
解説には「ばかっ」という安易にぎすぎすしない字づらが何ともこの書き手らしい、とある。「馬鹿っ」でも「バカッ」でもありえないし、!付きでもありえないというのだ。そうかもしれない。
川上弘美は輪郭を実線ではなく、破線、それも薄い破線でしか囲みようがないような場の空気、エッセイのタイトルにもしている『あるようなないような』雰囲気を実に上手く表現する。
さて、少しずつ小説モードへ。つぎは小川洋子かな。その前に『ヒマラヤ世界 五千年の文明と壊れゆく自然』『キリマンジャロの雪が消えていく』『それでも子どもは減っていく』『「論語」に帰ろう』『自然界の秘められ戸たデザイン』を読まなくては。今年の読み納めはどの本になるのだろう・・・。














