
533 撮影日150428
■ 狛犬にまで観察対象を広げてしまったのでヤグラセンサーが鈍くなっているのでは、と思いきや、感度は依然として良好なようで、国道148号を走行中に(私は助手席に座っていたが)この火の見櫓を見つけた。
洗練されてはいない、そう、武骨な印象の火の見櫓だ。ブレースがそのような印象を与えているのかもしれない。四角い櫓に四角い屋根、円い見張り台というのはよくあるパターン。
見張り台の大きさに比して屋根が小さい。白馬村が豪雪地帯であることを勘案すると、冬季には見張り台に雪が積もってしまうのではないのか、と気になる。四方に向けてスピーカーが設置されていてここに半鐘はない。

踊り場に半鐘が吊り下げてある。
脚元はこんな様子。このデザインだと火の見櫓だと気がつかないかもしれない。














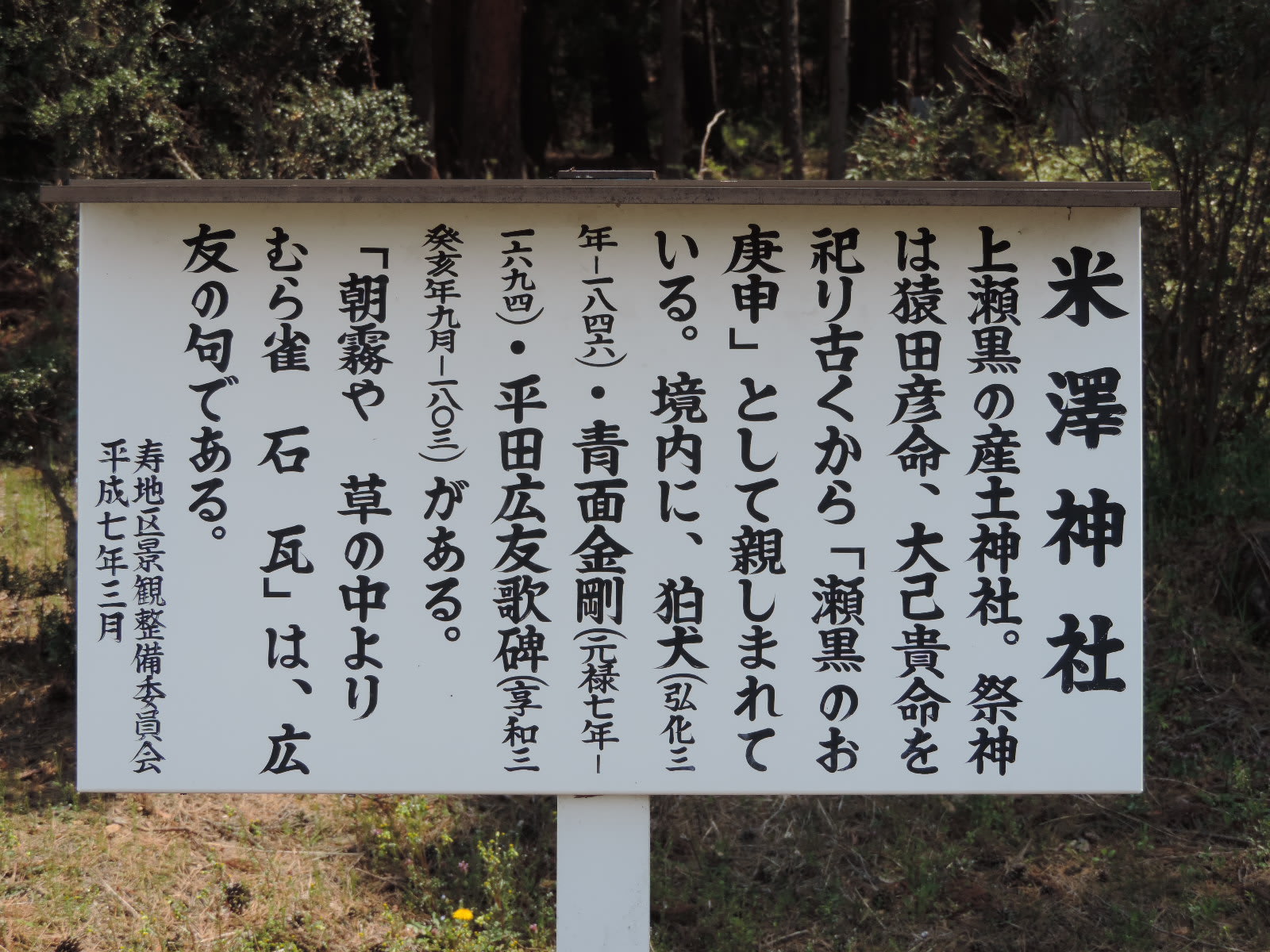






























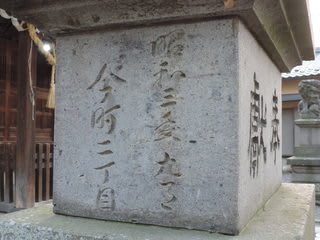



 でも・・・、これだけでは、なにか物足りない。
でも・・・、これだけでは、なにか物足りない。










































































