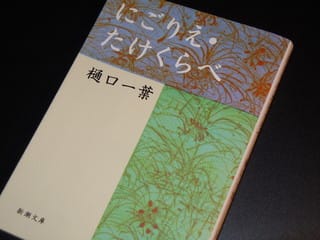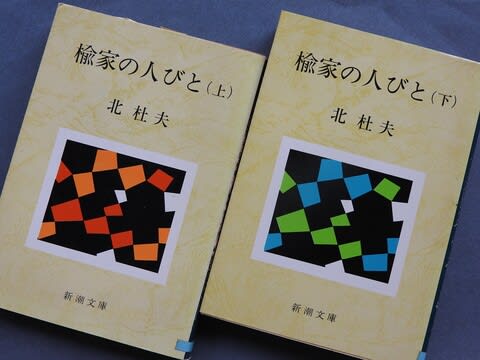240
240
■ 5月の読了本は5冊。
『徳川家康の江戸プロジェクト』門井慶喜(祥伝社新書2018年)
**利根川という大河川を曲げたうえに、湿地帯を埋め立てて土地を造成し、町をつくりました。飲み水は遠方から江戸まで堀を建設し、上水を引いて調達しました。食糧は日本海側の諸国や西日本、上方から船で運び込みました。そうすることで、一〇〇万人もの人が住めるようになったのです。**(134頁)
著者は江戸が人工的な町であったということをこのように分かりやすく説いている。利根川東遷についても分かりやすい図が見開きで載っている。総じて文章は読みやすく、掲載されている図も分かりやすい。一般読者向き。
『新幹線100系物語』福原俊一(ちくま新書2021年)
「関係者への綿密な取材に基づく記録」 帯にこのように記されている通り、関係会社、関係者への取材によって100系の開発から運行の裏側が明らかにされている。後世に残すべき貴重な資料に成り得るレポート。
『楡家の人びと上下』北 杜夫(新潮文庫1971年)
初読は1979年4月。久しぶりの再読。楡家の人びとの日々の暮らしの中に大正から昭和、太平洋戦争後に至る時代の大きな流れが描かれる。時代は違うが藤村の『夜明け前』にも通じるか。
楡家の人びとは時代の流れに抗うことなく、それを受け入れてそれぞれの生を過ごす。楡病院を継いだ徹吉(北 杜夫の父、歌人斎藤茂吉がモデル)は楡病院再建という困難な現実からの逃避的な作業として大著を執筆する。今回は徹吉の心情に共感。
『たけくらべ』樋口一葉(岩波文庫1927年第1刷)
名作は読み継がれる、読み継がれる作品こそ名作。物語は最後の1頁でそれまでの動から静へ転換する。そこが特に印象的。














 360
360 420
420



































 320
320