■ 早、明日は大晦日、古い表現だと大つごもり。同名の小説が樋口一葉にある。来年あたり一葉の作品を読み直すのもいいかもしれない。
信濃毎日新聞の今月27日付朝刊に「雑誌不振 街の書店を直撃する」という見出しの社説が掲載された。その中に**文化庁の調査では、日本人の半数は1カ月間に1冊も本を読まない。これでは出版文化、出版事業の衰退は止められない。**という記述があった。
日本人の半数とは、日本の総人口の半数、つまり本をまだ読めない未就学児も含めてのことなのかどうか不明だが、この字義を普通にというか常識的に解釈すれば総人口の半数ということになるだろう。などという理屈っぽいことはともかく、要は日本人は大人も子どもあまり本を読んでいないということだ。
今でこそ火の見櫓だ、マンホール蓋だ、狛犬だと趣味を挙げているが、何年か前までは読書くらいしか趣味がなかった。読書のような生活の基本的な営みが趣味といえるのかどうか、分からないが・・・。
学生が本を読まないのはいかがなものか、とも思うが、他人(ひと)の読書についてとやかく言うつもりはない。私は最も手ごろな趣味として読書を続けているだけだ。本を読むのが好き、ただそれだけのこと。
つまらぬ前置きはこのくらいにして、本題。今年最後のブックレビュー、12月の読了本は5冊だった。

『サンマの丸かじり』東海林さだお/文春文庫
食について一般人が気にもしないようなささいなことが東海林さんは気になってしかたがないようで、丸かじりシリーズにはそのようなことが取りあげられている。東海林さんの「食のなぜ?」に関する考察がおもしろく、興味深い。食の文化論ともいえる論考、と書けば大げさか。
「禁ゴクゴク飲みの時代」では食事のときに音をたててはいけない、という基本的なマナーについて考察している。
和食が世界的なブームとなった今、蕎麦のズルズルはいいのか、いけないのか。西欧の人は音をたてないで食べる。この風潮が日本に逆輸入され、やがて日本人も音をたてないで食べるのが主流になっていく、と東海林さん。煙草がそうだったように、次第にズルズル派が片隅に追いやられていく、と東海林さんは予測する。
蕎麦ズルズルかどうか、店員に訊かれ、そうだと答えると「蕎麦ズル」と書かれたフダが置かれたテーブルに案内される、と東海林さんは考える。この辺りのユーモアが実におもしろい。なるほどなぁ、と思いつつ読む。
更に東海林さんのこの論考はビールのゴクゴク飲みにも及ぶ。「当店ではビールのゴクゴク飲みは禁止とさせていただいております」

『三日月が円くなるまで』宇江佐真理/角川文庫
我が子のように作中の主人公の成長する姿をを優しく見守る宇江佐さん。代表作となった髪結い伊三次捕物余話シリーズ然り。

『昨日みた夢』宇江佐真理/角川文庫
この文庫本の帯に**闘病のさなかに書き継がれた渾身作!**とある。宇江佐さんは2015年11月に亡くなった。66歳だった。「口入れ屋おふく」もシリーズ化しようという目論見だったと思う。残念だ。
**「贅沢はほんのちょっぴり味わうだけでいいな。毎度だとありがたみが薄れちまう」**(60頁)
**「倖せって、その時は気づかないものですね。後で、あの時は倖せだったと思うのね」**(「三日月が円くなるまで」198頁)
宇江佐さんが登場人物に語らせる生活観には共感することが多い。来年も宇江佐さんの作品を読む。

『夏目漱石』十川信介/岩波新書
乳離れとともに養子に出された漱石。仲間と楽しく語っているときでも、ふと「孤独」が漱石の心を占める。当然、作品には漱石の心模様が投影されている。この本の指摘ではなかったが、あの「猫」にさえ孤独が見え隠れしているという。今回はこのことを意識して「猫」を読む。

『住み継ぐ家の物語』川上恵一/オフィスエム
時間・歴史と風景・風土。川上さんが重視するコンセプトがこの本に掲載されている作品に表現されている。時間を蓄積できない新建材の住宅には無い趣き、昔からそこに在ったかのように風景によく馴染む姿、その衒いのないデザインに大いに共感する。
来年はどんな本に出合うことができるだろう、楽しみ。











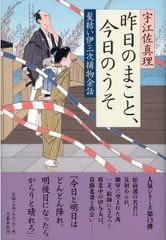






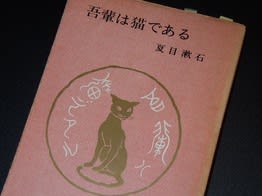
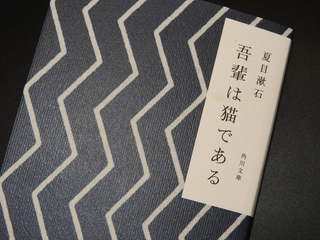
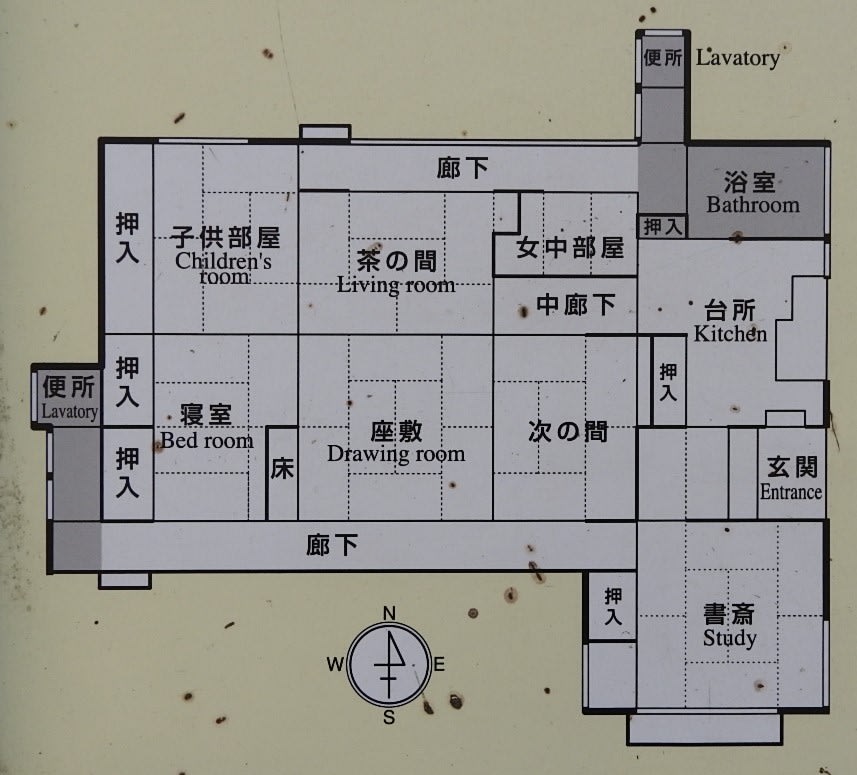



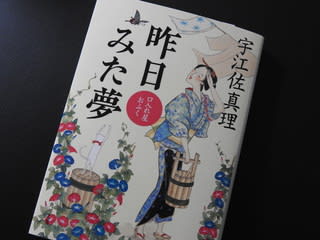
















 発車時刻は12時59分。待ち時間が40分以上ある。 で、食事をすることに。駅前通りに食堂見つからず。駅の売店でサンドイッチと缶ビールを買い、ベンチで食べる。これも旅。
発車時刻は12時59分。待ち時間が40分以上ある。 で、食事をすることに。駅前通りに食堂見つからず。駅の売店でサンドイッチと缶ビールを買い、ベンチで食べる。これも旅。



















