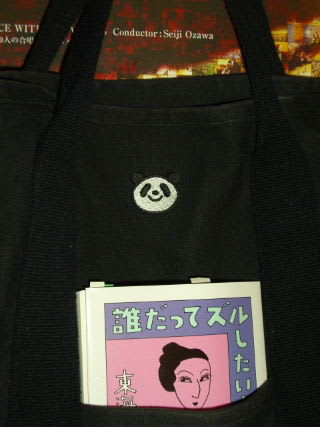
Yonda CLUB トートバッグ
■ 東海林さだおの作品は文春文庫に何冊も納められています。その冊数はざっと数えて50冊。全部揃えて書棚に並べたら壮観だろうな、と思います。残念ながら数冊しか手元にはありません。先週末「誰だってズルしたい!」を読みました。
巻末に特別付録として「棚から哲学」というコラムを週刊文春に書いている土屋賢二さんとの対談が収録されています。土屋さんの「こう書けば、笑ってもらえるという方法論みたいなものありますか」という質問に東海林さんは「擬人化」「誇張」「駄洒落」「言葉の短縮化」「比喩」などを使うと答えています。
この先はアルコールな夜のブログです。
比喩・・・、東海林さんは本書の中でいろんなズルを取り上げたあと、SEXもズルだと指摘しています。読者は全員大人だと思うので続けます。
性行為の本来の目的は生殖行為でそれは神聖で崇高な行為だと東海林さんは書いています。そうですよね、異論はありません。続けて**常に気高く、厳かに遂行されなければならない。**と書いています。もっともな指摘です。
あとは比喩で次のように続けています。**そのための様々な機器、器具、備品が人体のあの一帯に埋設されているのだ。**(中略)**現在、人類はそうしたあの一帯の施設をそういう目的に使用しているだろうか。**と疑問を呈し、**娯楽施設に流用しているのではないか**と鋭く指摘しています。流用も転用もズルだと東海林さんは考えているようです。
**神聖なほうの施設が、何の改良を加えることなく、そっくりそのまま娯楽施設として使用できるように設計した神様にも問題があるような気がする。**
建築では転用が盛んに行われています。駅や工場を転用した美術館もその一例でしょう。そういえば、前稿で紹介した雑誌には関東大震災後に生まれた復興小学校の代表、「四谷第五小学校」が「吉本興業の東京本部社屋」に転用されたことが紹介されていました。
神聖な施設の娯楽の大元締めの社屋への転用・・・、結構なことじゃないですか。











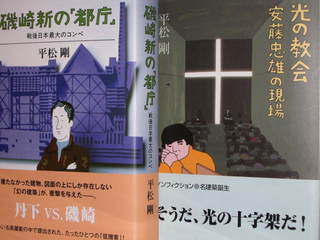
 ①
① ②
② ③
③


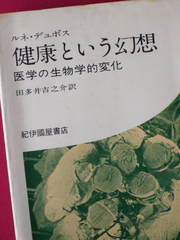
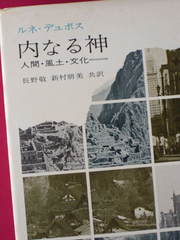
 ①
① ②
② ③
③
















