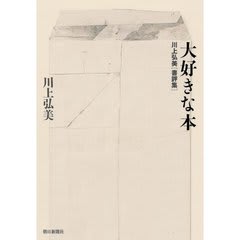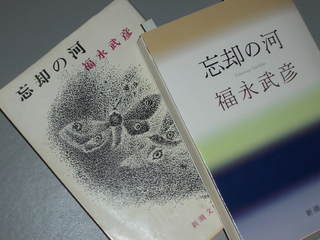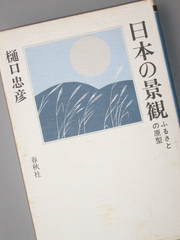■ 雨の日曜日、肌寒い朝。先日までの厳しい残暑がうそのよう。
「赤」でデビューした雑誌yomyom、今回は「紫」。写真の色の再現性がよくない、実際はもっと赤味がかった色。
川上弘美の短篇だけで680円払ってもいい。山本文緒、角田光代、阿川佐和子、恩田陸、金原ひとみ、島本理生、森まゆみ、松本侑子、三浦しをん・・・、敢えて女性作家だけ挙げたが豪華。この雑誌はお買い得だと思う。広告がほとんど無くてスッキリしているところもいい。
今日は雨降り、特に予定なし。ならば読むしかない。『彼岸過迄』とこの雑誌を持ってどこか落ち着くところに出かけよう。コーヒー飲みながら小さな幸せに浸ろう・・・。
ところで川上さん「濡れたおんなの慕情」って、今回は一体何を書いたの?













 私の乏しいクラシック体験。ストラヴィンスキーの「火の鳥」を新宿の厚生年金ホールで昔聴いて感動したことを覚えています。読売日響、指揮者は忘れました。
私の乏しいクラシック体験。ストラヴィンスキーの「火の鳥」を新宿の厚生年金ホールで昔聴いて感動したことを覚えています。読売日響、指揮者は忘れました。