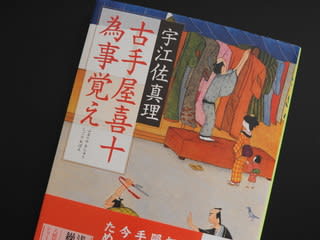■『ひょうたん』宇江佐真理/光文社文庫を読み終えた。
この物語の主人公の音松も、浅草田原町で古着屋を営んでいる喜十も、それから廻り髪結いの伊三次も皆、情に厚い。彼らの奥さんはしっかり者で、それぞれ良い組み合わせ、仲の良い夫婦だ。
江戸の下町の本所で小道具屋を営む音松の奥さんのお鈴さんは料理好き。店の前に七輪を出して煮物などをする。喜十の奥さんのおそめさんや伊三次の奥さんのお文さんが料理をするシーンとは違い、お鈴さんが料理するシーンは何回も出てくる。宇江佐さんも料理好きだったに違いない。
お鈴さんの料理目当てに音松の幼なじみが晩飯刻(小説の中の表記に倣った)にやってくる、手ぶらではなくて酒や食材を下げて。彼らは連れ立って花見に出かけたりもする仲の良い仲間。
なんだかいいなあ、彼らの関係。やはり持つべきは気の置けない友だちだ。
ここで宇江佐さんの作品は一休み。次は東海林さだおの食エッセイ『アンパンの丸かじり』文春文庫。週刊朝日に連載中のエッセイをまとめたもの。