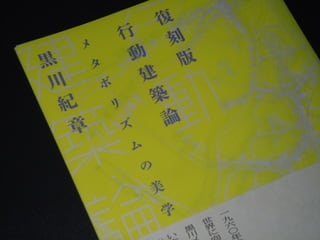406



■ 安曇野のヤグラー、のぶさんが紹介していた松本市波田下波田の火の見櫓を見てきた。
乗り鉄の場合、鉄道の全貌が分かっているからよいが(もちろん完乗するのは容易ではないが)、火の見櫓の場合、所在地が全て分かっているわけではないので身近なところにも未見の火の見櫓がまだまだあると思う。これもその1基。
4角形の櫓、8角形(立体形:8角錘)の屋根、隅を面取りした4角形の見張り台。見張り台の装飾的な手すりは整っていて好ましい。スピーカーは火の見櫓には全く似合わない。高さは優に15メートルを超えている。
脚部は1面のみアーチ状の構成になっている。このような場合、櫓内に梯子が設置されていて(上の梯子とは逆に左から右に向けて掛けられる)アーチ部が出入口のことが多いと思うが、この火の見櫓は梯子が櫓の外側に設置されている。では、櫓の正面のみアーチにしたのは何のためだろう・・・。
下の踊り場のところにこの火の見櫓の製作所(宮川鉄工所)と建立年(昭和34年)を示すプレートが取り付けられている。
立ち姿。踊り場が2ヶ所あるせいなのか、櫓のすっきり感がいまひとつ。櫓はもう少しスレンダーの方が好ましい。
でもアーチの曲線は美しい!これで脚の根元まで伸びていたら・・・。