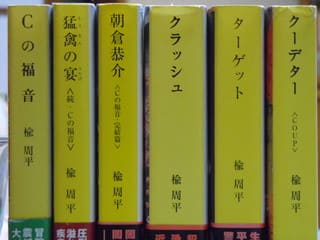■ 今日は出勤日だけれど、代休した。ワークライフバランスを少しは考えないと。女房は学生時代の友だちと女子会旅行で県外の温泉へ。ならばこっちも羽を伸ばそうと、夕方から冷酒をぐいぐい、いや、ちびちびやっている。
というわけでほろ酔いで書くアルコールなブログ。
「君の名は」って、ボクが生まれるよりずっと前(と強調しておく)のラジオドラマだけれど、再会を約束したもののすれ違いばかりでなかなか会えない、そう、会えそうで 会えない男と女のものがたりだということは知っている。放送時間になると銭湯の女湯ががら空きになっというエピソードも。
高見順の『今ひとたびの』を読み終えた。この恋愛小説もまた、恋人どうしの再会ものがたりと括っていいだろう。ウン、よい。
いままで高見順の作品にはなぜか縁がなかった。壇ふみのおとっつぁん、壇一雄や阿川佐和子のおとっつぁん、阿川弘之の小説は読んだのに高見恭子(ってこんな字だっけ?)のおとっつぁんの作品は未読だった。
これは何とも古風な恋愛小説だなと思いつつ読み進んだが、昭和21年の作品というから当然か。
**芝居の疲れからか、それともそのひとの性質なのか、まわりの人たちが傍若無人にはしゃいでいるなかで、そのひとだけは何か寂しそうに、皆と溶け合えないのを自ら寂しがっているような風で、頬に物倦げな微笑を浮かべていた。**(13頁)
主人公が一目惚れした女性はこんなふうに描かれている。ああ、このひとは・・・、ボクの好みのタイプ。
時代は第二次大戦前。主人公は大学生で左翼運動家。活動資金を援助してくれている友人の芝居を見に行って、舞台のそのひと、暁子に一目惚れしたのだった。暁子もまた次第に主人公の私に惹かれていく。
主人公は逮捕や徴兵に阻まれ、暁子が他人(ひと)の妻になっても、ひたすら慕情をつのらせ続ける。
**そのひとと、ここで、悲しい、別れたくない別れをしてから思えばながい年月が経っていることゆえ、私とのあの固い約束も、そのひとはあるいは忘れてしまったのだろうか。(中略) ここで、――お互いに生きていたら必ずまた会おうと言ったのは、ほかならぬそのひとだったのだから・・・・。**(3頁) 男と女の再会ものがたりはこのように始まる。
そしてラスト。
**「あ!」
思わず大声をあげた。周囲の人が吃驚(びっくり)してその私に眼を注いだ。
そのひとだ。
そのひとが立っている。
そのひとは遂に来た。**(122頁)
そして・・・。
映画ならその瞬間をスローモーションで表現するだろう。そしてそのひとの動きが止まった瞬間からその姿が次第にハレーションを起こして消えていく・・・。エンドロールが流れ出す・・・。で、そのひとのところではあのひとの名前が・・・って、一体誰?