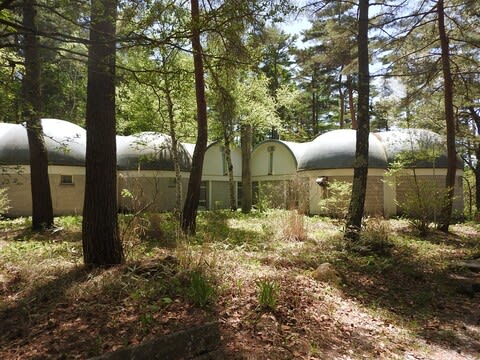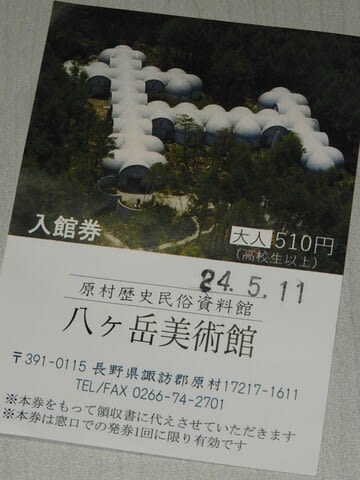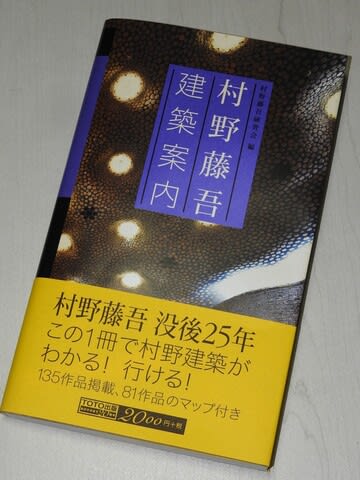420
420
■ 安部公房の『壁』(新潮文庫1969年発行1975年7月20日15刷)を読んだ。初読は高校生の時だったと思う。貼ってある水色のテープで10代、20代の時に読んだ本、ということが分かる。高校生の頃、同期生の間では安部公房と大江健三郎に人気が集中していたと記憶している。
『壁』には「S・カルマ氏の犯罪」「赤い繭」「洪水」「魔法のチョーク」「事業」「バベルの塔の狸」の6編が収められている。どれもシュールな作品で、読み解くのが難しい。
6編の中で一番長い作品「S・カルマ氏の犯罪」の主人公はある朝、自分の名前を喪失してしまう。わずか5頁の「赤い繭」では、主人公が自分の家を失い、せっかく家が出来ても今度は自分が消滅、いや透明人間になってしまう・・・。
また「洪水」では**不意に体の輪郭が不明瞭になり、足のほうからとろけ、へなへなとうずくまり、(中略)最後に完全な液体に変って平たく地面に拡がった。**(146頁) 世界のいたるところで始まった人間液化が様々な混乱を引き起こす。例えば**一村の農民全部の液化による小洪水などが、相ついで新聞紙上につたえられた。**(147頁)また**蒸気機関車の鑵は液体人間の混入で全く役に立たなかった。**(148頁)などということも。
「バベルの塔の狸」の主人公は自分の影をなくし、やがて自分の肉体も消えて透明人間になる・・・。
安部公房は人間が存在することの意味を問う。この本に収録されているのは初期の作品だが、その後も安部公房は人間の属性を喪失させている。『他人の顔』は顔の喪失、『砂の女』『箱男』は存在・帰属の消去・喪失・・・。
以下は既に書いたことだが、再掲する。名前、顔、帰属社会、そして故郷。属性を次々捨ててしまった人間の存在を根拠づけるのもは何か、人間は何を以って存在していると言うことができるのか・・・。人間の存在の条件とは? 安部公房はこの哲学的で根源的な問いについて思索し続けた作家だった。
手元にある安部公房の作品リスト
新潮文庫22冊 (文庫発行順 戯曲作品は手元にない。2024年3月以降に再読した作品を赤色表示する。*印は絶版と思われる作品)
今年中に読み終えるという計画でスタートした安部公房作品再読。5月25日現在10冊読了。残りは12冊。今年3月に出た『(霊媒の話より)題未定 安部公房初期短編集』(新潮文庫)を加えたとして13冊。6月から12月まで、7カ月。2冊/月で読了できる。 5月は既に3冊読んで、ノルマクリア。
5月は既に3冊読んで、ノルマクリア。
『他人の顔』1968年12月
『壁』1969年5月
『けものたちは故郷をめざす』1970年5月
『飢餓同盟』1970年9月
『第四間氷期』1970年11月
『水中都市・デンドロカカリヤ』1973年7月
『無関係な死・時の壁』1974年5月
『R62号の発明・鉛の卵』1974年8月
『石の眼』1975年1月*
『終りし道の標べに』1975年8月*
『人間そっくり』1976年4月
『夢の逃亡』1977年10月*
『燃えつきた地図』1980年1月
『砂の女』1981年2月
『箱男』1982年10月
『密会』1983年5月
『笑う月』1984年7月
『カーブの向う・ユープケッチャ』1988年12月*
『方舟さくら丸』1990年10月
『死に急ぐ鯨たち』1991年1月*
『カンガルー・ノート』1995年2月
『飛ぶ男』2024年3月
*記事中の過誤を訂正しました。

















 480
480
 360
360














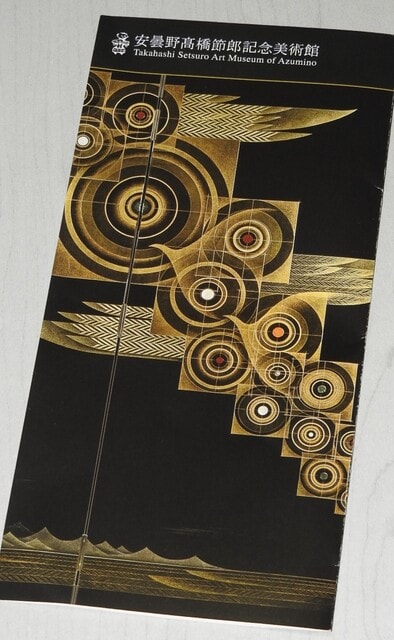






 360
360
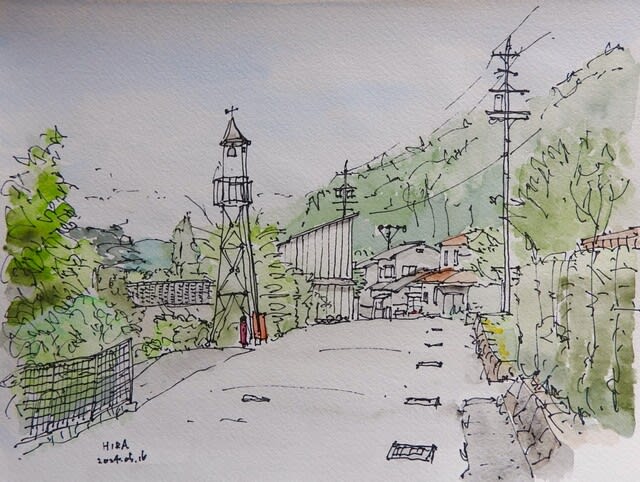





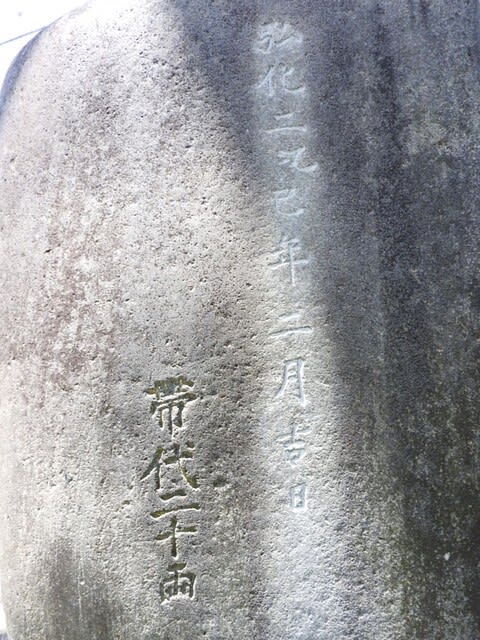

 360
360