看板建築


■ 看板建築という名称は今から30年くらい前に建築史家・藤森照信さんよってつけられた。
『日本の近代建築 大正・昭和篇』藤森照信/岩波新書に**震災復興期の東京の下町には、震災前の軒の出た木造の町屋に代り、正面を立て板状にし、その上に銅板、モルタル、タイルを張って面白い飾りをつけた木造の商店建築が軒を連ねるが、こうした〝看板建築〟と呼ばれる形式(後略)**(135頁)という説明がある。
上の写真は品川駅のすぐ近くで見かけた看板建築(木造2階建の商店)の戸袋に施された銅板の造形。戸袋の意匠をこのようにすべて変えている。職人がいきな遊び心を発揮した、といったところか。
正面の壁面をこのようにしたのは意匠上だけでなく防火性能を少しでも向上させて延焼を防ぐという防災上の理由もあったのだろう。
あまり時間がなくてじっくり観察できなかったのは残念。

同行のN君から提供を受けた全景写真 撮影120822

看板建築@東京銀座 撮影060408











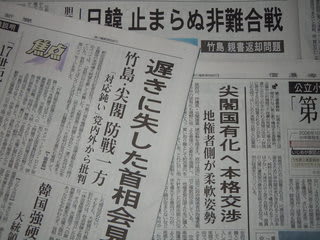
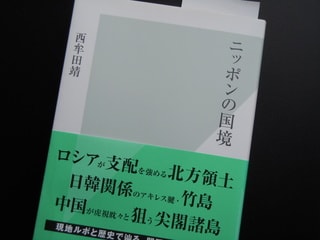
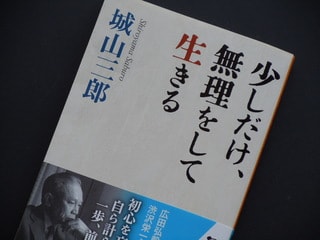

 340
340



 339
339




 338
338
 330
330
 331
331
 332
332

 333
333
 334
334
 335
335

 336
336



 337
337



















































