
■ ブログが3日更新されないと、どうしたのかなって思ってしまう、Kさんから何年か前に言われた。で、更新する。
訳あって(*1)数日前に『どくとるマンボウ青春記』北 杜夫(中公文庫1973)の何回目かの再読を始めた(過去ログ)。今日(29日)の朝カフェでも読んだ。
本に水色のテープが貼ってあるが、これは20代に読んだ本の印。ちなみに30代に読んだ本には緑色、40代に読んだ本には黄色のテープが貼ってある。50代になっても続けたかったが、松本でこのテープ(レトラライン)が入手できなくなり、止めてしまった。
**春、西方のアルプスはまだ白い部分が多かった。三角形の常念ヶ岳(*2)がどっしりとそびえ、その肩の辺りに槍ヶ岳の穂先がわずか黒く覗いていた。島々谷のむこうには乗鞍が、これこそ全身真白に女性的な優雅さを示していた。朝、アルプスに最初の光が映え、殊に北方の山々は一種特有のうす桃色に染るのであった。**(54頁)
2月4日は立春。まもなく、このような光景を見ることができる。
明日の朝もカフェでこのエッセイを読むつもり。
*1 いずれ「訳」を明らかにしたい。
*2 文中の表記










 360
360 360
360


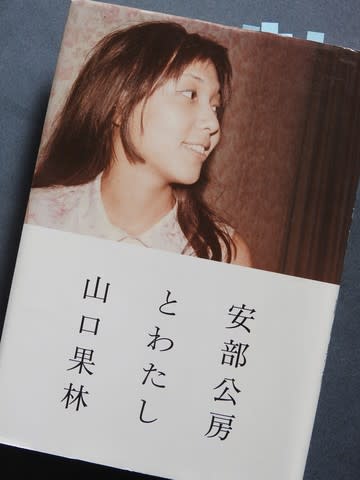
 360
360

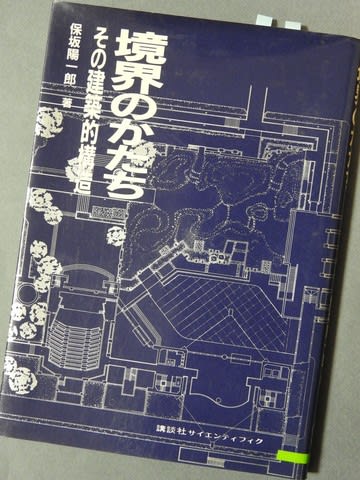 320
320












 360
360