
■ 久しぶりのアップです。今回は長野県飯山市の民家(198008)。茅葺き屋根の場合15~20年位で葺き替える必要がありますが、かなり費用がかかることや人手不足(地域力の低下)などの理由で茅葺き屋根をこのように鉄板で葺いてしまう例が多いです。
風景によく馴染む茅葺きの民家が今ではあまり残っていません。残念なことです。この屋根も鉄板で葺いてしまっています。煙出し(だと思います)は塞がずに残しています。それが特徴的な外観をつくっています。職人さんの心意気を感じます。

■ 久しぶりのアップです。今回は長野県飯山市の民家(198008)。茅葺き屋根の場合15~20年位で葺き替える必要がありますが、かなり費用がかかることや人手不足(地域力の低下)などの理由で茅葺き屋根をこのように鉄板で葺いてしまう例が多いです。
風景によく馴染む茅葺きの民家が今ではあまり残っていません。残念なことです。この屋根も鉄板で葺いてしまっています。煙出し(だと思います)は塞がずに残しています。それが特徴的な外観をつくっています。職人さんの心意気を感じます。
■ 久しぶりに出かけた書店で手にした『「縮み」志向の日本人』李 御寧/講談社学術文庫、明日読もう。
**小さいものに美を認め、あらゆるものを「縮める」ところに日本文化の特徴がある。世界中に送り出された扇子、エレクトロニクスの先駆けとなったトランジスタなどはそうした「和魂」が創り出したオリジナル商品であった。他に入れ子型・折り詰め弁当型・能面型など「縮み」の類型に拠って日本文化の特質を分析、〝日本人論中の最高傑作〟と言われる名著。** だそうだ。
彼岸過ぎから読み始めた『彼岸過迄』新潮文庫だが、この小説は漱石が修善寺での大患(このとき漱石は臨死体験をしていると何かで読んだ記憶がある)後に初めて書いたそうで、**久し振りだから成るべく面白いものを書かなければ済まないという気がいくらかある。**と連載を始めるに際して書いている。
100頁過ぎまで読み進んだところで、ようやく小説が動き出した。これから面白くなるのかもしれない。途中で投げ出すことなく最後まで読もう。文豪の作品だもの・・・。


■ 国立新美術館については既に書きました。先日亡くなった黒川紀章さんにこの作品以降、竣工した作品があるのかどうか分かりませんが、たぶんこの美術館が最後の作品でしょう(日本設計との共同設計)。
相反するが共に不可欠な要素の「共生」。当初は対象が建築と自然だったと私は理解しているのですが、機械の時代と生命の時代、過去と現代、グローバリズムとローカリズムという相反する思想、というようにこの「共生」という概念は次第にその対象が広がっていったのでしょう。
この美術館ではいくつかの共生が具現化されていると黒川さんは説明しています(「新建築」07/1月号)。
歴史的建造物(旧陸軍歩兵第三連隊兵舎:写真の左側の建物)と新しい現代建築との共生、規則と不規則(円錐と曲面のガラスの壁、両者は機械の時代と生命の時代の象徴と捉えることも可能)の共生、そして本来の建築と自然の共生・・・。
「共生(きょうせい)」は仏教用語の共生(ともいき)に由来するそうですが、50年も前から黒川さんが提唱してきたこの言葉は、いまや政治の世界でも使われるほど馴染みになりました。
建築は思想、哲学の表現手段ともなり得る奥の深い存在、ということを私は黒川さんの著書や雑誌に掲載される論文によって理解しました。因みに丹下さんの作品によって建築は美しいものということを知りました。
黒川さんの追悼記事が週刊誌などに掲載されていますが、建築家としての評価よりも先の選挙でのパフォーマンスによって奇人・変人として取り上げられていること、関心の対象が専らそこにあるということが残念でなりません。
■ **氷点下20度を下回る日が珍しくない旭川市では、2003年に20人を越える野宿者が確認された。その中には雪が膝上まで積る河川敷の橋の下をテント地で覆って通年を過ごす54歳の女性もいたという。** 
日本の野宿者の過酷な生活のルポルタージュ。「野宿から脱出したくても脱出できない」実態が次から次へと紹介される。
多くの人は、野宿に至ったことを「社会の問題」ではなく「本人の問題」だと捉えがちである。しかし著者はそうは捉えない。椅子とりゲームに喩えて社会の構造的な問題なのだ、と指摘する。
著者は20年以上も野宿者の支援活動に携わってきたという。その活動を通じて見てきた社会の「最底辺」に生きる人たちの極貧の日常生活。
もうらしい(気の毒な、かわいそうなという意味の信州の方言)生活ぶりに思わず涙ぐんでしまった。
帯に「若者に告ぐ!」とあるのは現在400万人ともいわれるフリーターから野宿者になっていくパターンが仮に1パーセントだとしても4万人、5パーセントなら20万人!にもなるからだ。
『ルポ最底辺 ----不安定就労と野宿』生田武志/ちくま新書

■ 建築家の黒川紀章さんが亡くなった。
建築家の書いた本で最初に読んだのが黒川さんの『情報列島日本の将来』第三文明社だった。これは黒川さんが30代のときに書いた本だが、既にこの本の「二元論からの脱出」という章で「共生」という概念について触れている。
日本の伝統的な住宅にみられる縁側、内でも外でもない空間。建築と自然とを繋ぐ役割を果たす「縁」。建築と自然、あるいは都市との共生はこの「縁」空間、「中間領域」を設けることで可能となる。要するにこういう考え方だと私は理解している。
この考え方を最も明快に具体化したのが福岡銀行本店だと、私は思う。アーバンルーフという屋根のついた屋外空間を都市に開放している。学生時代に見学に出かけてこの空間に設えてある黒御影石のベンチに座ったことを今でも憶えている。
黒川さんは建築のみならず中国やロシアの地方都市の計画なども手掛けて、国際的に活躍した建築家だがその実績に相応しい評価を必ずしも得ていないように思う。何故だろう。
この本に黒川さんが自身の人生を総括する文章を載せている。
**黒川紀章は自ら、建築家であるまえに、思想家であると語っていた。一九六〇年から彼が語り、書いた言葉=コンセプトは、新陳代謝、循環(リサイクル)、共生、突然変異、情報、生態系(エコロジー)、中間領域、曖昧性、遺伝子、アブストラクト・シンボリズム等、実に目まぐるしい。しかし、四十年の創作活動の末に、それらがすべて生命の原理の基本コンセプトであるという種明しをされると、その思想の一貫性に驚かざるを得ない。(中略)アブストラクト・シンボリズムは、彼の創作活動の作法(手法)とでもいうもので、近代建築の遺産としての抽象化を継承しながら、それぞれの異なる土地や文化のアイデンティティをシンボリズムとしてとり入れようとするものであった。(後略)**
黒川さん、長い間お疲れ様でした。

■『深層社会の点描』筑摩書房 この本の発行は1973年、もう30年以上も前のこと、随分昔の本だ。この本には松本清張の作品の評論が収録されている。
二つの要素(具体的には人)の対照を強調しながら、両要素の遭遇ないし符合を描くこと、つまり異次元の遭遇、これが松本清張の小説の特徴だと著者の作田啓一氏(社会学者)は指摘している。
昨年も書いたと思うが、清張の代表作の「砂の器」や「ゼロの焦点」、「球形の荒野」などは将にこの異次元の遭遇をモチーフにしている。異次元の遭遇によって生ずる悲劇、ドラマ。例えば「砂の器」は主人公の作曲家(TVドラマでは中居君が演じた)と彼の遠い過去を知る現役を引退した警察官との遭遇が生んだ悲劇(殺人)を描いている。
ところで異次元の遭遇は小説や映画(例えば「ET」)の世界だけに限られているわけではない。
以下本題。
建築の世界。例えば老人デイサービスセンターと保育園や小学校との一体的整備、従来全く異なる施設として個別に計画されていた異次元の両者が遭遇することによって新しい価値というか意義が生まれる。ショッピングセンターと映画館との複合施設についても同様の捉え方ができそうだ。あるいは建築とは無縁なところで使用されている材料の建築への応用なども同様。
他の世界にも同様の事例をみることができるだろう。全く無関係な産業どうしの遭遇、例えば医学と農業技術の遭遇。全く無関係な世界に身を置く人どうしのコラボ。
「異次元の遭遇」という視点からの発想、それは新しい産業開発や商品開発など様々な分野で有効のように思われる。
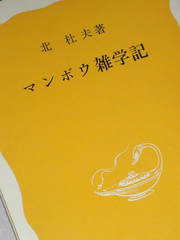

■ 『マンボウ雑学記』 この新書を手にしたときは岩波新書も変ったものだ、と思った。1981年、26年前のことだ(この年に読んだ本が時々出てくるが偶然)。
「はしがき」に著者の北杜夫が書いている。**これは伝統ある「岩波新書」にはふさわしくない本である。むしろ、中学生や高校生むきのエッセイといってよい。**
著者の謙遜もあるだろう、内容は総じて難しくて対象が中高生かどうか。 だが確かにこれはエッセイ、だから読了後に先のような感想を持ったのだった。
今は新書ブーム。新書の創刊が続いた。そして新書のイメージも変わった。エッセイが新書に収録されることも別にめずらしいことではなくなった。
今日『池辺の棲家』を読み終えた後、この長いタイトルの本を手にした。新書だがこれもエッセイ。著者は映画の字幕翻訳者の太田直子さん。海外の映画作品翻訳の舞台裏、それに気になる日本語について綴っている。
男「どうしたんだ」
女「あなたが私を落ち込ませているのよ」
男「僕がなにかしたか」
吹き替えならこれで問題はないが、字幕は一秒四文字が原則だそうで、
男「不機嫌だな」
女「おかげでね」
男「僕のせい?」
と、こんな字幕ができあがるのだそうだ。流石、という他ない。でも著者はこれを苦肉の策だと書いている。女の台詞で皮肉がすんなり伝わるかどうか気になるとのこと。きちんと伝わると僕は思うけれど。
長いタイトルは日頃のうっぷん(?)晴らしか?
日本語の誤用などについての厳しい指摘はきちんとした文章を書こうと思っているブロガー必読かも知れない。
著者はこんな指摘もしている。**時間とカネの節約。このふたつを最優先にする効率主義がちまたにあふれている。質を保つために必要な時間(労力)とカネを惜しめば、世界は低劣で薄っぺらなものになってゆくだろう。けれどもヒトは順応性が高いので、いつの間にかそれに慣れてしまう。怖いのはそこだ。**
どこかの業界にも当て嵌まるこの鋭い指摘、「正鵠を得ている」って言うんだっけ。
『字幕屋は銀幕の片隅で日本語が変だと叫ぶ』太田直子/光文社新書

■ ブログの背景を秋色に替えてみました。写真のマットとしては無彩色、グレーの方が好ましいと思いますが、ま、いいでしょう。お気に入りに登録してときどきお邪魔しているブログのいくつかが、テンプレートを最近替えているのを見て、私も替えよう、と思いました。
さて、今回は加藤幸子(ゆきこ)さん。カバーの折り返しに載っているプロフィールによると、1936年、札幌生まれ。83年には「夢の壁」で芥川賞受賞、91年「尾崎翠の感覚世界」で芸術選奨文部大臣賞、02年には「長江」で毎日芸術賞を受賞している、とのことですがこの作家の作品を読むのは初めてです。
桜庭一樹さんのコピー「女の人生の黄昏は、かくも色あざやかに静ひつであるのか。」 これで手にしました。この作家、名前から男性と思ってしまいますが、若い女性ですよね。週刊ブックレビューにもゲスト出演したことがあります。私の興味からは、かなり離れた世界を描いている方で、全く読んだことがありません。
加藤幸子さん、衒いのない静かな文章を書く方です。今日は体育の日、でも雨模様。予定していた屋外作業もウォーキングもできません。こんな日は読書に限ります。今日こそどこか落ち着くところで、ゆっくり『池辺の棲家』を読みたいと思います。
今日はこの小説を読むのに相応しい雨の休日です。

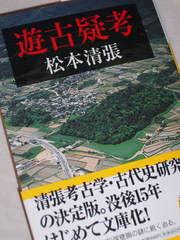
 『ねじれた伊勢神宮』宮崎興二/祥伝社文庫については既に書いたかも知れない。「かたち」が支配する日本史の謎 というサブタイトルで分かるように「かたち」には意味があるという視点から日本の遺構のさまざまな謎に挑むという試みをまとめたもの。
『ねじれた伊勢神宮』宮崎興二/祥伝社文庫については既に書いたかも知れない。「かたち」が支配する日本史の謎 というサブタイトルで分かるように「かたち」には意味があるという視点から日本の遺構のさまざまな謎に挑むという試みをまとめたもの。
この本には前方後円墳が取り上げられている。そう、中学で習う前が□、後ろが○という意味の古墳。この名前が初めて現れるのは江戸時代、蒲生君平の「山陵志」ということだが、歴史に疎い私はこの書を知らない。
松本清張がこの「前方後円」という捉え方に疑問を呈し、前後ではなく左右に並んでいるのだという説を唱えたということも紹介されている。
以前この本を読んだとき、「前方後円」と判断する根拠も知ることなくただそのように憶えたことを思い出し、清張の「定説」を疑う探究心に感心させられた。
そのときから清張説を読んでみたいと思っていたが、今日書店で見つけた。
『遊古疑考』河出文庫。松本清張はこの文庫の「前方後円」墳の謎と題する章で自説を展開している。明日、読みたい。
さて「フラガール」!

■ うっかりしていた。もう10月。9月の本たちのアップを忘れていた。
あっという間に9月は過去に流れていった・・・。ブログで取り上げた本も少ない。
『忘却の河』福永武彦/新潮文庫が復刊された。26年ぶりの再読。


■ 川上弘美の『センセイの鞄』が新潮文庫に収録されました。文春文庫には既に3年前に収められています。どちらも上品な装丁。解説者が違います。文春文庫の木田 元さんはセンセイのモデルでは?と噂になったとか・・・。二人の対談を雑誌で読んだ?、という曖昧な記憶があります。
私は単行本(平凡社)で読んで文春文庫で再読しましたが、新潮文庫ファンとしてはどうしようかなと迷うところ。 また読みたくなったらそのときは新潮文庫を購入することにします。
『パレード』も文庫(新潮文庫)になりました。単行本(平凡社)には絵本のような雰囲気が漂っています。センセイとツキコさんのもうひとつの物語。こちらは文庫本も迷うことなく購入する予定です。
この作家の本は新潮社、講談社はもちろん、岩波書店(「なんとなくな日々」)、日本経済新聞社(「此処彼処」)、中央公論新社(「光ってみえるもの、あれは」)、平凡社などあちこちの出版社から出ています。
特定の出版社に限定している作家もいます。人気作家だからいろんな出版社から依頼があるんでしょうか。その辺の事情を知りたいと思うのですが・・・。