■ 1928年(昭和3年)に建設されたという木曽の旧黒川小学校を大規模改修して出来た「木曽おもちゃ美術館」(実質的には子どもたちがいろんなおもちゃを使って遊ぶスペースがいくつも創りだされた施設)が昨年(2022年)11月にオープンしていた。SNSで紹介されているこの「美術館」を見て、見学に行きたいなぁ、と思っていた。 ⓪
⓪
国道19号を南下、木曽大橋の信号を右折して4,5km走行、目的の「木曽おもちゃ美術館」に着いた。 ①
①
エントランスに施設の案内図が掲示されていた。⓪で右奥に写っているのが「たいけんのやかた」。 ②
②
「であいのやかた」と体育館をリノベーションしてできた美術館「おもちゃのやかた」とをつなぐ朱塗りの開放廊下。構造的に特別なことをしているわけではない。色でこんなに印象的で魅力的になるとは・・・。 ③
③
「おもちゃのやかた」の玄関から中に入ると、真正面にこのシンボルツリーが立っている。樹齢約250年の木曽ヒノキだという。 ④
④
体育館だったから、階高が高い。中間に床面を新たにつくって、2層の空間に改造している。④は上階からステージを見たところ。 ⑤
⑤  ⑥
⑥
⑤はステージを背に2階へ上る階段、小屋組みを見たところ。既存の天井を撤去して露出した洋小屋トラスを補強している。水平構面をきっちりつくることで、各トラスを一体化する効果があるだろう。元々あった小屋組部材と補強部材とが魅力的な空間を創出している。新旧部材の一体化の魅力、と評すれば良いだろうか。④でわかるようにステージをそのまま残しているが、これは新旧空間の一体化の魅力であろう。上手いデザインだと思う。 ⑦
⑦  ⑧
⑧
上階(2階)の様子 利用者は何人もいたが極力写らないようにした。 ⑨
⑨  ⑩
⑩
下階(1階)はアリーナだった大きな空間をいくつもの小さな空間に区切って、子どもたちにフィットさせている。2階の床を支えるために柱を何本も立てる必要があり、そのことを上手く活かしている。 ⑪
⑪  ⑫
⑫ ⑬
⑬  ⑭
⑭
⑬「であいのやかた」のカフェ
⑭「たいけんのやかた」の廊下 ちょっとした設えがアクセントになって、魅力的な空間になることの好例
リノベーションの手本のような建築だった。 昨日なぎさちゃんを見て、明日は好いことがあると思った。確かに好い日だった。




















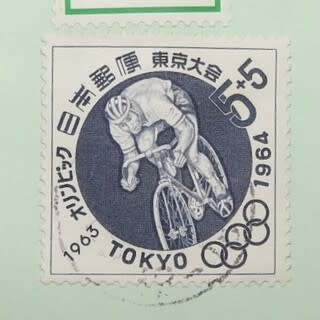















 ①
① ②
② ③
③ ④
④
 ①
① ②
② ③
③ ④
④









 280
280








