■ 今年2024年は安部公房生誕100年。『芸術新潮』は3月号で安部公房の特集を組んだ。「わたしたちには安部公房が必要だ」と題して。今年は安部公房を読もう!と思い、3月から手元にある新潮文庫を読み始めた(現在手元にある新潮文庫は新たに買い求めたものを含めて23冊)。
『無関係な死・時の崖』(新潮文庫1974年)を読み終えた。今からちょうど50年前に読んだ文庫。
この文庫には短編10編が収録されているが、安部公房がいかに発想力・構想力が優れていたか、よく分かる。印象に残ったのは表題作の「無関係な死」、それから「人魚伝」と主人公が建築士の「賭」。
「無関係な死」
ある日、アパートの自分の部屋に死体が置かれていた男が、あれこれ考える。**犯人が、計画的に彼の部屋をねらったのか、それとも行き当たりばったりに、彼の部屋がえらばれたのか、その点はまだよく分からない。**(178頁)
男は死体を他の部屋に運ぶことにする。自分とは無関係な死とするために。
**そうだ、彼の部屋にこの死体を持ち込んで来たものだって、案外同じように誰かから押しつけられた組だったのではあるまいか。死体は、アパートの中を、ぐるぐるたらい廻しになっているのかもしれないのだ。**(182,3頁)
部屋には男の無罪を証明してくれるような証拠があった。男がそのことに気がついたのは、その証拠を消してしまった後だった・・・。推理小説として、おもしろい。
「人魚伝」
沈没船の中で出会った人魚に恋した男が、彼女を連れて帰り同棲生活を一年以上続けるという話。
**なにしろ彼女の下半身は魚なのだ。下腹部に、産卵用とおぼしき穴はあいていたが、そんな穴なら、耳にだって、鼻にだってあいている。**(234頁)**ぼくたちの性は、眼と唇の接触をつうじて、満たされていたようなものだった。**(234頁)
この辺りまでは大人のファンタジー(かな?)といった趣だが、この後はホラーな展開になる。
「賭」
**「しかしですねえ、この社長室は、三階にあるわけですな。そして十七号室は、二階なんですからね。」
「そうですか・・・・・二階と三階の部屋を隣りあわせにするのは、相当にむつかしい技術でしょうな。」**(101頁)
宣伝事業をしている社屋の設計を担当している主人公が、依頼主の仕事の実情を知るために、その会社を訪ねる。会社で見聞きした不思議なというか、風変わりなできごと・・・。
**こうした風変りな体験が、依頼主の注文を理解するうえで、すこぶる有意義な、みのり豊かなものであったことは、あらためて説明するまでもないだろう。おかげで私は、三階の部屋が、六階の部屋と壁を接していようと、また階段を降りて上階に達することになっていようと、すこしも意に介さないまでになっていた。仮に、天井と床とを逆さにしなければならないような羽目におかれたとしても、たぶん平然として応じていたに相違ない。**(136頁)
三次元的な空間では実現できない。そこで設計を担当する主人公が採った方法・・・。これはSF、それも50年も前の。
推理小説、ホラー小説、そしてSF小説。10編も収録されている傾向の異なる作品たちが、冒頭に書いたように安部公房が発想力・構想力に優れた作家であることの証左だろう。短編集の魅力はこういうところにもある。
この文庫のカバーには**未知の小説世界を構築せんとする著者が、長編「砂の女」「他人の顔」と並行して書き上げた野心作10編を収録する。**と書かれている。
やはり安部公房は凄い作家だったと思う。文庫本の大半を処分した時、再読するなら安部公房と思って、夏目漱石、北 杜夫の文庫と共に残しておいたが、正解だった。
手元にある安部公房の作品リスト
新潮文庫23冊 (文庫発行順 戯曲作品は手元にない。2024年3月以降に再読した作品を赤色表示する。*印の5作品は絶版)
今年(2024年)中に読み終えるという計画でスタートした安部公房作品再読。8月24日現在15冊読了。残り8冊、9月から月2冊。
『他人の顔』1968年12月
『壁』1969年5月
『けものたちは故郷をめざす』1970年5月
『飢餓同盟』1970年9月
『第四間氷期』1970年11月
『水中都市・デンドロカカリヤ』1973年7月
『無関係な死・時の壁』1974年5月
『R62号の発明・鉛の卵』1974年8月
『石の眼』1975年1月*
『終りし道の標べに』1975年8月*
『人間そっくり』1976年4月
『夢の逃亡』1977年10月*
『燃えつきた地図』1980年1月
『砂の女』1981年2月
『箱男』1982年10月
『密会』1983年5月
『笑う月』1984年7月
『カーブの向う・ユープケッチャ』1988年12月*
『方舟さくら丸』1990年10月
『死に急ぐ鯨たち』1991年1月*
『カンガルー・ノート』1995年2月
『飛ぶ男』2024年3月
『(霊媒の話より)題未定 安部公房初期短編集』2024年4月






































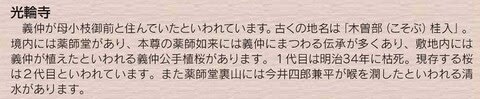



 ①
①  ②
② ③
③ ④
④
