
○ 最初のブックレビュー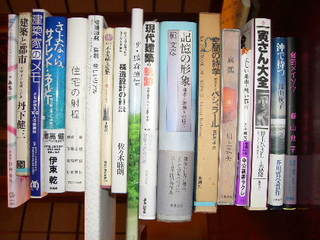
○ 今年最後のブックレビュー
来年はどんな本と出会うことができるだろうか。

雑誌「yom yom」をやっと入手した。川上弘美の小説が掲載されている新潮社の新しい雑誌。今人気の作家の読み切り小説やエッセイ満載、どうやらこの雑誌で年越し読書ということになりそうだ。
この雑誌に掲載されている角田光代の「涙の読書日記」の書き出し**一日の隙間時間に、読書が挿入されている。**は最近の私の読書スタイルそのものだ。
昨日、隙間時間に『海の仙人』絲山秋子/新潮文庫を読んだ。帯には**孤独に向き合う男女三人と役立たずの神様が奏でる不思議なハーモニー**とある。男女三人、なぜか男二人と女一人という組み合わせかと思ってしまったが男一人と女二人の恋愛物語だった。恋愛物語と捉えるのは少し違うような気もするが・・・。
主人公、河野勝男は元デパートの店員、宝くじで三億円当たって勤めを辞めて敦賀で生活している。・・・とあらすじを書き続けてもよいが省略。勝男と全くトーンの異なるふたつの恋愛を展開するのがデパートで同期だった片桐妙子と偶然敦賀の港で出会った中村かりん。
片桐は『沖で待つ』に登場したわたしとよく似たキャラの女性。二人の交わす会話も「おう、片桐、相変わらず、柄悪いなあ」「カッツォも相変わらずさえないなあ」こんな調子で『沖で待つ』のわたしと太っちゃんの会話と雰囲気が似ている。そして二人の関係も似ている(06/04/19のブログ)。 勝男が三億円当たったとき使途を相談したのも片桐だった。
一方、勤めの休みを利用して敦賀にジープで出かけて来たかりんは子供のころ読書魔だったという女性。かりんとの恋愛は予想外の方向へ展開して・・・。ラストは具体的には書かない、「涙」とだけ書いておく。
どうも絲山さんは欲張りすぎたのではないか、と読了後思った。それぞれ別の小説に仕立ててもよかったのではないかと。尤もふたつの恋愛を対比的(とも違うかな、この辺がまだ消化できていない)に描くというのが絲山さんの「意図」のようにも思われるが。
勝男と片桐とで『沖で待つ』のような物語を最後まで展開して欲しかった。かりんとの悲しい物語はこの作家のイメージからは遠いような気がする。『絲的メイソウ』で懐いた印象から、そう思う。 もっと別の作品を読めば、あるいは印象が変わるのかもしれないが。


駅は駅舎の後方にホームがいくつか並びその上に通路が架かるという空間構成が共通している。「茅野市民館」は大小ふたつのホール、美術館、図書館そしてレストランからなる複合施設だが、駅のホームを建築化したような図書館が特徴だ。
上の写真はホーム上の通路から図書館部分の外観を撮ったもの。図書館がホーム上の通路に直結していて利用者はあたかもホームに降りていくかのように図書館に入ることが出来る。
下の写真は、図書館の内部を撮ったもの。ホームと同様に直線状に長い。一番奥が通路からのエントランス。ゆるやかなスロープ状の床で地上レベルまで下ろしている。円柱のブースはトイレ。
設計者の古谷誠章さんは、現地を訪れて直ちに図書館を駅の通路に直結させようと思ったそうだ。学校帰りの高校生達がホーム上の通路で所在なげに列車を待つ姿を見かけたらしい。そのユニークなアイデアが決め手となってプロポーザルで設計者に選ばれたという(「新建築」05/11)。
プロポーザルやコンペ(両者は明らかに異なるがしばしば曖昧に扱われる)に勝利するには「ひらめき」が必要だ。他の応募者が到底考えつかないようなユニークなアイデア。
伊東さんは「まつもと市民芸術館」のメインホールで、前面の道路側に客席を向けるというアイデアを提示した。応募案の中でそのような提案は他には無かった。普通にプランニングすれば一番奥がステージになり客席は道路に背を向ける。
かつての学校のように「雛型」に倣って設計すればOKという時代は終った。個々のケースごとに独自の解法を示さなくてはならない。設計の苦しみでもあるが楽しみでもある。固定観念にとらわれない自由な発想、脳みそを柔らかく保たなくてはならない・・・。

今年もあと一週間。午前中、書店に出かけた。年内に読み終えることが出来なければ、「年越し本」となる本を探す。
吉村昭さんの遺作短篇集『死顔』はモノトーンの静かな装丁、読みたい一冊。吉村さんの作品は何作も読んだが、中公文庫はいままでほとんど手にしなかった。『秋の街』、誠実な人柄が滲み出る吉村さんの小説は年末に相応しいだろう。
絲山秋子さんの作品が文庫になった。『海の仙人』、初めての新潮文庫だから背表紙の色は白。2冊目が出るときに絲山さんの希望も考慮して決められることになるだろう。彼女がユニークなキャラ、ということは『絲的メイソウ』というエッセイ集から分かるが、どんな色に決まるだろう。
『美しい都市 醜い都市 現代風景論』五十嵐太郎/中公新書
帯の「カオスか秩序か」が気になって手にした。ぱらぱら頁をめくって芦原義信の『東京の美学-混沌と秩序』岩波新書をとり上げていることを知った。このところ都市の景観についてときどき考える。
他にも『フェイク』楡周平/角川文庫 など気になる本は何冊かあったが、結局購入したのは写真の3冊。
『空海の風景 上、下』司馬遼太郎/中公文庫 をようやく読み終えたがクリスマスに空海はないだろう、後日書きたい。
Merry Chirstmas 


**締め切りの直前まで書かないでおいて、何日かでわーって書くこともあるんですけどね。今回は同じペースで書いては消し、これという言葉が見つかるまで手触りを確かめつつ書いていきました。**
週刊ポストの「著者に訊け」というコーナーで『真鶴』(以前書いたので内容は省略する(06/11/11))について著者の川上弘美さんがインタビューにこう答えていた。確かにこの作品には川上さんの今までの作品とは異なる雰囲気が漂っている。ひらがなの多用、句読点の多用もその要因だろう。
今朝の週刊ブックレビュー(NHK衛星第2 朝8時から)の書評コーナーでこの本がとり上げられた。今回の書評ゲストは編集者の松田哲夫さん、作家の吉川潮さん、翻訳家の鴻巣友季子さんの3人。
不思議なとしか表現のしようのない読後感、真鶴という絶妙な場所の選定、川上さんしか表現できない言葉の魔術、昼でも夜でもないような時間をゆっくりたどって行く、微妙な心の狭間を行ったり来たりする、ことばと表現と物語が渾然一体となっている、ことばが柔らかいが強い・・・。
書評ゲストのコメントを書き並べると、この小説の独特な雰囲気が少しは伝わるかもしれない。
「存在と不在のあわいを描いた作品」(推薦した鴻巣さんのこのコメントに同感)、今年一番の収穫はこの作品の読者になったことだ。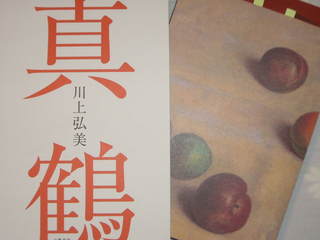
『真鶴』川上弘美/文藝春秋

『現代建築の軌跡』川向正人/鹿島出版会 のサブタイトルは「建築と都市をつなぐ思想と手法」です。2002年から2004年にかけて開催された公開対談をまとめたものです。川向さんの対談の相手は上の写真で分かる15人の建築家達でした。
過日、安藤さん設計の「表参道ヒルズ」が都市との関係を断ち切った自己完結的な建築だと書きました。内部にショッピングストリートをスパイラル状に詰め込んだ建築だとも書きました。
ところで表参道から程近い青山に「スパイラル」という名前の建築があります。設計したのは槇文彦さん。
その槇さんとの対談もこの本に収録されています。建築と都市との関係を考える上で大変興味深い内容です。そのことについて書こうと思います・・・。
タイトルはグループフォーム(群造形)、福祉施設のグループホームとは違います。
今回はその予告、次回書くことにします。
○『空間の詩学』ガストン・バシュラールは、現在ちくま学芸文庫に収められています。
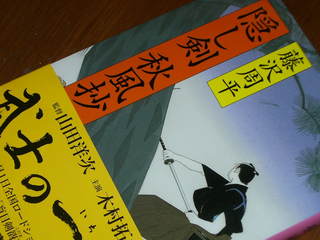
 アルコールなブログ。
アルコールなブログ。「武士の一分」の原作の『盲目剣谺返し』は文春文庫に収録されている(写真)。確か前にも書いたが、文春文庫の背表紙はピンク、藤沢周平のイメージではないのであまり手してこなかった。久しぶりに、ピンクの背表紙を購入。今日の昼休みに読んだ。映画はかなり原作に忠実につくられていることが分かったが、もちろん異なるところもある。今夜はその辺について書いてみよう。
映画では桃井かおりがキムタク(新之丞)のオバちゃん役で登場するが、原作ではふたつ年上のいとこになっている。キムタクに好意を寄せていて結婚を望んでいたが、別の男と結婚して今では子どもがふたりいる。
彼女の台詞を私なりに「ちょっと、うちのダンナが染川町で加世ちゃんが男と一緒のところを見かけたらしいんだけど、しんちゃん、大丈夫なの?」
映画でもキムタクは視力を失ってからも木剣を振ってトレーニングしているが、原作はすごい。飛来する虫を気配で察知して木剣で打ち落とす!!ことができるようになるのだから。
加世の不倫相手はキムタクの上司、近習組頭の島村籐弥という男だった。女癖が悪くてどうしようもない男だが、頭脳明晰、剣の腕もたつという設定。原作では歳が三十四となっているが映画では、中年のオッサンだった(何歳の設定かは不明)。
さて、スケベなオッサン島村との果し合い。原作ではキムタクが島村の頚の血脈を一撃で断つが、映画では腕に重症を負わせるだけ、翌日島村は自害して果てる。
そして、こらえきれずに涙したラストシーン、具体的には書かないでおく。映画は山田監督のオリジナルな演出かと思ったが、原作と細部は異なるがほぼ同じだった。
広島は呉の地ビールが効いて来た・・・。この辺で、オシマイ。



前々稿「テンプレート」で構造家の佐々木睦朗さんの書名『構造設計の詩法』をなぜか間違えて『空間の詩法』としてしまった(今日訂正しておいたが)。 よく似た書名に『空間の詩学』がある。哲学者で詩人のガストン・バシュラールのこの著作は建築を志す者の必読書といわれていた(一応、過去形にしておく)。
メモによると30年以上も前、75年の5月に読んでいる。所々にサイドラインがひいてあるから読んだとは思うが内容を全く忘れている(今は線をひく替わりに付箋紙を貼ることにしている)。書名を間違えたのは、この本を再読せよ、ということなのかも知れない・・・。次から次へと読みたい本が出てくるがいつか再読してみようと思う。
ところで、先日夜きれいなスポットとして「まつもと市民芸術館」のあわあわな光の壁を挙げたが、ここも挙げておきたい。
適度に「暗い」照明、内部が立体的に浮かび上がっている。コードペンダント他、照明計画がいいのだろう(この写真では分かりにくいが)。サッシのフレームの縦長の割り付けもなかなかいい。グリーンの文字が都会的でおしゃれ。
ここは昼より夜の方が断然きれいだ。別にスタバのファンというわけではない、ただ夜景がきれいだ、と思うだけ。
ここの2階は落ち着いて本を読むことができる空間。休日に『空間の詩学』を持って出かけよう・・・。


伊東さんが「ガウディを目ざす」と何かの席で言った・・・。藤森さんの本でそのことを知ったと前稿に書きました。
そういえば伊東さんのパートナーで構造家の佐々木睦朗さんも『構造設計の詩法』住まいの図書館出版局 で最初にガウディをとり上げていました。
ガウディか・・・
偶々手元にあった『不思議な建築 甦ったガウディ』下村純一/講談社現代新書 をぱらぱらと見ていると・・・
**人工の丘に地下鉄のコンクリート・チューブが滑り込む**
**ホームの構造を並木に見たてたクロールのスケッチ**
写真やスケッチにこんな説明がつけられています。
目次を見ると
第一章 自然と生物
第二章 洞穴
第三章 肉体
第四章 樹木
第五章 物の魂 などとあります。
このまま伊東さんの本の目次に使えそうです。
伊東さんは「新しいリアル展」に際して 現代建築に物質(もの)の力を回復するために というタイトルで文章を書いています。その点で第五章の「物の魂」というタイトルは伊東さんのこれからの方向性を表現しているかのようです。
ガウディは建築の構造や形を自然から直接学び、自然の美や合理性を建築に再構成しました。そして伊東さんはピューター・テクノロジーを駆使して自然に近い建築を創造しようとしているのでしょう。
静的で幾何学的な造形で自然との際立った対比を生み出した近代建築から自然への回帰を目指す新しい建築。 ガウディとは全く違う方法によるアプローチ、でも到達点は案外近接しているのかも知れない、そう思います。
伊東さんは**藤森さん、教えて下さい。近代建築の矛盾を見てしまった建築家に、でも頼るべき田舎も自然も無いことを知ってしまった建築家に、この先あるべき建築を・・・・・。**と問いかけました(『ザ・藤森建築』)。
その問いかけに対する自分なりの回答を見いだし、その方向に向って歩き出した。そしてその到達点を「台中」で早くも提示しようとしている。伊東さん、このような理解でOKでしょうか・・・。

■ オウム真理教による一連の事件から既に10年以上の年月が流れた。
この本の著者の伊東乾さんと、地下鉄サリン事件の実行犯の一人とは東大の同級生。実行犯は大学院で素粒子理論を専攻していた。博士課程に進学した直後に「出家」したという。そんな「優秀な科学者」がなぜ荒唐無稽な教団に入り、あのような事件を起こしたのか・・・。
裁判では決して明らかにならない心の深層に潜む「何か」。
著者は学生時代を振り返り、勾留中の同級生と接見を重ねてその「何か」を思索する。同級生と著者を分けたものはなんなのか。ほとんど偶然のような小さな分岐点・・・。
実行犯は中目黒駅で地下鉄日比谷線の先頭車両に乗り込む。新聞紙に包んだサリン入りのナイロン袋を足元にそっと置く。恵比寿駅に停車する直前にビニール傘の先端を袋に突き刺す・・・。
著者は中目黒から地下鉄に乗るところから本書をスタートさせている、十年前、同級生がとった行動をトレースするように。
『さよなら、サイレント・ネイビー 地下鉄に乗った同級生』伊東乾/集英社
第4回開高健ノンフィクション賞受賞作

○今年最後の満月、きれいです。
♪月がとってもあおいから、遠回りして帰~えろ、と思うこともなく早く帰宅。
何回目かのブックレビューです。ブログでふれた「本」が20冊になったところでアップしています。来年からはこのルールを改めようと思っています。「真鶴」が24日のNHK衛星第2「週刊ブックレビュー」でとり上げられます。3人のゲストの書評が楽しみです。今夜はあっさりこの辺で、また次回。














