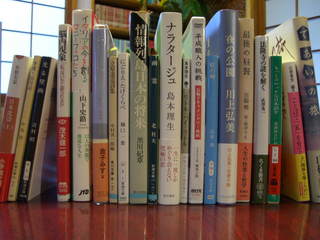■ 増沢洵さんという建築家が建坪がたった9坪の自邸を設計しました。1階が3間×3間の正方形、2階は6坪 合計15坪の住宅です。1952年に出来たこの住宅、建築界では有名で「最小限住居」と呼ばれています。
ある展覧会(1999年)でその家の骨組みが再現されました。会場は新宿パークタワーにあるリビングデザインセンターOZONE。萩原修さんはこの展覧会の担当者、この骨組みの美しさにすっかり魅せられて、この骨組みを使って自分の家を造ろう!と決心します。 
『9坪の家』は萩原さんが自邸が完成するまでの出来事を記録した本です。なんと奥さんも『9坪ハウス狂騒曲』というタイトルでやはりこの家の完成までの出来事を書いているのです。延べ床面積がたったの15坪の最小限住宅で、ふたりの小さな娘さんと共に4人で生活することの戸惑い、新しい発見。
本当に必要な物しか室内に置かない(置けない)シンプルな生活空間。今回の設計を担当した小泉誠さんによって随分モダンにリ・デザインされています。 ふたりの同じ出来事の捕らえ方の違いがよく分かって興味深かったです。
やはり記録しておくことは大切ですね、こうして本になるんですから。尤もプロフィールを読むとふたりとも書籍の編集などを手がけておられるようですが。
「仕事を家に持ち帰る」ってことは、あるでしょうが、「仕事の家を持ち帰る」ってことは、ないでしょうね。