■「バイオマス」というと最近まで家畜の排泄物や食品廃棄物(生ゴミ)から発生するメタンガスを利用して熱や電気エネルギーを供給するシステム、と理解していた。しかし実はもっと対象のひろい「生物資源」全体をさす概念であることを知った。今までの不明を恥じるばかりだ。
ネットで調べてみると「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」と定義されている。ということで「木」も含まれている。
建築するときには鉄やアルミ、石油を原料とする材料など少なからぬ資源消費を伴う。これらの地球埋蔵資源は「総量」がきまっている。ところが「木」は伐採して利用したあと植林して育てれば再び使うことができる。本来の意味で再生可能な唯一の建築資源だ。また「木」はエネルギーとしても利用できる。そう薪(熱エネルギー)として。
最近、薪ではなくて間伐材や廃材などを利用したペレットを熱源とするストーブやボイラーを設置する例が見られるようになってきた。
先日紹介した大町の住宅、床屋天井にはムクの根羽杉が使われ、リビングには暖房用のストーブ(ペレット、薪どちらでも可)が設置されている。仕上げ材と燃料、どちらも「木質バイオマス資源」だ。
利便性、経済性に押し流されて木に代表される自然素材や薪を使うかまどや風呂などが住宅から消えて久しい。
地球的な規模での資源枯渇、その対策の必要性が指摘されている。ここで数十年前の生活に戻って資源の消費を減らそう、というのはたぶん無理だろう。
でも少し「エコ」な生活をしようという意識を明確にもってそれを実践すること、これは宇宙船地球号の乗組員の責務だということに異論、反論はあるだろうか。スウェーデンのヴェクショー市では「化石燃料ゼロ宣言」をすでに10年くらい前にして、バイオマスへの転換を目指しているという。 
もう一度自分の住まいを造るという機会がもしあれば、エコロジカルな住宅を考えよう。私にはその機会はまずないと思うけれど・・・。
忘れていた、こんな講座の本を購入していたんだ。未読じゃないか、少し読もう・・・。
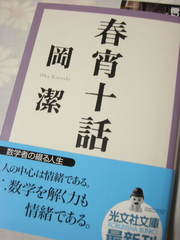
光文社文庫はほとんど手元にない、光文社新書はときどき読むのだが。
先日書店でこの本が平積みされているのを目にした。岡潔、何で今ごろ文庫に?と思いつつ手にした。1963年に毎日新聞社から単行本が出版されているようだ。この有名な数学者の専門の「多変数複素解析函数論」、って何のこっちゃ???????・・・・。
この随筆集で岡氏は自身の経験を振り返りながら教育を論じている。
このところ全国の高校で必須科目を履修していない生徒が多数いることが判明し問題になっている。受験科目にない必須科目を大学受験を優先して他の科目に置き換えて授業をしていた、ということのようだ。大学に提出する成績表のデータの捏造まで見つかっている。
こんな事態をもし岡氏が知ったらさぞかし嘆いたことだろう。改めて教育について考える、という意味でこの文庫の出版は実にタイムリーとなったと思う。
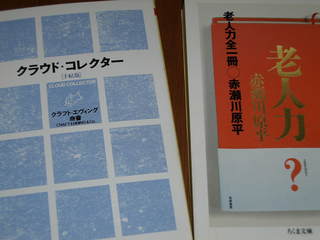
本日ちくま文庫2冊購入。
『クラウド・コレクター』クラフトエヴィング商会
友人がメールで紹介してくれた本。但し友人はたぶん単行本を読んだと思う。以前『オーデュボンの祈り』伊坂幸太郎/新潮文庫も紹介してもらった。どちらも紹介されなければまず手にすることはないと思う本だ。紹介された本は読んでみることにしている。へ~、こういう本が好きなのか・・・、と相手のことを考える。
『老人力』赤瀬川原平
実はこの本は未読、読んでおく必要があるだろうと思って購入した。
どうだ、と「老人力」をときどき自慢したい。

今回の20冊、建築関係の本と小説が並んだ。
パソコンに取り込んだときには、比較的鮮明な写真だったのに、ここにアップしたら不鮮明になってしまった。なぜだろう・・・
 写真を差し替えた
写真を差し替えた
しばらく前の新聞の文化欄に載った記事。
黒川紀章氏の代表作品のひとつ「中銀カプセルタワー」が取り壊されるかもしれない、と報じている。メタボリズムという建築思想を氏はこのビルで具現化して見せた。これ程までに明確にこの思想を建築化した例を他に私は知らない。
黒川紀章氏の思想は論文になり、あるいはこのビルのように建築として形象化されてきた。氏の場合、建築作品より世に提示してきたキーワード、例えば「共生」の方が一般にはあるいは知られているかもしれない。『けんちく世界をめぐる10の冒険』の中で伊東氏は書くこととデザインすることとは等価だと指摘している。
昨日のブログに黒川氏の著作集全18巻のパンフレットの写真を載せた。建築家で著作がこれだけのボリュームになるというのは凄いことだと思う。今年の3月に出版された『都市革命 ―公有から共有へ―』中央公論新社が100冊目だという。
40年以上にも及ぶ黒川氏の思索を網羅的に収録するという今回の企画、一番嬉しいのは氏自身であろう。
いま、定年後、来し方を振り返り自分史としてまとめることが静かなブームなのだという。この著作集は黒川氏の壮大な「自分史」だ。
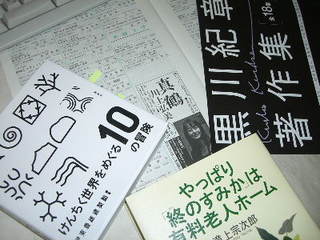
松本市内の老舗の書店に電話で注文しておいた本が今日勤務先に届いた(写真)。パンフレットは黒川紀章の全18巻!の著作集、全巻セットで105,000円。毎月1巻ずつ刊行されるなら(約6,000円/月)、購入してもいいなと思うが全巻まとめてとなるとちょっと手が出ない。「これから出る本」という近刊図書情報。ここに川上弘美の長編『真鶴』文藝春秋 今月28日発売、という広告が載っている。久しぶりの長編、楽しみだ。
前置きが長くなってしまった。
今回は『けんちく世界をめぐる10の冒険』伊東豊雄建築塾/彰国社について。1辺が13cmの正方形の本。絵本のような装丁の本だが、中身は凄い。
裏表紙には**21世紀のけんちく原理を探る、小さいけれど大きな1冊**とある。本当にそうだ、と思う。
伊東さんの最近のプロジェクトを平易にそして深く語っている。伊東さんの事務所に入所して数年の所員とのディスカッションも収録されている。
**(前略)環境が変わろうが、ある人間が生まれて死のうが、建築は変わらないという大前提があるから、正方形や円という純粋幾何学が一番美しいといわれてきたけれど、そうではない美しい建築があるのかもしれない。(中略)
エコロジーや自然とのかかわりを建築が問うのであれば、純粋幾何学の建築ではなく、別の建築のありようを求める必要がある。僕らはそれをアルゴリズムを使って示そうとしている。**
ここではアルゴリズムが生みだす美学をめぐって議論が展開している。装丁のイメージとは全く異なる高度で知的な議論だ。
僕達は空間を水平、垂直の直交座標によって認知するように「訓練」されている。それ故、建築もそのようにイメージし構成する、水平の床、垂直の壁そして天井とによって。伊東さんが「せんだい」以降に志向している流動的な建築はこのような従来の空間認知の仕方ではイメージしにくいのだという。そこでアルゴリズムという概念が登場するというわけだ。
アルゴリズムは運動を規定するのだと伊東さんは解説し、それが従来の幾何学とは違う流動的な形態をつくりだすのだという。「アルゴリズムをめぐって」というこのディスカッション01は最近の伊東さんの先駆的なプロジェクトを読み解く鍵が示されていて大変興味深い。いい本を入手できた。
○ 安曇野ちひろ美術館 ○ 安曇野ちひろ美術館外観
○ 安曇野ちひろ美術館外観 ○ 谷樋の詳細
○ 谷樋の詳細
上の写真は以前載せましたが、今回再度載せます。下の写真は工事中に見学した際、撮ったものです(当時のプリントを接写しました)。どの部分の写真かは分かりますね。屋根と屋根の間の谷樋、上の写真の白い四角い部分の詳細です。
有名建築家の作品を見学すると、こんなのありかな~、と思うようなディテールを目にすることがあります。防水をシールだけに頼っていたり、こんなに薄くて持つのかな、と積雪時の強度が心配になったり、「にげ」をとってなかったり、数年経ったら錆びるだろうな・・・といった具合に。
さて、「安曇野ちひろ美術館」の谷樋に戻りましょう。美術館をいくつかの部分に分節してそこに切妻の屋根を架けています。するとこのように谷の部分ができます。谷樋は雨仕舞い上、弱点になりやすいので、できれば避けたいところです。
内藤さんは実に用心深くこの部分を設計してあります。ドレーンの他にオーバーフロー管を2本立てています。ドレーンがもし詰まってしまってもオーバーフロー管から雨水が排出されるようにしてあるのです。この部分はステンレス防水(ステンレス板の立てはぜ葺きシームレス溶接)、施工さえきちんとしていれば一番信頼できる防水だと思います。冬期の凍結対策としてヒーターも設置する予定なのでしょう。
ところで内藤さんのデビュー作は「ギャラリーTOM」でした(私の記憶が間違っていなければ)。学生のとき見学したと思うのですが、所在地は覚えていません。確か、渋谷区だったと思います。このギャラリーの屋根はよく雨漏りしたらしいのです。そのたびに内藤さんは呼び出されてシールを打ったりして対応したらしい(昔、雑誌で読んだ記憶があります)。そういう苦い経験が雨仕舞いに対して用心深くしたのかもしれません。
『「失敗をゼロにする」のウソ』ソフトバンク新書 で著者の飯野謙次氏は同じ失敗がくり返されないような仕組みを考えなければならない、と強調しています。ま、当然な主張ですが、これがなかなか難しいのです。一度あることは二度ある、二度あることは三度ある。このことを残念ながら経験的に知っている人は多いと思います、私も含めて。

民家 昔の記録 1980.07.22
いままで、昔撮った民家の写真を何回か載せました。民家は地元産の材料を使って地元の人たちの手で造るというのが基本的な姿です。白川郷の合掌造りの民家の大屋根の葺き替えに(「結」という助け合いの組織によって)地元の人たちが大勢参加する様子がテレビ番組で紹介されたりします。
今回は新島(伊豆七島)の民家です。新島では抗火石が採れます。この石が採れるのは日本では新島だけ、世界的にもあとイタリアのシシリー島だけです。軽くて断熱性に優れていますから、この写真のように新島では建築材料として使われています。加工性に優れているので定形材に加工して屋根に用いられています。おそらくブロック状に加工して壁材としても使われているでしょう。遮音性にも優れています。このような優れた建築材料が入手できる新島の人たちはラッキーです。
この写真を撮ったのは1980年7月の合宿の時。あの時一緒に出かけた仲間もみんなオジちゃん、オバちゃんになっただろうな・・・。

「新建築」6704(1967年4月号)より
■ 先日行なわれた、塩尻市の「市民交流センター」の公開審査については既に書いた。一次審査を通過した5案の内、2案がいわゆる「分散コアシステム」を採用していた。構造システムとしてだけでなく、空間的にもコアに重要な意味を持たせていたところが、両案に共通していた。
因みに当選案は「分散壁柱システム」とでも呼称されようか。
この分散コアシステム、「せんだいメディアテーク」をすぐに想起するが、私の記憶はさらに「山梨文化会館 /丹下健三+都市建築設計研究所」に繋がっている。甲府駅に隣接するこの建築は手元の古い「新建築」によると1966年11月に竣工している。いまから40年!も前のプロジェクトだ。
雑誌からこの「山梨」の計画に関する解説文を引用する。
**ここでわれわれが採用したのは、(中略)分散コアともよばれるシステムである。全体のブロック配置、スパン割りなどから15.290m×17.375mのグリッドが設定され、各格子の接点に、直径約5mの円筒コアを配置している。このコアは3本の階段シャフト、2本のエレベーターシャフト、2本の荷物用エレベーターシャフト、3本の便所、給排水シャフト、6本の空調機械室、設備配管シャフト、計16本のシャフトよりなっている。(中略)構造的にも、各スペースのフレキシビリティの要求からきた17mのスパン架構を支える中核体としてきわめて有効に働いている。**
構造シャフトの内部をこのように使うという発想は「せんだい」でも同じだ。
以下『せんだいメディアテーク コンセプトブック』NTT出版からの引用。
**このチューブは床を支える役目、つまり柱として働いているだけではなく、さまざまな役割を果たしています。(中略)エレベーターや階段はなかに収められ、人がこのなかに入ることができます。また、空調や電気、ネットワークの配管を収め、火災時には排煙の経路にもなります。チューブは全体を支えると同時に、さまざまなエネルギーや情報を建物全体に供給する樹の幹のような役割を果たしているのです。**
実によく似ている。説明文を入れ替えても分からないくらいだ。既に40年も前のプロジェクトでコアシステムを採用した計画がなされていたのだ。雑誌には構造に関する説明も載っているが図表は全て手書きだ。
この分散コアシステムのアイディアは磯崎さんによるものだと、むかし聞いたことがあるような気がするが、磯崎さんは1961年に大学院を修了し、1963年には既にアトリエを設立しているから、このプロジェクトに関わったのかどうかは分からない。
「せんだい」のコンペの審査委員長は磯崎さんだった。自分の昔のアイディアを思い出した?
まさかね。
学生の頃、この「山梨文化会館」を見学に行った。受付で渡された黄色い腕章をつけて内部を見て回ったものだ。このプロジェクトが掲載されている「新建築」はずっと後年(雑誌の発行年、1967年には生まれてはいたがまだ小さかった!?)、南洋堂(東京神田の建築書専門店)で買い求めたもの、手元にある建築関係の一番古い雑誌だ。
「せんだい」はすごい建築だと思う。
「山梨文化会館」も当時の建築デザインの状況を考えるとすごい!と思う。そして美しいと思う。「山梨」の美しさをどう説明したらいいだろう・・・。

文春文庫の今月の新刊広告に南木佳士の名前を見つけた。
南木さんの本はとにかく読む。
うつという心の病を抱えながら静かに暮らしている著者が、休日の早朝、暗いうちから起き出して、書き溜めたというエッセイが収録されている。一冊にまとまる分量になるまでに三年かかったそうだ。
**メランコリーを好む性格だから、創りあげた秩序のなかに安住しているのがいちばん薬だとは分かっていても、出来事は上から、うしろから、そして内側からも勝手に起こってくる。** 文庫版あとがきに著者はこう書いているが、私の場合もまったくその通り。
**私はよい医者にはなれないまま終わりそうだ。**と、エッセイの一文が帯に採られているが、私には南木さんは名医、彼の「薬」は欠かせない。


○ 朝日新書創刊の広告 今朝の朝日新聞 (061013)
写真の通り、見開き2ページのカラー広告。自社の新書創刊の広告だから別にいいけれど・・・。
右の写真の下に「001」と番号が付いているのが分かる。これは刊行順に付けられる通し番号だ。今回12冊刊行された。従って「001」から「012」までの番号がついたことになる。
ところで、『愛国の作法』につけられた番号は「001」であって、「1」ではない。「001」としたことに意味があるのだろうか。この新書の総体というか総数を意識したナンバリングのシステムなんだろうか。そうだとすると3桁、999まではOKだが刊行点数が1000になった時にこのナンバリングシステムだと変更しなくてはならない。おそらくその先は1000、1001、1002という具合になるのであろう。ならば今回001ではなくて1から始めた方がよかったのではないか。
他の新書はどうだろう。ちょっと先輩の新潮新書も「001」から始まっている。文春文庫も然り。1年で100冊刊行されるとするとこの番号づけのシステムはたった10年しかもたない。
「0001」から始めると100年もつ。そうしている新書はないものかと探した。あった。講談社現代新書がそうだ。「0001」から始めている。ただしカバーデザインの変更後のことであって、以前は「1」から始めていた。
中公新書も同じつけかたになっている。手元の中公新書を見ると例えば『整理学』加藤秀俊には「13」という番号がついている。既述の理由で「013」とつけるよりはよいだろう。集英社新書は4桁の通し番号とA、B、Cなどのアルファベットの組み合わせのナンバリングがなされていて、分類や登録などについてシステマティックな考え方がされていることが分かる。
今回朝日新書が採用したナンバリングは、このような発想が無く、ただ前例に倣っただけなのかもしれない。別に番号のつけ方なんてどうでもいいけど。

月刊「カーサ ブルータス」特別号 06年9月号
■ 記憶の片隅にあってずっと気になっていた、どこの庭だったかなと。
書店で立ち読みした雑誌に偶然この庭を見つけたときはビックリした。記憶とぴったり符合した瞬間だった。急流を下る舟を見たとき、あ、これだ!と思った。この写真には写っていないが、左側には滝に見立てた石組みもあって、その部分も記憶に合致した。そうか大仙院の庭なのか、この石は舟石というのか・・・。
龍安寺の石庭は何回か見ているが、抽象的で多様な解釈が可能なところが魅力だろう。あるいはそれは解釈不能ということかもしれないが。それに対して黒い石で構成されたこの庭は立体的な水墨画のようだ。自然をぎゅっと凝縮している。龍安寺の庭の対極にあるこの具象的な庭もまた魅力的だ。
さて、私の記憶の中に長い間留まっていた庭が、大徳寺の塔頭(たっちゅう)、大仙院の庭だということは分かったが、では一体いつ私の記憶にインプットされたのか・・・。
こちらはまだ分からない。中学の社会科の教科書? 修学旅行? その後の旅行? できたら確認したい。まずは今年の1月に一緒に京都に出かけた昔の仲間に訊いてみよう。
『空港にて』村上龍/文春文庫 カバーの空港は羽田の第二旅客ターミナルですよ、って教えてくれたSさん、ありがとう。

『ハヅキさんのこと』川上弘美/講談社
川上さんはこの本のあとがきにこう書いている。
**ちかごろ、原稿用紙にして十枚前後の、短篇、というには少々短い長さの小説をしばしば書くようになった、(後略)**
この本にはそのような小編が何編か納められている。
写真では帯の文字が読みにくい。
**
この人は、きっと少し前に
本気の恋をしたんだろうな。
なんとなく思った。
そしてそれはもう、終ったんだろうな、とも。**
この文章は、収録作品「森」の一節だが、私にはこの作品が印象的だった。
同い年の幼なじみのふたりが二十五年ぶりに偶然故郷で再会して、小さい頃遊んだ森に行く。
「わたし、○ちゃんのこと、好きだったんだよ」
よくある告白だ。
「もうちょっと若かったら、○ちゃんと深みにはまってもよかったのにね」 ふたりの年齢は五十。
「ほんとにここは、森だったんだね」
「また、来られるかな」
「きっと、いつかね」
○ちゃんは、わたしと同じ名前、漢字が違うけれど。
たった9頁の小説、なんだかくすぐったいような気分で読了。
川上弘美の作品の雰囲気が少しずつ変わってきているような気がする。
以前のような、「ふわふわ」感が薄らいで、ここに収録されている作品はどれもきちんと輪郭がある、とでも表現すればよいのかな。
村上龍の『空港にて』文春文庫も同時に読んでいたから、二つの作品の異なる印象がミックスされてしまったのかもしれない・・・。
ついでに『空港にて』はなかなかの短編が揃っていた。
特に「クリスマス」は、この作家のいつものストーリー展開とはちょっと違っていて印象的な作品だった。こちらについてはまたいつか。
昨日の原稿を加筆修正しました。改めてお読み下さい。


■ 塩尻の「市民交流センター」の2次審査が昨日(10/07)の午後1時から公開で行なわれた。各案のプレゼンテーションと質疑応答がまず行なわれ、その後提案者全員と審査員全員との間で質疑応答が繰り返された。予定時間の5時頃をかなり過ぎて、審査員の計3回の投票によってこの②案に決まった。審査が公開で行なわれることは最近ではめずらしいことではないが(審査の透明性を高めるということで最近行なわれるようになった)、長野県内の大きなプロジェクトでは始めての試みだった。
前稿に一次審査を通過した5案の模型写真を載せた。⑤案以外の4つの案は印象がよく似ていることが分かる。審査員による1回目の投票で②案と④案が同数で選出された。
①案には新しい構造的なシステムの提案が無く一般的なラーメン構造で解いたところが評価されなかった。建築の中に大通りを造ってその両側が図書館になっている。通りと図書館との間に視覚的な交流を生むという提案が他の案にないオリジナルな提案だった。
②案は構造的には壁柱をランダムに建てている。壁柱のシステムそのものは別に新しい提案でもない。ただそれが鋼板とコンクリートとの組み合わせによる厚さ18cmのPC(プレキャスト)版で可能だという。審査員の山本理顕さんや高橋晶子さんはこの壁柱によって規定される空間を魅力的と考えたようだ。また4つの雰囲気の異なる空間を創出してそこに相応しいジャンルの本をセットするという提案、仕事場をこの建築内に持つインキュベーションリーダーを点在させるという、ソフトな領域にまで提案を広げていた。ただ図書館の専門家の審査員からすれば、どうやらこの建築的な提案が??ということらしい。なるべく大きな無柱空間のワンフロアでないと図書館としての機能が充分発揮されないということなのだ。そういった観点からすれば、壁柱が邪魔ということになる。
このように建築家は建築的システムの提案に注目し、図書館の専門家はその機能性を重視した結果、表が割れた。山本さんは自身のプロジェクトでも新しい構造システムの提案をしているから、その観点からも作品を評価したと思う。
④案は7つのコアに各階のスラブを受けさせて構造的に成立させたもの。③もこの構造システムを採っていた。この2つの案は比較的大きな無柱空間が可能だが、これは「せんだいメディアテーク」で既に具現化されている。6人の審査員のうち、少なくとも山本さんと高橋さんは当然そのことには気が付いている。③案や④案が採用されれば「せんだい」が既にあることから塩尻の独自性という点で希薄になるな、と私は思った。おそらく山本さんと高橋さんが③案や④案を推さなかったのもその点に尽きるのではないか。そういう意味からすると、②案で建築システムとしてのオリジナリティが確保されたといったところだろうか。
③番の模型の印象は「せんだい」のチューブと呼ばれている鋼管の籠状の「柱」が以前ここで紹介した「銀座ミキモト」のボックスに置き換えられたものという印象だった。そのように捉えるかどうかは人によって異なるだろう、私はそう読み取った。そのことがやや独創性に欠けているのではないかと感じさせたのかもしれない。ただ妹島さんばりのコンセプチュアルな空間は魅力的だった。実際に体験してみたい提案だった。
⑤番だけ他の4案と異なった提案だったが、始めに浮かんだであろう空間の抽象的なモデルにリアリティを持たせることの詰めが少し足りなかった、ということなのかもしれない。あと1階のかなりのスペースを広場として解放するために図書館が地下になっていたことも気になった。あの場所に大きな広場を造るとしたら外に閉じるという判断は妥当だと思った。木漏れ日の空間で読書する心地よさにこだわっていたがそのことはよく分かる。また構造担当の川口衛氏(法政大教授、たぶんそうだと思う)のYポストという構造システムの提案は樹を連想させ、コンセプトと合致していて興味深かった。あんなにスレンダーな構造が可能だとしたら、なんとも魅力的ではないか。
結果的には、図書館単一ではなくて、市民交流施設との機能的な関係についてどう解くかが今回のポイントになったということだろうか、当然ではあるけれど。
今回のプログラムに対して建築の有効性を信じて熱心に取り組んだ全ての提案者に拍手を送る。
これからこの提案を基に議論を繰り返しながら、市民のいろんなニーズとのすり合せに入る事になるだろう。できればその過程も今回の審査のように「透明」に情報提供して欲しいと思う。ウェブサイトという最適の手段を利用して。
審査会場で偶然東京の友人と再会した。どうやらこのブログをみて私と会場で会えると考えたらしい。Sさん、こんどは日帰りではなくゆっくり遊びに来て下さい。
■ 昨日行なわれた「市民交流センター」について一次審査を通過した5案のうち4案の印象がよく似ていたことは既に書いた。ネットでちょっと探偵してみた。建築設計事務所を主宰している方々ならば検索すればヒットするはずだ。
敢えて名前は記さない。そうか、伊東さんの事務所に在籍していた人が2人、別の1人はあの金沢21世紀美術館の初期からの担当者だった。質疑応答で自分の言葉で説明をした時、できる人という印象を抱いたがそういう経歴の持ち主だったんだ。この美術館の設計者の妹島さんは伊東さんの事務所の出身。検索して分かった3人には伊東DNAが組み込まれていたんだ。
なんだ、兄弟の戦いだったってわけか。「せんだい」に似ているわけだよな・・・。 審査員との質疑応答のなかでちらっと妹島さんのようなプレゼンだねって言われた人は本当に妹島さんの事務所の出身者だったってことだ。そうか、この人の案は「金沢」の地と図の反転プランと「せんだい」の断面で出来ているんだ!

金沢(左)の四角い展示室(図)が塩尻(右)では四角いボイド(地)に反転している。この人は「金沢」を初期から担当していたということだから、両者のアイディアが似ていることは全く不思議ではない。
当選案の壁柱の構造的なアイディアは「銀座ミキモト」と似ているかなと思ったけれど全く関係ないということではなさそうだ。ミキモトは2枚の鋼板の間にコンクリートを充填するというアイディア、こちらは鋼板型枠の打ち込みパネル、考え方も違うか・・・。
実に簡潔で明快な説明で分かりやすいプレゼンテーションだった、素直に拍手を送る。
改めて「せんだいメディアテーク」の設計者、伊東さんの凄さを認識した。現在のある意味では最先端を行く伊東さんの建築を引き継ぐ担当者達を間近で見たということなんだ。
今回のプログラムに対して建築の有効性を信じて熱心に取り組んだ全ての応募者に拍手!














