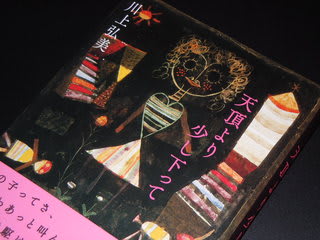
『天頂より少し下って』川上弘美/小学館
**奇妙な味とユーモア、そしてやわらかな幸福感 川上マジックが冴えわたる、極上の恋愛小説7篇。**(帯より)
くっきり、はっきりなカバー装画はパウル・クレーの「人形劇場」。川上弘美の小説に相応しいのかどうか、でもきれいですね。
さっそく読みはじめます。
読み終えたら加筆します。

『日本の建築遺産12選 語りなおし日本建築史』 磯崎新/新潮社 とんぼの本
「磯崎流日本建築史」を読む。
日本の建築は常に外部から技術を取り入れ、それをオリジナルとは違う形に独自に変形させてきた。磯崎さんはこの変化の過程を「和様化」と捉え、その歴史を語りなおすという試みをしている。
この論考で取り上げられる日本建築を特徴づけるふたつの流れ、「垂直の構築」と「水平の構築」。柱を立てる行為に象徴的な意味があるとする垂直の構築と横の広がりを建築の内部にとりこむ営み、水平の構築。取り上げた12件の建築をこのふたつの概念で対にして読み解いていく。その過程で明らかにされる「和様化」とは・・・。
それを私なりに解釈すると、「くずしの美学」だ。
形式がきっちりして固すぎるヨーロッパや中国のデザインのかたちをくずし、固さを取り払っていく日本の建築。そういえば伽藍配置もシンメトリックな構成が次第にくずされていったのだった(『法隆寺の謎を解く』 武澤秀一/ちくま新書)。それは漢字が楷書から草書へとくずされていき、ひらがなを生んだ文化にも通じる。
しかし、今や「グローバリゼーション」の時代。「和様化」の時代は終わった・・・。これからどうする?

『映画空間 400選』 長島明夫+結城秀勇 編/INAX出版
「映画の建築・都市・場所・風景を読む 映画史115年×空間のタイポロジー」
■ こんな本が出版されたことを知ると直ぐ注文してしまう。一気に通読する、という本ではない。書棚の取り出しやすいところに置いて、ときどきパラパラとページをめくって楽しむ本だ。マニアな雰囲気かつ上品なカバーデザインがいい!
熱心な映画鑑賞者でなくとも400本も紹介されていると、知っている映画、観た映画も取り上げられている。
映画の「空間」、それも「都市空間」が最も印象に残っているのは『第三の男』だ。この映画の舞台というか、都市は大戦直後のウィーン。その大観覧車、その地下水路。モノクロの光と影。この映画では建築よりも建築的に空間の奥深さが表現されていた。
ちなみに「時間」が最も印象に残っている映画はスタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』だ。この映画ほど「時間」、それも「宇宙時間」とでもいったらいいのか、を意識させられた作品は他にない・・・。

166
■ 今月読み続けている漱石の『吾輩は猫である』に次のようなくだりがある。
**ますます神の全知全能を承認するように傾いた事実がある。それはほかでもない、人間もかようにうじゃうじゃいるが同じ顔をしている者は世界じゅうに一人もいない。顔の道具はむろんきまっている、大きさも大概は似たり寄ったりである。(中略)よくもまああれだけの簡単な材料でかくまで異様な顔を思いついたものだと思うと、製造家の伎倆に感服せざるをえない。よほど独創的な想像力がないとこんな変化はできんのである。**(164頁)
火の見櫓の観察を続けていると、同じ想いを抱く。
Tさんに謝謝。

■ 今月は毎日少しずつ『吾輩は猫である』を読んでいる。この小説を読むのはたぶん3回目。
名前のない猫の飼い主、苦紗弥先生は英語教師。モデルは漱石自身。そして猫は漱石を客体化して観察するもうひとりの漱石。ビートたけしを客観視する北野武と同じだ。
猫が台所で今まで一ぺんも口にいれたことがない雑煮を食べたもののかみ切れず、前足を使って餅を払い落そうとあと足二本で立って台所じゅうあちら、こちらと飛んで回るという、まるで赤塚不二夫のニャロメのようなシーンが早々に出てくる。ここで笑った。
読み進むと苦紗弥先生の家に夜中に泥棒が侵入するという「事件」が起きる。泥棒は先生の枕元に大切そうに置いてあった箱と、奥さんの着物や帯を盗んでいく。箱の中身は価値ある書画骨董の類かと思いきや、山芋だった・・・。実際に漱石家には泥棒が入ったそうで、小説同様、奥さんの帯や着物を盗んでいったという。
**先生この猫をわたしにくんなさらんか。こうして置いたっちゃなんの役にも立ちませんばい**と多々良さんに言われて(179頁)、鼠も捕らず、泥棒が来ても知らせようとしない猫はピンチに陥る・・・。
今月中に読了できるかどうか。

『環境デザイン講義』 内藤廣/王国社 読了。

■ 『神様』は川上弘美のデビュー作で、第一回パスカル短篇文学新人賞を受賞した。くまにさそわれて(小説では「くま」も「さそわれて」もひらがな表記)川原へ散歩に出かけるというごく短い物語だが、この作品に福島第1原発のトラブルの後、手を加えたのが『神様2011』で、雑誌「群像」に掲載されている。今日(19日)えんぱーくで読んだ。
**「いい散歩でした」
くまは305号室の前で、袋から鍵を取り出しながら言った。**
**「いい散歩でした」
くまは305号室の前で、袋からガイガーカウンターを取り出しながら言った。**
『神様』ではくまが袋から取り出すのは鍵だが、『神様2011』ではガイガーカウンターになっていた。帰宅すると外部被曝線量と内部被曝線量を計測し、累積外部被曝線量と累積内部被曝線量を計算するのだ。 そう、 花たちが日々の外気温の積算値を「計算し」、それがある値になると咲き出すのと同様に、被曝線量は日々の値ではなく、その「累積値」が問題になることを川上弘美はきちんと書いている。
あとがきには**静かな怒りがあれ以来去りません**とあった。 いち早く福島第1原発のトラブルを小説で取り上げた川上弘美はやはり作家としてスゴイ。

165 夏のフォトアルバム 奈良井宿 110619 早朝
中山道奈良井宿。 木造2階建て平入りの建物が軒を連ねている。緩勾配の切妻屋根、出桁造りで軒が深い。軒下両端のうだつ壁がリズミカルに並ぶ。
それぞれの火の見櫓にはそれぞれの歴史がある。宿場を後方からそっと見守る姿が凛々しい。

■ 文字書き道祖神 諏訪市中洲
前稿に載せた火の見櫓の脚元に立つ道祖神。
道祖神というと安曇野の路傍に立つ双体道祖神がよく知られているだろう。道祖神はもともと塞の神。邪悪なものをさえぎるとされ、江戸後期から盛んに立てられるようになった。やがて五穀豊穣、安産などを祈願する神として庶民の生活に浸透していき、それは連綿と今日まで続いている。花が飾られている道祖神や注連縄をかけた道祖神をときどき見かける。
文字書き道祖神の数も多い。総じて文字は豪胆にして達筆だ。

164
■ 所用で諏訪へ出かけた。初めてのところではないが、案内図を送ってもらった。案内図には火の見櫓が載っていた。それがこの火の見櫓。辻に立つ火の見櫓の脚元には道祖神があった。
先日載せた火の見櫓のチェックポイント(改訂版)で観察すればいいのだが、それはまたの機会に・・・。
■ 建築家にしてエッセイストでもあったバーナード・ルドフスキーの『建築家なしの建築』。この本は1984年に鹿島出版会のSD選書として刊行されたものが一般によく知られているが、1975年に「都市住宅」別冊として出版されている(写真)。

■ 今日(13日)、この煙突を松本市内で見ていてふとこの本のことを思い出した。
訳者・渡辺武信氏はあとがきに**本書は世界各地の無名の工匠による風土的な建築をパノラマ的に紹介したもので(後略)**と書いている。そう、日本も含め、世界各地の「風土的、無名の、自然発生的、土着的、田園的」建築を紹介している。
海岸の小石が繰り返し繰り返し波に洗われて次第に形が丸く整っていくように、建築家なしの建築は建築家に替わって風土が、永い時の流れが、建築に合理的な形を与えたと言っていいだろう。茅葺きの民家もその好例のひとつだ。
**風土的な建築は流行の変化に関りがない。それは完全に目的にかなっているのでほとんど不変であり、まったく改善の余地がないのである。(12頁)**とルドフスキーは本書に書いている。
現代建築の大胆な造形を見るにつけ、その依拠するものは一体なんだろう・・・、と思う。
■ 建築デザイン。その主眼は美しい建築空間の創出から、建築空間を成立させるシステムの提案へと移りつつあるようだ。海外の事情には明るくないが、国内では伊東豊雄の「せんだいメディアテーク」がそのはしりだったかもしれない。独創的な空間構成システムをいかに提案するか・・・。「せんだい」では、チューブと呼ばれる籠状に組まれた鋼管トラスとプレートと呼ばれるフラットスラブによる空間の構築システムが提案され、実現している。
森のコート
太陽のコート
■ 塩尻の「えんぱーく」、2006年に行われた設計競技の当選案には「壁柱」と呼ばれる、プレキャストコンクリート(PC)と鋼板の複合版(厚さ約200mm)によって床を支えるというシステムが提案されていた。
約100枚の壁柱が創りだす空間ってどんなものだろう・・・。柱ではなくて壁柱。設計競技の公開審査では壁柱について、図書館というオープンであるべき空間にとってはうっとうしい、できれば無い方がいい存在になるのでは、という指摘もあったように記憶している。
実際に空間体験してみると、壁柱はまったく気にならない。むしろ壁柱がいろんな空間を創りだすのに欠かせない存在になっていることがわかる。来館者はお気に入りの場所を見つけて、そこで読書をしたり、原稿を書いたり、勉強をしたりして過ごしている。
月のコート
今日の午前中、「月のコート」と呼ばれる吹き抜け空間に面する一角で『吾輩は猫である』を読んで過ごした。トップライトから自然光が降り注ぐ明るい空間は細かな活字を追うのによい。数回目のえんぱーく体験。


白:昭和46年2月発行
■ 庄司薫は若い人には馴染みのない作家だと思う。昭和44年(もう随分昔のことだけれど)、『赤頭巾ちゃん気をつけて』で芥川賞を受賞している。作品はその後、薫くん(主人公の名前)シリーズ4部作としてまとまる。
その第3作『白鳥の歌なんか聞えない』はNHKでドラマ化された。このドラマで仁科明子がヒロインの由美(薫くんのガールフレンド)役でデビューしている。このときの経緯を彼女は『いのち煌めいて』小学館に次のように書いている。
**高校三年の夏。この夏、私は、ある雑誌のグラビアに、父といっしょに出た。それが、ちょうど庄司薫さん原作の『白鳥の歌なんか聞えない』をドラマ化しようと、出演者を探していたNHKのプロデューサーの目にとまり、姉のマネージャーに出演を打診してきたのだ。話が決まったのは、もう二学期の終わりころだった。(16頁)**
調べてみるとこのドラマが放送されたのは昭和47(1972)年3月のことだった。ストーリーは忘れたが彼女がすごくかわいかったことだけは今でも覚えている。そう、当時高校生だった彼女はぼくの好みにぴったりだったのだ。
ぼくはドラマ化されたのは『赤頭巾ちゃん気をつけて』だったとずっと思っていて、昨日(11日)カフェ・バロでそのことを話したのだが、違っていた。なぜこの小説のことを話題にしたかは書かないでおく。
**女の子にもマケズ、ゲバルトにもマケズ、男の子いかに生くべきか。さまよえる現代の若者を爽やかに描く新しい文学の登場!**「赤頭巾ちゃん気をつけて」の帯。
**早春の陽ざしに音もなく忍びよる死の影。生命あることの寂しさ空しさを見すえて互いに求めつつさすらう若い魂を、光と影の交錯の中に美しく描く永遠の青春像**「白鳥の歌なんか聞えない」の帯。
ぼくの青春時代とシンクロしている小説で、書棚から取り出してながめているととても懐かしい想いがする。一冊だけ再読するなら、やはり『白鳥の歌なんか聞えない』かな・・・。
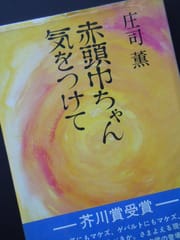


薫くんシリーズ
赤:昭和44年8月発行 黒:昭和44年11月発行 青:昭和52年7月発行


■ 建築家のミース、ミース・ファン・デル・ローエはル・コルビュジエとフランク・ロイド・ライトと共に近代建築の三大巨匠と呼ばれている。ミースは鉄とガラスという近代建築を代表する材料を用いて抽象的な「白」の建築を創りつづけた。代表作としてまず浮かぶのはやはりファンズワース邸だ。
カフェバロの外観の印象について、ミースの建築のようだとKさんだったか、設計者のMさんに対してだったか忘れてしまったが語ったことがある。
既に書いたが、先日塩尻のえんぱーくで藤森照信さんの本を読んでいて「木造ミース」という言葉に出会った。どのような文脈で使われていたのかは、覚えていないが、そのときカフェバロの外観デザインのことを思った。そうか・・・、木造ミース! こんな言葉があの時浮かんでいたらな~、と残念に思った。
どうだろう、この外観。木造ミースという言葉がぴったりのデザインだと思うのだが・・・。

162 東筑摩郡筑北村本城の火の見櫓

163 松本市四賀の火の見櫓
■ 火の見櫓観察のポイントを整理しておこう(100813の記事の改訂版)。
1 火の見櫓の立地、環境
10 周辺の状況・環境、観察時の季節や天候、時間など
11 消防団詰所(屯所)、消防倉庫の有無
12 観察者の主観的な印象
2 火の見櫓の全体の様子
20 形式:1本柱、梯子型(2本柱)、櫓型(3本柱、4本柱 その他の型)
21 櫓の高さ、脚の長さ、脚間長さ
22 プロポーション:上方への絞り方(櫓が描く曲線の様子) 総高/脚間長さ、逓減率
23 屋根と見張り台の形、大きさ及びバランス
24 色 その他
3 火の見櫓を構成する各部の様子
30 屋根の有無 屋根の形(平面形と立体形)と飾り(避雷針及びその飾り、蕨手、その他)
31 半鐘の有無 半鐘の形 半鐘用の小屋根の有無 形
32 見張り台の有無 見張り台の平面形、床の構成、手すりのデザイン
33 櫓の材料(鋼材、木材、石、コンクリート)
34 櫓の平面形と立体形、構成部材の種類と接合方法(鋼材:ボルト、リベット、溶接)、ブレース(筋かい)
35 梯子の構成部材 手すりの有無など
36 脚部のデザイン 単脚、複合脚(トラスの組み方やアーチの有無 カーブの様子)
37 基礎:独立基礎、一体型(塊状)基礎
38 消防信号表示板の有無 銘版の有無と記載内容(製造所名、製造年など)
39 スピーカー、サイレン、照明等の有無 経年変化の状況 その他
4 その他















