 金沢の山ちゃんからのフォト便り<奥山中温泉>
金沢の山ちゃんからのフォト便り<奥山中温泉> ・・・奥がつく山中温泉があるなんて知らなかった・・・

<奥山中の温泉野天風呂>
石川県の福井県境に近い山の中に温泉宿がある。
近くに樹齢二千三百年の大杉を祀った神社がある
険しい渓谷は歩いて行く道がなく、眺めるだけである。
昔の人もせせらぎの音を聞きながら、静かにゆっくりと湯治に訪れたこと偲ばれます。
(加賀市 奥山中温泉にて)
野天風呂への階段

野天風呂湯畑

野天風呂の湯治客

野天風呂の灯り

 金沢の山ちゃんからのフォト便り<奥山中温泉>
金沢の山ちゃんからのフォト便り<奥山中温泉> 




 金沢の山ちゃんからフォト便り<山中温泉>が届いた。
金沢の山ちゃんからフォト便り<山中温泉>が届いた。



 久しぶりで金沢の山ちゃんから金沢のフォト便りをいただいた。
久しぶりで金沢の山ちゃんから金沢のフォト便りをいただいた。






 もいいですよ。
もいいですよ。 金沢の山ちゃんから暑中見舞いをいただいた。
金沢の山ちゃんから暑中見舞いをいただいた。
 これがブドウ? 一見すももかと思った。
これがブドウ? 一見すももかと思った。


 ・・・インターネットの紹介では・・・
・・・インターネットの紹介では・・・ 味もいいそうですが、大きさを実感するためぼくもインターネットで調べてみました。
味もいいそうですが、大きさを実感するためぼくもインターネットで調べてみました。 巨峰、デラウエアと比較してみてください。
巨峰、デラウエアと比較してみてください。

 友人から毎月送られてくる地方月刊誌<アクタス>に興味深い記事があったのでご紹介しよう。
友人から毎月送られてくる地方月刊誌<アクタス>に興味深い記事があったのでご紹介しよう。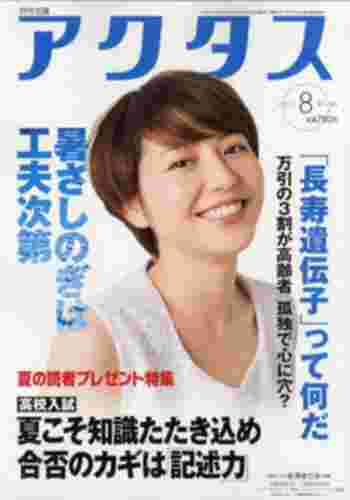
 6月、NHKスペシャル<あなたの寿命は延ばせる>でも取り上げられたようだが、長寿遺伝子(サーチュイン)は2000年に米・マサチューセッツ工科大学のレオナルド・ガランチ教授によって酵母の中から発見された。地球上のほとんどの動物が持っており、この遺伝子の働きを強めることで寿命が20~30%延びることが確認された。
6月、NHKスペシャル<あなたの寿命は延ばせる>でも取り上げられたようだが、長寿遺伝子(サーチュイン)は2000年に米・マサチューセッツ工科大学のレオナルド・ガランチ教授によって酵母の中から発見された。地球上のほとんどの動物が持っており、この遺伝子の働きを強めることで寿命が20~30%延びることが確認された。
 この遺伝子は万人が持っているが普段は働かない。
この遺伝子は万人が持っているが普段は働かない。
 古家教授のグループは今年1月、人もカロリー制限を続けると長寿遺伝子が活発化することを裏付け、人体でサーチュイン酵素量の増加を確かめた世界初の研究成果となった。
古家教授のグループは今年1月、人もカロリー制限を続けると長寿遺伝子が活発化することを裏付け、人体でサーチュイン酵素量の増加を確かめた世界初の研究成果となった。 長寿遺伝子はたとえ数年間カロリー制限を続けても、1回でもカロリーをオーバーするとたちまち休止するとの研究報告もある。かなり意思が強い人でないと、なかなか続けられない側面があるようだ。
長寿遺伝子はたとえ数年間カロリー制限を続けても、1回でもカロリーをオーバーするとたちまち休止するとの研究報告もある。かなり意思が強い人でないと、なかなか続けられない側面があるようだ。 金大大学院の鈴木特任教授によると、赤ブドウの皮などに含まれる<レスベラトール>は、ポリフェノールの一種で、代謝を高めて脂肪を燃焼させるほか、インスリンの働きや血糖値を正常にし、糖尿病、動脈硬化を改善する効果が確認されている。
金大大学院の鈴木特任教授によると、赤ブドウの皮などに含まれる<レスベラトール>は、ポリフェノールの一種で、代謝を高めて脂肪を燃焼させるほか、インスリンの働きや血糖値を正常にし、糖尿病、動脈硬化を改善する効果が確認されている。
 <金沢の山ちゃん>から<山代温泉>のフォト便りがありました。
<金沢の山ちゃん>から<山代温泉>のフォト便りがありました。
 <服部神社の境内>
<服部神社の境内>

 山代の古総湯は昨年の10月3日に開業したそうだ。浴室の窓にはステンドグラス、壁や床には当時使用されていた九谷焼のタイル、建物は総ヒノキ造りという和洋折衷の構造になってる。
山代の古総湯は昨年の10月3日に開業したそうだ。浴室の窓にはステンドグラス、壁や床には当時使用されていた九谷焼のタイル、建物は総ヒノキ造りという和洋折衷の構造になってる。
 古来親しまれた<加賀温泉郷>もこのところの観光客低迷で、各地でこういった<総湯>の建築が相次いでいるという。北陸新幹線の開業を控え、各温泉郷の思惑が交錯する。
古来親しまれた<加賀温泉郷>もこのところの観光客低迷で、各地でこういった<総湯>の建築が相次いでいるという。北陸新幹線の開業を控え、各温泉郷の思惑が交錯する。









 、中学の近くには<尾山神社>
、中学の近くには<尾山神社> の観光スポットが隣接する。
の観光スポットが隣接する。


















