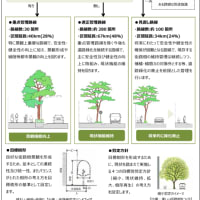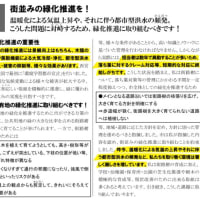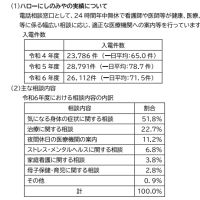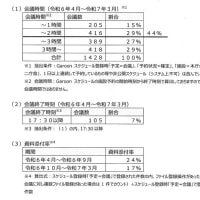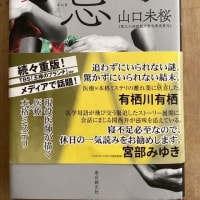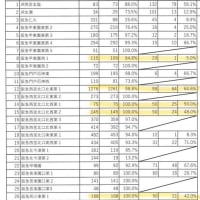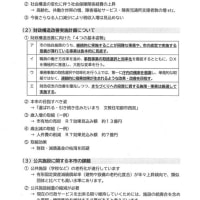今日は、フレンテ問題特別委員会。
わたしゃ、傍聴に行っただけですが、なかなか長かった。
報告したいことも色々ありますが、今の段階では、とてものこと、
まとめて、よう書かんので、その報告は、また別途。
というわけで、今日は、昨日の日記の続きです。
昨日の日記では、
○特養の施設数が現状、圧倒的に不足している
○施設だけでなく、介護従事者も、将来、大幅に不足する可能性が高い
の二点を、大きな問題としてあげたうえで、
現状の対応が続くのであれば、
今後も、施設不足の状態が続くor更に悪化する可能性が高い
ことを書きました。
で、今日は、その続きの介護従事者の不足の話をば。
少し古い数字ですが、平成17年10月時点で、介護保険サービスに
従事する介護職員数は、約110万人。
ところが厚生労働省の試算によりますと、平成26年度までに
約40万~約60万人の介護従事者が、新たに必要になるそうです。
【参考: http://www.mhlw.go.jp/seisaku/09.html 】
比率にして、既に働いている介護従事者全体の約半分、
絶対数にして数十万人単位の介護従事者が、
新たに必要になるというのは、尋常な事態ではありません。
実際、介護施設をつくったはいいが、従事者が集まらないという事態が
多数発生しており、「介護難民」という言葉も、多く、聞かれます。
こうした事態を踏まえて、国は、
○離職者に対する資格取得の補助
○資格取得者を雇用した事業所への一時金支給
等の対策をとっています。
しかしながら、こうした対応は、根本的な問題解決の手段にはなりません。
介護従事者には
○他の産業と比較して離職率が高い
○介護福祉士国家資格取得者約47万人のうち、
実際に福祉・介護分野で従事している方々は約27万人に留まっており
残りの約20万人はいわゆる「潜在介護福祉士」となっている
という特性(?)があります。
せっかく就職しても、その職を辞する人が多いということは、
いろいろな意味で、介護職が、職業としての魅力がないということを
示唆しているように感じます。
国家資格取得者47万人のうち、約20万人が資格を持ってはいるが、
その職に従事していないという事実は、
こうした憶測を客観的に証明していると言えるでしょう。
大切なのは、介護を長期的に支える人材作りであり、
そうした方々の働く意欲を高める具体的施策だと思うのです。
介護従事者が長期的に働きやすい環境を整え、
介護職を多くの方にとって、魅力的な職種とすること。
これこそが介護従事者の不足を解消するために、
最も重要なことであるはずです。
一方で、各種マスメディア等で、
「介護職の給料では結婚できない。。。」
といった趣旨の声が多数報道されるなど
介護従事者の所得水準の低さは、よく知られているところです。
私は、この問題を解消するために、真っ先に取り組むべきは、
介護従事者の所得水準をあげることだと考えています。
こうした声に対する国レベルでの対応は、先述の通り、基本的に
○離職者に対する資格取得の補助
○資格取得者を雇用した事業所への一時金支給
に留まっています。
(今春実施された、いわゆる3%の見直しは除く。)
繰り返しになりますが。
資格取得者に対する一時的な補助に留まるのであれば、
○離職者の多さ
○潜在的な資格保持者の多さ
に顕著に現れている介護従事者の劣悪な労働環境を
改善することはできません。
これでは介護従事者の不足を解消することなどできません。
今、我々の前には、雇用の不安定・低所得化・景気の悪化といった
非常に深刻な問題が存在します。
(とりわけ景気の悪化について、私は、所得の減少・雇用の不安定さ等に
起因する消費意欲の減退という要素が非常に大きい、と考えています。)
介護職の雇用拡大・所得水準の向上は、こうした問題に対抗し得る
可能性を持つ、非常に有望なカードだと、私は考えています。
一部自治体では、介護職不足を解消するための補助金の支給等、
独自の取り組みを国の施策に上乗せして実施しています。
私は、本市においても同様に、介護従事者不足の解消に直結する
施策を実施するべきだと考えています
繰り返しになりますが、それこそが、
介護従事者の大幅な不足・深刻な雇用問題・消費意欲の減退等の
重要な問題に対抗しうる有望なカードだと考えているからです。
一議員の力で、どこまでのことができるかは分かりませんが。
こうした施策の実現に向け、取り組んでまいります。