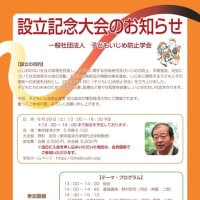お盆休みとはいえ家庭内でいろんな用事が入っていたため、更新が1週間ほど途切れてしまいました。また、今朝からこのブログの更新をしようと思ってパソコンに向かっていたら、今度は急に画面が暗くなるというパソコンのトラブル。ようやく復旧したので、さっそく、前回の続きを書きます。
さて、前回とりあげた『双書解放教育の実践』シリーズ(解放教育研究会 福地幸造・中村拡三編、明治図書、全4巻)の第1巻『解放運動と教育』(1970年)の話を続けます。
この本なのですが、目次をずっと見ていけばわかるように、たとえば識字教室(学校)、解放子ども会とその保護者組織の活動、青年のサークル活動、各地区での教育計画づくりの取組みなど、1960年代後半あたりで、解放運動の側から地域の教育運動として取組んできたことをふまえてまとめられています。また、このような内容で構成された第1巻には、次のような編者・中村拡三の思いがこめられています。(以下、文字色が青の部分は、この本からの引用です。)
この巻は、あとに続く三巻の前提となるものであり、解放教育の土台にすえられねばならないものである。解放運動というものが、「教育」というものをどうとらえてきたか、どんな教育を生みだしてきたか、そのことを明らかにしたいと思う。(p.17)
この引用からもわかるとおり、当時の編者らの認識においては、解放運動が地域の教育運動として取組んできた子ども会や保護者組織の活動、青年のサークル活動、識字教室の活動などが、まさに「解放教育の土台」というべきものだったわけです。
また、次の一文は識字教室の位置づけについて述べられたものですが、当時の解放運動において「教育」や「学習」とは、このようなものとして考えられていたことを忘れてはならないでしょう。
字を習い、読み、書ける。生活が便利になる。識字の運動は、ただ、それだけにとどまっては意味をもたない。その文字を通して差別の実態を知り、自分の経験や自分を取り巻く差別の現実を自分の手で書き続ける運動に発展しなければならない。その習得した文字は、差別を告発し、解消させるための有効な手段であるからである。怨念(おんねん)―うらみつらみを綴り、これを通しての現在おかれている姿を変えさせる力にならなければならない。進学のための予備校や塾で勉強するのとは、わけが違う。の子どもたちの、文字を習うという教育もまた同じではないか。(p.60)
もちろん、この文章が綴られた1960年代末と今とでは、差別の現状や解放運動を取り巻く社会情勢はずいぶん、変わっています。
ただ、「進学のために」いわゆる「受験学力」を高めるような学習ではなくて、自らの置かれている現実を批判的に認識し、そのなかで問題となることを的確にとらえ、周囲に訴え、働きかけていく力を身につけていく学習。こういったことを当初、解放運動の側は教育・学習に求めていたことは、あらためて確認しておいてもいいと思います。なぜなら、このことが、先に述べた「解放教育の土台」として当時、考えられていたと思われるからです。
あるいは、当時のある地区での子ども会活動にかかわって、この本には次のような文章もあります。
まずなによりも“生きる”ことを先行さすこと、つまり、教室や家庭のなかでは得られない解放感を、自らの手でつくり出していくことから、活動は始められたのである。(p.78)
不就学や長欠、そしていわゆる非行といわれる事柄についても、子どもたちの集団としての解放感を組織して、はじめてそれらに対する一定の批判力と、解決への行動力が生まれる。解放感をつくりだし、育てていくなかで子どもたちは自らが生んだものについて考え始める。自らの解放をハバむもの、それが自分と自分の周囲にある現実への関心となって現れてくる。(p.78)
この文章から察するに、この地区の子ども会は、たとえば劣悪な住環境や両親の不安定な就労、生活苦、家庭の不和、授業についていけない等の学校生活への不適応など、さまざまな課題に直面し、まさに落ち着いて自分のことを話したり、考えたりできるような「居場所」のない状態の子どもたちに、まずは学校でも家庭でもない「居場所」を創りだすことからはじめられたのでしょう。
子どもたちが学校からも家庭からも解放された場で、教師でも親でもないおとなに支えられて、自らの生い立ちや生活環境のなかで抱え込むことになった諸課題を見つめなおし、それにどう対応するかを考える機会を設けること。また、そのようなことが可能な「居場所」を創出すること。
この「居場所」創出という取組みは、1960年代末だけでなく、いわゆる不登校やひきこもり、非行など、現代日本社会のさまざまな青少年の問題にかかわって、今もなお必要なことでしょう。また、このような「居場所」創出の取組みは、差別の問題だけでなく、ほかの子どもの人権にかかわる諸課題においても必要なことでしょう。私としては、この当時において、編者らが「解放教育の土台」に、子ども会のこうした「自らを解き放つ居場所」という側面を重視したことを評価したいと思います。
そして、この本には、社会教育について、次のような指摘もあります。これは1960年代末のある地区での青年たちの学習会活動にかかわっての指摘です。
青年は夢をもっている。希望もある。反面、不満もある。しかし、これらの、ねがいや不満を語る場がない。その場を設定すること、それ自体が、本来の社会教育ではなかろうか。ところが、その場の設定すらなされていないのが実際の姿ではなかろうか。今の社会教育には、青年をたちあがらせる方向に問題のあることはいうまでもないが、その場さえないというのが現状である。(p.102)
青年・婦人・子どものねがいを聞かずして、社会教育は成り立っていかない。とくに青年の願いに、どこまで耳を傾けるかに、社会教育のすべてがかかっているといってもいいのではなかろうか。(p.102)
「婦人」という言葉に当時の制約のようなものを感じるのであるが、しかし、言おうとすることはよくわかります。大阪市内のもと青少年会館での子ども会や保護者組織の活動、識字教室や青年のサークル活動などを見ていると、「こうした活動を積極的に支援することこそ、社会教育・生涯学習行政の仕事ではないのか?」と私も思いますし、「そこで活動している人々の願いや要望をどうして聞こうとしないのだろう?」と思ってしまいます。今もなお、1960年代末の指摘が通用するのは、なぜなのでしょうか?
このように、前々からこれはこのブログなどで書いてきたことですが、古い解放教育関係の文献を読んでいると、「これって、今の状況にも通じることじゃないの?」と思うような言葉に、何度も出会うことがあります。特に、もと青少年会館で取り組まれている諸活動にかかわっていると、私にしてみると、1960~70年代あたりに書かれた解放教育関係の文献が、比較的最近書かれたそれよりも、何か示唆に富むことが多々あります。今後も引き続き、古い文献を読んでいて気づいたことを、ここに書いていこうと思います。
<script type="text/javascript"></script> <script src="http://j1.ax.xrea.com/l.j?id=100541685" type="text/javascript"></script> <noscript>