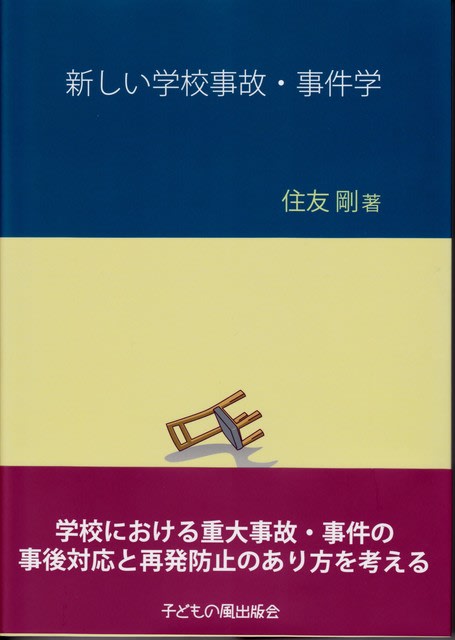まだ出版社のエイデル研究所から掲載号が届かなかったので、今日、梅田の本屋で自分で買ってきたのですが…。
『季刊教育法』の195号、ようやく書店に並びはじめました。
私の連載企画「『ハの字』の両側を見つめる学校事故・事件学」の第2回目も、この195号に掲載されています。
今回の私の原稿は、前号掲載の連載1回目ではほとんど書けなかった拙著『新しい学校事故・事件学』の本題に触れるような、そういう中身になってます。
まあ、ここのところの『季刊教育法』の編集をやっている小野田正利さん(大阪大学)が、「住友さん、『新しい学校事故・事件学』の宣伝を兼ねた連載をやってくれ」とおっしゃるので、ばんばん、その手の原稿を書いているわけですが。
ということで、ぜひ一度、ご一読ください。
それも、できれば拙著『新しい学校事故・事件学』と『季刊教育法』の連載企画、両方あわせて読んでください。そうすると、いろんなことが見えてくるはずです(通販サイトAmazonのリンク先に、私の本の題名部分をクリックすると行けるはずです)。
あと、今号の「教師の不祥事」で敗戦前の事例を扱っている原稿が2本あるんですが…。「これ書くんだったら、『日本近代公教育の支配装置(改訂版)』(岡村達雄編著、社会評論社、2003年)の第2部第3章にも触れてよしいよな~」と、ちょっと不満が残りました。
私が1900~1920年代の教育雑誌や週刊教育新聞の記事、あるいは当時の判例などをてがかりに、その頃の教員の不祥事と処分の問題を論じたのが、この『日本近代公教育の支配装置(改訂版)』の第2部第3章なんですけどねぇ…。
「この話なら、もう15年前に私らも書いてるよ~」と、そこだけツッコミいれておきたくなりました。
あ、そうそう。
『新しい学校事故・事件学』の第1章で、私が『日本近代公教育の支配装置(改訂版)』を書くに至るまでの近代日本の教員処分史研究にかかわったことについても触れています。そういう経験の蓄積の上での私と学校事故・事件とのかかわり、そして『新しい学校事故・事件学』という本の執筆なんですよねえ…。