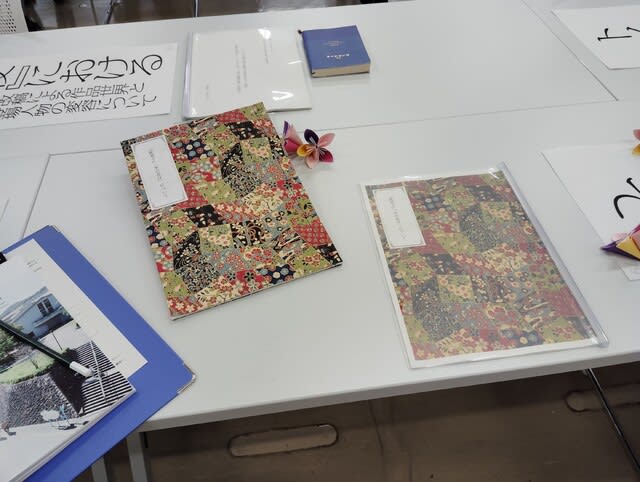今日は2月27日(木)。会議があるので大学に出勤しています。気づけば2月末、あと3週間ほどで卒業式です。
まあ、そんな時期ですので…。いつも研究室に出入りしている4年生教職組の学生有志と、2月24日(月)・25日(火)の1泊2日、広島・宮島に「卒業旅行」に出かけてきました。
ちなみに、なぜ「広島・宮島」なのか、ですが。学生たちのなかに「あ~広島でおいしいカキ(牡蠣)食べたい」という学生が居たもので…。で、「1日目の夜にカキ料理を食べたあと、翌日は船で宮島まで往復したらいいかな~?」と提案したら、「それがいい!」と話がまとまりました。
なお、2日目ですが、原爆ドーム近くの元安桟橋から宮島行の観光船に乗って往復したのですが、学生たちが「帰りに資料館見たい。ここまで来て、見なかったら後悔する。行ったら気持ちが落ち込むけど、でも、見ないわけにはいかない」と言い始めたので、帰りの船のなかで予定変更。急遽、閉まる間際の広島平和祈念資料館に入って、常設展だけ見てきました。
そんなわけで、今日の画像は1日目の広島と、2日目の宮島、そして帰る間際の広島平和祈念公園周辺の様子です。
<1日目> お好み焼きだけ、新幹線広島駅で私が食べたものです。残り2枚は1日目の夜、学生たちと食べたものですね。



<2日目の宮島> 宿泊先から原爆ドームの方を撮りますと、元安桟橋が映ってました。それが1枚目で、2枚目は宮島の厳島神社、3枚目は宮島で食べたミニの穴子めしと穴子卵とじうどんです。



<2日目の広島平和祈念公園付近> こちらは平和祈念公園の窓から撮ったものが1枚目、2枚目は帰り道に撮った原爆ドームと宮島行の観光船です。