先日、私の勤める病院の近隣医療関係者向けに表題にある講演会を開催し、その「開会にあたっての提言」として短い発表をしました。意外と好評だったので内容はいままでブログで述べて来たことを短くまとめたものに過ぎなかったのですが、備忘録として記しておきます。
本日はご多用な中、本講演会にご参加いただきありがとうございます。本日の2題の講演「死と向き合う臨床・病院医療からホスピスまで」「がんにおける精神疾患とその対応」をご専門の先生にしていただく「つかみ」として、「がん医療におけるこころの問題」を考える上で参考になると思われる事項を紹介させていただきます。

これは以前当施設でもご講演いただいた、死やホスピス医療について勢力的に活動しておられるジャーナリストの米沢 慧氏が提言される「往きの医療、還りの医療」という概念です。日本においてもつい数十年前までは、左図のように日本人の平均寿命は60歳を超えておらず、人生50年という考え方に従って医療を行っていれば良かったのです。つまり全ての医療は「病気を完治させて患者を今までの日常生活ができるよう復帰させること」を目標におこなっていれば良かったのです。しかし、還暦を迎えて20年以上の人生を送ることが当たり前になっている現在、医療の目標を「病気の完治」のみに置くことで本当に良いのかが、問われていると思います。つまり同じ癌であっても50歳と80歳の患者さんの治療方針が同じであって良いのか、それでどちらの患者さんにも同じ幸福が得られるのか、という問題です。社会における平均寿命が80歳などという事は人類の歴史が始まって以来、今日初めて達成されたことです。だから現在の人々の健康を扱う我々医療者が人類始まって以来のこの新しい命題について答えを考えて行く義務があるのではないでしょうか。

これは医師の石飛幸三氏の「平穏死のすすめ」という本に紹介されているものですが、死には「三つの態様」があるということです。「突然死」は天災や事故で亡くなる場合や、心筋梗塞や脳卒中などであっという間に亡くなってしまう場合です。これは本人にも家族にも死に対してこころの準備がありません。
二番目の「がん死」これは本日のテーマになります。つまり本人にも周囲の家族にも近くに終末が来る事がわかっている死です。
三番目の「自然死」これを石飛先生は「平穏死」と言っておられますが、ある意味「老衰」と表現しても良いかも知れません。これは人生の終末を迎えながらも終わりが見えない死、ということができ、本日とは別の大きなテーマになりえる題材と言えます。

死と向き合う医療(看取り)を考える上で大事な事は、重症になった末期の状態においては、決まった形の医療を受けなければならないといった思い込みで患者さんの選択肢をなくしてしまわないようにする事です。人は死ぬ瞬間までがその人の人生であって、最期はこのように看取られなければならないといった決まりはないのです。心臓が止まった瞬間に医師や看護師が駆けつけて死亡宣告をしないといけないなどという決まりはありません。眠るように自宅で家族に見守られて亡くなって翌日かかりつけ医の診断書を書いてもらっても良いのです。要は患者さんが自分の望ましい生き方ができるようにサポートすることが医療者の努めであるという認識です。
がん研究所の元所長の北側知行氏は、高齢で、苦痛を伴わず天寿を全うしたように死に導く癌を「天寿癌」と呼んで苦痛を取る治療のみを行い治癒を目指さない医療を行うことを提唱しました。超高齢者の癌を扱う上で、患者さん本人や家族の希望を尊重する際に大切な概念ではないかと思われます。

ここで日本人の死生観について参考になる本を紹介します。福島県の臨済宗の僧侶で芥川賞作家である玄侑宗久氏は「日本人のこころのかたち」という本で、日本人特有の物の考え方として「不二と両行」という概念を紹介しています。「不二」というのは、本来相異なる概念、例えば生と死というものを別々のものとして考えず、一体、連続したものと捉えるということです。両行というのはやはり別々の概念を両方活かして独自の文化にしてしまう、和魂洋才、神仏習合のような考え方を言います。
この生死を一体と考えることは、人間を肉体と魂に分けて考えた時に、肉体の救いを薬師如来に託し、魂の救いを阿弥陀如来に託すことで両方の如来が揃う事で人間の安寧が保証されるという考え方に現れます。そして肉体が滅んでも魂が生き続けて、やがてこの世に戻ってくることを「黄泉帰る」と表現したり、驚いたときに一次的に我を忘れたようになることを魂が消える、「魂消る」と表現することに現れます。魂が無くなる状態を「惚」または「呆」と言いますが、年老いて肉体が残って魂が先に逝った状態が「痴呆」と考えられたのかも知れません。葬儀の追悼のことばで「また天国で一緒に酒を酌み交わしましょう」などと挨拶をするのも魂は継続するものと考え、死を断絶と考えない日本人の思想と言えるかも知れません。これは死後神の復活に際して神との契約に則して裁きを受けるとする一神教の考え方とは異なるもののように思います。
ということで「つかみ」は終わりにして「がん医療におけるこころの問題」について勉強してゆきたいと思います。ありがとうございました。

















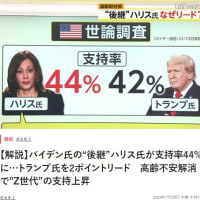








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます