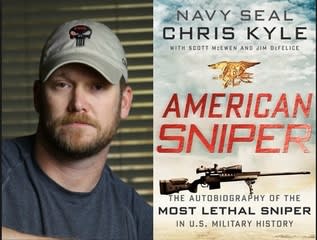書評 イスラーム 生と死と聖戦 中田 考 著 集英社新書 2015年刊
イスラム国関連で話題になったイスラム教信者でありイスラム法学者でもある中田 考氏のまさにムスリムにとっての死生観と聖戦について解りやすく解説した本で、特にキリスト教との違いや今話題のジハードについてのとらえ方について良くわかる内容でした。
一神教における死生観というのは、我々日本人にはなかなか理解できないもののはずですが、海外のドラマや小説における霊魂の存在や、医療における死との向き合い方などを顧みるに、実はキリスト教やイスラム教においても、日本人との考え方とあまり差がないのではないかという印象も持っていました。
死生観
キリスト教においては、神によって創造された人は死ぬと神による審判を受けることになっていて、その後地獄、天国、煉獄にゆくことになっているようですが、またこの世に生まれ変わるという考え方も映画などでは一部にはあるようです。イスラムにおいては霊魂と肉体は死ぬと離れて(霊肉二元論)、霊魂も暫くは意識があるのですが、キリスト教と同様に死後に裁きがあって、その後天国が地獄に行く事になっているということです。審判の時までは地中で待つことになるので、死ねば天国に行くという日本的な考えとは異なるということです。善行や徳を積めば、審判で認められて天国にゆけるのは皆同じなのですが、アッラーは比較的緩い神で、悪行よりも善行を点数多めに見てくれるという解釈があるそうです。一部悪人正機説に通じるものかも知れません(悪人でさえ救われるのだから、「いわんや善人をや」というのが本来の意味と言われますが)。面白いのは、人でも神でもない、精霊とか魔人のような存在(ジンと呼ばれる)があって、アラジンの魔法のランプから出てくるような、妖怪のような人智を超えた存在が考えられているようです。これは恐らくアニミズム的土着の宗教やインドの多神教からの影響と思います。
ジハードの意味
ジハードというのは「聖戦」を意味すると考えられますが、イスラム教徒にとってのジハードとは「イスラムの教義を実践するための自分との戦い」を意味するもので、これを「大ジハード」と呼ぶそうです。そして一般的に認識されている「イスラムの大義のための異教徒との戦い」は「小ジハード」と呼ばれて、本来的な意味とは少し異なる物であるとされます。しかも小ジハードは誰彼かまわず行えば良いというものではなく、カリフの指示の下に行う必要があると言う事です。ISILにおける自称カリフの「バグダディ」氏が異教徒との戦いを指示しているのは形の上でのカリフによる命令を取っているのだと言えます。ジハードによる死は、神の審判を受けずに天国に行けるとイスラム教では考えられているので、自爆テロという極端な方法が正当化されるようです。頭の悪い米国人にはこの小ジハードによる自爆テロと日本国における神風攻撃による自己犠牲によって靖国に祀られる事の違いは理解できないでしょう。ジハードはイスラムの実践によって自分が天国に行けるという利己的な目的で行われるのであって、国や家族を思いながら自分を犠牲にする神風の精神とは全く異なるものであると言えます。
イスラムと国家
以前ISILは国家の体をなしていない、という事をブログに書きましたが、この本を読むと、本来イスラム教は社会のあり方をも規定していてウエストファリア条約で規定された現代国家のあり方自体「規定外」の物であるという説明(第4章)があり成る程と思いました。つまり政教分離の考え方自体をイスラムは否定していて、イスラム教を信ずる人達の集まりの中で社会は成り立つようにできているのであって、国家といった別の規範や境目があること自体が誤りなのだということになります。その意味でイスラム教は「真のグローバリズム」とつながる所もあり、これは以前紹介した「一神教と国家」にも通じる内容です。
イスラムとの共存
では我々日本人のような多神教(仏教と神道どちらもまあまあ信じている)的な人達とイスラム教徒は仲良く暮らして行く事ができるのか、という問題になります。ここでイスラムでは「剣かコーランか」という二者択一を迫られると言われるけれども、これは誤解であり、「剣か税かコーランか」が正しいと説明されます。確かにエジプトなどのイスラム圏においてもコプト教徒などの古いキリスト教信者達が残っていて彼らは税を払う事で改宗をしなくてもイスラム教社会の中で普通に暮らして来た事の証です。ISILはコプト教徒達を殺害し、暴虐だとされていますが、正に本来のイスラムの教えから逸脱した行為と言えます。イスラム教徒はイスラムの教義の実践を邪魔さえしなければ異教徒の存在を許さないということはないのが本来のあり方であって、無理矢理改宗を迫るということはないというのが正しい解釈と思われます。
イスラム国というのはイスラム教の教義をうまく取り入れた中東に戦乱を起こすための米国戦争勢力の方便だろうと私は思っていますが、イスラムの教義を逸脱した世俗主義による統治を行っている中東において、本来のイスラムに戻ろうという純朴な若者達を惹き付ける魅力があるのは確かなのでしょう。だからこそ不用意にイスラム国を討伐する勢力に日本が加担する事(自衛隊を派遣して戦争をさせ、米国戦争勢力の片棒を担いで金儲けをさせてもらう事)には私は反対です。


本題と直接関係はありませんが、1998年のアメリカ映画で死後の世界と天国、地獄の様子(それは各人の持つイメージがそのまま現れるという解釈になってます)が描かれた印象的な映画です。完全なキリスト教の教義とは少し違うようでこれがヒット作として広く受け入れられた事は興味深いと思いました。