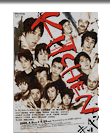NINAGAWA COCOONシリーズの第2弾。
COCOONシリーズの第2弾。
5月『メディア』のチケットを買っていたら、冒頭遅刻。またまた入場制限だったが『将門』の時とは違ってモニター画面でちゃんと見せてくれた。サービスレベルアップを確認。合格?!
いつもと同じように何も知らずに観に行ったが、入場したら舞台の上はロの字に調理施設が並べられたまさに調理場。今回の私の席は2階のD列だったが、舞台が斜め上から全体的に見えるいい位置だった。これでコクーンシートなのだからありがたい。舞台奥にも客席が設けられ、舞台を囲んでいる。向こう側とこちら側の両側の通路が舞台の延長で大活躍。また舞台はロンドンということだったのだが、登場人物がイギリス人だけではなく、アイルランド人やユダヤ系の人がいるというのは予想の範囲内だとしてもドイツ人、キプロス人(元イギリスの植民地)までがいて一緒に働いているというのは意外で、ヨーロッパ社会への私の認識不足を痛感した。

ひとりまたひとりと登場人物が出勤してきて、昨晩起きたドイツ人のペーター(成宮寛貴)とキプロス人のガストン(大川浩樹)の大喧嘩の噂話から始まる。変化の少ない職場に一石が投じられたようだ。それぞれの登場人物は、仕事を始める準備のしぐさの中で多くない台詞でそれぞれの置かれた状況、人物同士の関係性を伝えていく。あまり高級でないレストランの調理場で働く者、給仕長、ウェイトレス...。オーナーも顔を出す。仲間関係、対立関係、恋愛関係...。ドイツ人同士で大きな声でドイツ語で内緒話をする時は天井からの字幕を使ってドイツ語をしゃべらせるという方法を使っていてなかなか憎いことをすると思う。
喧嘩の仲直りもされず、緊張関係が高まるがランチタイムになって注文が相次ぎ、それに応えて戦場と化すキッチン。待ちきれずにペーターの料理の盛り付けに手を出そうとするウェイトレス、彼は「オレの領域を侵すな」とどなる。その戦場の様子の中でも料理をつくる仕草は全てマイムなのだが、本当に食材をつかみ道具を使って調理し、盛り付け、ウェイトレスが両手に皿を持って運んでいくかのような身についた動き、それぞれのリアルな動きに本当の調理場の戦場の迫力が伝わってきた。そこで幕。
ロビーの軽食コーナーにはこの作品にちなんで特別メニューが用意されている。ケチな私はいつもはここでは食べないのだが、やはり我慢できずにベーグルサンドを食べた。
後半は、ランチタイムが過ぎた休憩時間から始まる。お菓子担当のふたりは休憩時間にも仕事をやめない。それがペーターを苛立たせる。ペーターは夢を話してみろと皆にたきつける。「もっと寝たい」とか「金だ」とか「女だ」とかいろいろな話が出るが、本人からはついに何も出てこない。ここで一番印象に残ったのが高橋洋が演じるポールの話だった。アパートの隣に住む男の一家となんとなく近所付き合いをする中で友人を得たと思っていたのだ。バスの運転手をしている男の長期のストライキのためにバスに乗れずにその分歩くために早く出勤するという事態にも彼を応援したいと何も言わなかった。ところが、ある時ポールがせめて自分の気持ちを平和行進に加わるということで表明しようと行進に参加したのに、それを知った男は自分たちバスの運行手の運転の邪魔をした平和行進に参加したヤツはくそくらえだと罵った。そのことで大きく傷ついてしまった経験を話す中でその時の傷を引きずっている姿が浮かび上がる。日本と違ってイギリスの労働運動はもう少し根強いから長期のストライキなどもある。しかしながらストに参加する者すべてが自分の生活に直接関係があると思えない平和のための行進などに共感や支持もしないという現実がある。自分中心にものごとを考えると人と人とがわかりあうことは難しいし、それを当然と受け止めた上でどのように折り合っていくのかを考えるのもなかなか大変だと思う。

夢を語れないペーターだが、それは3年越しの不倫関係にあるモニク(杉田かおる)と幸せになることが夢だからである。彼女は夫と別れたいけれど切り出せないといいながら若いペーターと付き合っているが、熱くなっているのはペーターの方で彼女の方はもう2回も子どもを堕ろしている。いくら彼が若いとはいっても3年もそういう状態にあるのはすでに腐れ縁だと感じているのではないかと思っていたら、やはり愛想づかし。「夫は私のために家を買うと言ってくれてるの」ときた。そこで、ペーターは逆上し、包丁をもって大暴れしてしまうのだった。最後、オーナーが「自分の全てであるこの店を滅茶苦茶にしおって」と切れて使用人一同にあたりちらす。使用人一同は、店を愛してはいるが自分たちにはひとかけらの愛情も示さないオーナーに対して冷たい視線を投げかけながら、全員が客席の通路に去って舞台の調理場を見つめて終幕。調理場でのある一日、それも特別な事件が起こった一日を描いた舞台である。しばらくはこの騒ぎでレストランは客足が遠のくだろう。しかしながらそんなに遠くない日に忘れられ、事件を起こしたペーターを除く残りのメンバーは生きていくためにいつものような毎日を繰り返していくのだろうと思った。
キャスト評
ペーター=成宮寛貴
女装が話題になった『お気に召すまま』では大苦戦していたが、若者の焦燥感をストレートに出すこの役では大成功した。焦燥感が空回りせずに台詞も滑舌がよくなり、目もぎらぎら輝き身体の動きも軽快。蜷川さんの期待に応えたと思う。見直した。
モニク=杉田かおる
彼女の舞台は初めてで楽しみに観に行った。光輝くほど美人ではないがやはりきれいだし、芝居はうまい。若いペーターが夢中になる「イイ女」だった。年上でしっかりしていて甘えさせるのも上手。そして色気もある年下キラーの女。しかし、これからの人生を考えてさらっと愛想づかしをする罪な女を可愛く演じてくれた。
ポール=高橋洋
いつも蜷川作品の中で気になる台詞をいう役回りをすることが多く、印象深い。この役でもず~っと言葉少なくちょこまかと調理し続けている。ペーターのことは好きになれないと言いながら求めに応じて夢を語るシーンが見事だった。得られたと自分では思っていた友情が幻だったと気づいた時の孤独が痛いほどに伝わってきた。
ガストン=大川浩樹
彼がなぜペーターにボコボコにされるのだろうと思うほど大柄な立派な身体。今までに見た役は『リチャードⅢ世』のこわ~い部下役などのように強面の役ばかりだった。今回は大柄だけどこわくはない役。若者と年配者の間くらいの年齢の役で、私の席から遠い方に持ち場があったが大きな身体で存在感がすごかった。蜷川作品には彼がいるのが当たり前のようになっている。
アルフレッドー=津嘉山正種
『喪服の似合うエレクトラ』以来だった。言葉は少ないがベテランコックで腕も確かな様子を身体の動きで表現しなくてはならない。そして少ない台詞はあの渋いお声で人生の深さを感じさせてくれた。


この作品は1957年にアーノルド・ウェスカーによって書かれ、ジョン・オズボーンの『怒りをこめて振り返れ』とともに「怒れる若者たち」とよばれる時代に反旗を翻す1960年代文化の代表のようになっているとパンフに書いてあった。日本でも清水邦夫がその時代の作家だという。
しかしながら、今の若者はこのように感情を直接的に表現しないが、成宮寛貴の演技は十分イライラ感を全身で出し切っていて、観ているこちらも相当触発されてしまい、イライラしてしまった。2回目を観たいとは思えなかったが、1月の清水の『将門』演出に続いて蜷川幸雄がこの作品を演出することで、今こそ多くの人に時代について考えろというメッセージを発しているように感じている。



写真は、今回公演のHPよりのチラシ写真。
(当初アップした時に、文中で最後までペーターと書くべきところを途中からポールにしてしまい、わけがわからなくしてしまっておりました。ごめんなさい。訂正しておきます。)
(といいながら翌日もマチガイを見つけて訂正入れました。重ねて申し訳ありません。訂正しておきます。)
 COCOONシリーズの第2弾。
COCOONシリーズの第2弾。5月『メディア』のチケットを買っていたら、冒頭遅刻。またまた入場制限だったが『将門』の時とは違ってモニター画面でちゃんと見せてくれた。サービスレベルアップを確認。合格?!
いつもと同じように何も知らずに観に行ったが、入場したら舞台の上はロの字に調理施設が並べられたまさに調理場。今回の私の席は2階のD列だったが、舞台が斜め上から全体的に見えるいい位置だった。これでコクーンシートなのだからありがたい。舞台奥にも客席が設けられ、舞台を囲んでいる。向こう側とこちら側の両側の通路が舞台の延長で大活躍。また舞台はロンドンということだったのだが、登場人物がイギリス人だけではなく、アイルランド人やユダヤ系の人がいるというのは予想の範囲内だとしてもドイツ人、キプロス人(元イギリスの植民地)までがいて一緒に働いているというのは意外で、ヨーロッパ社会への私の認識不足を痛感した。

ひとりまたひとりと登場人物が出勤してきて、昨晩起きたドイツ人のペーター(成宮寛貴)とキプロス人のガストン(大川浩樹)の大喧嘩の噂話から始まる。変化の少ない職場に一石が投じられたようだ。それぞれの登場人物は、仕事を始める準備のしぐさの中で多くない台詞でそれぞれの置かれた状況、人物同士の関係性を伝えていく。あまり高級でないレストランの調理場で働く者、給仕長、ウェイトレス...。オーナーも顔を出す。仲間関係、対立関係、恋愛関係...。ドイツ人同士で大きな声でドイツ語で内緒話をする時は天井からの字幕を使ってドイツ語をしゃべらせるという方法を使っていてなかなか憎いことをすると思う。
喧嘩の仲直りもされず、緊張関係が高まるがランチタイムになって注文が相次ぎ、それに応えて戦場と化すキッチン。待ちきれずにペーターの料理の盛り付けに手を出そうとするウェイトレス、彼は「オレの領域を侵すな」とどなる。その戦場の様子の中でも料理をつくる仕草は全てマイムなのだが、本当に食材をつかみ道具を使って調理し、盛り付け、ウェイトレスが両手に皿を持って運んでいくかのような身についた動き、それぞれのリアルな動きに本当の調理場の戦場の迫力が伝わってきた。そこで幕。
ロビーの軽食コーナーにはこの作品にちなんで特別メニューが用意されている。ケチな私はいつもはここでは食べないのだが、やはり我慢できずにベーグルサンドを食べた。
後半は、ランチタイムが過ぎた休憩時間から始まる。お菓子担当のふたりは休憩時間にも仕事をやめない。それがペーターを苛立たせる。ペーターは夢を話してみろと皆にたきつける。「もっと寝たい」とか「金だ」とか「女だ」とかいろいろな話が出るが、本人からはついに何も出てこない。ここで一番印象に残ったのが高橋洋が演じるポールの話だった。アパートの隣に住む男の一家となんとなく近所付き合いをする中で友人を得たと思っていたのだ。バスの運転手をしている男の長期のストライキのためにバスに乗れずにその分歩くために早く出勤するという事態にも彼を応援したいと何も言わなかった。ところが、ある時ポールがせめて自分の気持ちを平和行進に加わるということで表明しようと行進に参加したのに、それを知った男は自分たちバスの運行手の運転の邪魔をした平和行進に参加したヤツはくそくらえだと罵った。そのことで大きく傷ついてしまった経験を話す中でその時の傷を引きずっている姿が浮かび上がる。日本と違ってイギリスの労働運動はもう少し根強いから長期のストライキなどもある。しかしながらストに参加する者すべてが自分の生活に直接関係があると思えない平和のための行進などに共感や支持もしないという現実がある。自分中心にものごとを考えると人と人とがわかりあうことは難しいし、それを当然と受け止めた上でどのように折り合っていくのかを考えるのもなかなか大変だと思う。

夢を語れないペーターだが、それは3年越しの不倫関係にあるモニク(杉田かおる)と幸せになることが夢だからである。彼女は夫と別れたいけれど切り出せないといいながら若いペーターと付き合っているが、熱くなっているのはペーターの方で彼女の方はもう2回も子どもを堕ろしている。いくら彼が若いとはいっても3年もそういう状態にあるのはすでに腐れ縁だと感じているのではないかと思っていたら、やはり愛想づかし。「夫は私のために家を買うと言ってくれてるの」ときた。そこで、ペーターは逆上し、包丁をもって大暴れしてしまうのだった。最後、オーナーが「自分の全てであるこの店を滅茶苦茶にしおって」と切れて使用人一同にあたりちらす。使用人一同は、店を愛してはいるが自分たちにはひとかけらの愛情も示さないオーナーに対して冷たい視線を投げかけながら、全員が客席の通路に去って舞台の調理場を見つめて終幕。調理場でのある一日、それも特別な事件が起こった一日を描いた舞台である。しばらくはこの騒ぎでレストランは客足が遠のくだろう。しかしながらそんなに遠くない日に忘れられ、事件を起こしたペーターを除く残りのメンバーは生きていくためにいつものような毎日を繰り返していくのだろうと思った。
キャスト評
ペーター=成宮寛貴
女装が話題になった『お気に召すまま』では大苦戦していたが、若者の焦燥感をストレートに出すこの役では大成功した。焦燥感が空回りせずに台詞も滑舌がよくなり、目もぎらぎら輝き身体の動きも軽快。蜷川さんの期待に応えたと思う。見直した。
モニク=杉田かおる
彼女の舞台は初めてで楽しみに観に行った。光輝くほど美人ではないがやはりきれいだし、芝居はうまい。若いペーターが夢中になる「イイ女」だった。年上でしっかりしていて甘えさせるのも上手。そして色気もある年下キラーの女。しかし、これからの人生を考えてさらっと愛想づかしをする罪な女を可愛く演じてくれた。
ポール=高橋洋
いつも蜷川作品の中で気になる台詞をいう役回りをすることが多く、印象深い。この役でもず~っと言葉少なくちょこまかと調理し続けている。ペーターのことは好きになれないと言いながら求めに応じて夢を語るシーンが見事だった。得られたと自分では思っていた友情が幻だったと気づいた時の孤独が痛いほどに伝わってきた。
ガストン=大川浩樹
彼がなぜペーターにボコボコにされるのだろうと思うほど大柄な立派な身体。今までに見た役は『リチャードⅢ世』のこわ~い部下役などのように強面の役ばかりだった。今回は大柄だけどこわくはない役。若者と年配者の間くらいの年齢の役で、私の席から遠い方に持ち場があったが大きな身体で存在感がすごかった。蜷川作品には彼がいるのが当たり前のようになっている。
アルフレッドー=津嘉山正種
『喪服の似合うエレクトラ』以来だった。言葉は少ないがベテランコックで腕も確かな様子を身体の動きで表現しなくてはならない。そして少ない台詞はあの渋いお声で人生の深さを感じさせてくれた。


この作品は1957年にアーノルド・ウェスカーによって書かれ、ジョン・オズボーンの『怒りをこめて振り返れ』とともに「怒れる若者たち」とよばれる時代に反旗を翻す1960年代文化の代表のようになっているとパンフに書いてあった。日本でも清水邦夫がその時代の作家だという。
しかしながら、今の若者はこのように感情を直接的に表現しないが、成宮寛貴の演技は十分イライラ感を全身で出し切っていて、観ているこちらも相当触発されてしまい、イライラしてしまった。2回目を観たいとは思えなかったが、1月の清水の『将門』演出に続いて蜷川幸雄がこの作品を演出することで、今こそ多くの人に時代について考えろというメッセージを発しているように感じている。



写真は、今回公演のHPよりのチラシ写真。
(当初アップした時に、文中で最後までペーターと書くべきところを途中からポールにしてしまい、わけがわからなくしてしまっておりました。ごめんなさい。訂正しておきます。)
(といいながら翌日もマチガイを見つけて訂正入れました。重ねて申し訳ありません。訂正しておきます。)