記憶とは、不思議なものだ。
昨年3月11日の東日本大震災を期に、日本人になる決意をした日本文学研究者のドナルド・キーン氏(90歳)が、今年2012年1月1日の新聞(朝日新聞)に記憶について次のように述べている。
「小さくなった人間が、人の体内に入り込む「ミクロの決死隊」という映画があったが、自分の頭の中に入り込み、生い茂る記憶のジャングルを歩けば、どんなに面白いだろう。些末な記憶なの堆積がひっくりかえったオモチャ箱のように散乱しているだろう」
人がそれぞれ生きてきただけの時間の記憶が、過去として堆積しているとするならば、記憶の量は膨大なものになる。単純に時間に換算しても、20歳の人で約17万5千時間、60歳の人では約52万6千時間となる。人の最初の記憶が始まるとする3歳ないし5歳から起算したとしても相当な時間量となる。
その記憶は、年表のように年代順に整理されていればいいのだが、そうではない。あるいは、ジャンル分けされているわけでもない。きわめてアトランダムなのだ。
記憶から取り出した具象は、どれが先でどれが後だったかは、あとで、つまり思い出したそのとき、確認・検証しないといけない。その取り出した記憶の具象には、タグやシールが貼ってあるわけではないのだ。
だから、整理学の本が売れるわけだ。
記憶は、ビデオやDVDのように映像だけなのか。いや、音楽や、匂いや味覚で甦る記憶もある。とすれば、記憶は僕たちが現在体感するすべてを内包しているものなのか。
また、記憶を巻き戻してと言うが、過去をどう振り返っても、ビデオやDVDのように、記憶は巻き戻るのではない。常に取り出した記憶は基点から現在の方向に進み、つまり時間の経過のように進み、現在に近い方から遠い方にと逆進行はしない。
ということは、どうやっても時間を巻き戻すことができないということではなかろうか。ということは、タイムマシンは人間の想像以上のものではないと言えるのではなかろうか。たとえ、ニュートリノやそれ以外の物質が光より速いとしても。
いや、このことを根拠に、物理学の専門家でもない私がそんなことを断定できはしないが。
このどこに何があるかも分からず、整理不可能な記憶をジャングルにたとえるなら、それこそ生い茂る密林だろう。
しかし、残念なことに、その生い茂るジャングルの中から引き出すことができる記憶は、わずかなものでしかない。大半は思い出そうと思っても、甦らせることはできない。
そのジャングルそのものが次第に枯れ果てて、徐々に失われているかもしれないのだ。実際のジャングルの木々が失われれば、そこに何が残るか。砂漠である。
記憶のジャングルが失われれば……
さらに、キーン氏は続ける。
「記憶とは不思議なものだ。歳をとるにしたがい、先ほどの出来事、昨日の出来事が次々と頭から消えていく。なのに思いがけないひと時に、過ぎた日の断面が突然、甦る。
そんなことは誰にでもあるだろう。ある出来事を経験した時、それが数十年後に別の抒情詩となって戻ってくるとは、人々は日々の行いの中で予想できないからだ」
ここに言われているように、記憶は実は少し違った姿で甦るようだ。
そのときの思いで、記憶の具象は、美しく着飾ったり、悲しみに彩られたり。あるいは、別の物語に脚色されたりするのだろうか。
「思い出は再構成であって、再現の過程ではない。
過去に体験したある出来事を思い出すとき、われわれは脳に分散されている符号化された構成要素を再構成する。想起が、もともとの出来事の複製のようなものであることはほとんどない」(「子どもの頃の思い出は本物か」カール・サバー著)
私たちは、自分の記憶を本当のことだと、つまりそれが真実だと、信じ、思い込んでいる。しかし、思い起こすたびにその思い出の記憶は再構成されて、少しずつ変形した姿となっているようなのだ。
思い出の記憶は、ビデオやDVDのように、再現のそのままの姿ではない。言い換えれば、記憶はその都度、いわば「上書き保存」されているのである。
思い出は、作り変えられているのだろうか。
昨年3月11日の東日本大震災を期に、日本人になる決意をした日本文学研究者のドナルド・キーン氏(90歳)が、今年2012年1月1日の新聞(朝日新聞)に記憶について次のように述べている。
「小さくなった人間が、人の体内に入り込む「ミクロの決死隊」という映画があったが、自分の頭の中に入り込み、生い茂る記憶のジャングルを歩けば、どんなに面白いだろう。些末な記憶なの堆積がひっくりかえったオモチャ箱のように散乱しているだろう」
人がそれぞれ生きてきただけの時間の記憶が、過去として堆積しているとするならば、記憶の量は膨大なものになる。単純に時間に換算しても、20歳の人で約17万5千時間、60歳の人では約52万6千時間となる。人の最初の記憶が始まるとする3歳ないし5歳から起算したとしても相当な時間量となる。
その記憶は、年表のように年代順に整理されていればいいのだが、そうではない。あるいは、ジャンル分けされているわけでもない。きわめてアトランダムなのだ。
記憶から取り出した具象は、どれが先でどれが後だったかは、あとで、つまり思い出したそのとき、確認・検証しないといけない。その取り出した記憶の具象には、タグやシールが貼ってあるわけではないのだ。
だから、整理学の本が売れるわけだ。
記憶は、ビデオやDVDのように映像だけなのか。いや、音楽や、匂いや味覚で甦る記憶もある。とすれば、記憶は僕たちが現在体感するすべてを内包しているものなのか。
また、記憶を巻き戻してと言うが、過去をどう振り返っても、ビデオやDVDのように、記憶は巻き戻るのではない。常に取り出した記憶は基点から現在の方向に進み、つまり時間の経過のように進み、現在に近い方から遠い方にと逆進行はしない。
ということは、どうやっても時間を巻き戻すことができないということではなかろうか。ということは、タイムマシンは人間の想像以上のものではないと言えるのではなかろうか。たとえ、ニュートリノやそれ以外の物質が光より速いとしても。
いや、このことを根拠に、物理学の専門家でもない私がそんなことを断定できはしないが。
このどこに何があるかも分からず、整理不可能な記憶をジャングルにたとえるなら、それこそ生い茂る密林だろう。
しかし、残念なことに、その生い茂るジャングルの中から引き出すことができる記憶は、わずかなものでしかない。大半は思い出そうと思っても、甦らせることはできない。
そのジャングルそのものが次第に枯れ果てて、徐々に失われているかもしれないのだ。実際のジャングルの木々が失われれば、そこに何が残るか。砂漠である。
記憶のジャングルが失われれば……
さらに、キーン氏は続ける。
「記憶とは不思議なものだ。歳をとるにしたがい、先ほどの出来事、昨日の出来事が次々と頭から消えていく。なのに思いがけないひと時に、過ぎた日の断面が突然、甦る。
そんなことは誰にでもあるだろう。ある出来事を経験した時、それが数十年後に別の抒情詩となって戻ってくるとは、人々は日々の行いの中で予想できないからだ」
ここに言われているように、記憶は実は少し違った姿で甦るようだ。
そのときの思いで、記憶の具象は、美しく着飾ったり、悲しみに彩られたり。あるいは、別の物語に脚色されたりするのだろうか。
「思い出は再構成であって、再現の過程ではない。
過去に体験したある出来事を思い出すとき、われわれは脳に分散されている符号化された構成要素を再構成する。想起が、もともとの出来事の複製のようなものであることはほとんどない」(「子どもの頃の思い出は本物か」カール・サバー著)
私たちは、自分の記憶を本当のことだと、つまりそれが真実だと、信じ、思い込んでいる。しかし、思い起こすたびにその思い出の記憶は再構成されて、少しずつ変形した姿となっているようなのだ。
思い出の記憶は、ビデオやDVDのように、再現のそのままの姿ではない。言い換えれば、記憶はその都度、いわば「上書き保存」されているのである。
思い出は、作り変えられているのだろうか。











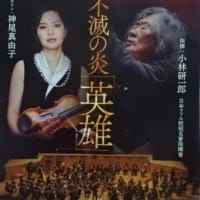

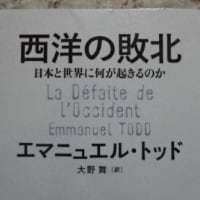











だれでも思い出したくない記憶は封印し、
都合のいい記憶はどんどん上書きして美化しているかもしれませんね。
生後何歳からの記憶があるかは人によって様々でしょうが、
写真やビデオなどの記録装置がなかったころは美化できた幼少期も
今の子供たちはバッチリ録画&保存されますから、
記憶の上塗りができない時代になったとも言えるのでしょうか?(笑)
ちょっとカワイソウ?
毎回、記憶は上塗りされる。
となると、自分の過去に多少の疑問を持たざるを得ませんね。
記憶は、本来は、曖昧になる前に更新しないといけませんが。