
*大航海のポルトガル
ポルトガルというと、海辺の夕日を思い浮かべる。暮れていく陽を見ている大人の後姿が重なる。
落日。晩秋。旅愁。孤影。矜持。
世知辛い競争世界から、少し離れたところで静かにゆっくりと自分の脚で歩いている大人の姿だ。
「俺も若いころはあんな(悪ガキの)時代があったなぁ」と、かつての若かりし頃を懐かしみながら、世界を斜に眺めているといった感じとでも言おうか。そこに、幾分の寂しさもあるかもしれないが。
1543年に種子島にポルトガル船が漂着し、日本に鉄砲を伝えた。ポルトガル人こそ、日本がヨーロッパと接触した最初の人種(国)で、やがて日本の南蛮貿易へと繋がっていった。
これより先、ポルトガル人のヴァスコ・ダ・ガマがインドに到達し、インドを目指したペドロ・アルヴァレス・カブラルがブラジルを見いだし、ポルトガルによるアメリカ大陸の植民地化が進んだ。
つまり、このころポルトガルはスペインと並び、大航海時代の世界の最先頭を走っていた。
そして、アフリカ大陸、南米大陸、それにアジアの各地に植民地を有するに至った。
しかし、広大な植民地を維持することができず、徐々に勢力が衰えていったポルトガルは19世紀にはブラジルを手放すに至った。
近代に入り、イギリス、アメリカはじめヨーロッパ各国が産業革命により国力と勢力を拡大化させたのに比し、ポルトガルの産業は成長させることができず、次第に勢力は衰えていった。
第2次世界大戦後は、世界が脱植民地化のなか、アジア・アフリカの植民地が次々と独立していく。
そんななか、1974年、ポルトガルは無血の内にそれまでの独裁体制を覆すカーネーション革命を達成する。
1975年中に、ポルトガルはマカオ以外の植民地を全面的に喪失した。1999年にはマカオも中華人民共和国に返還され、2002年には、名目上ポルトガルの植民地だった東ティモールが独立を果たした。
15世紀の大航海時代とともに生まれたポルトガル帝国は、21世紀の幕開けとともにその歴史を終えたといえる。
*
ポルトガルは、ヨーロッパの一国である。
イギリスほど高慢でない。
フランスほど洒落ていない。
ドイツほど自己主張しない。
イタリアほど派手でない。
スペインほど脂っぽくない。
ポルトガルは遠くを見つめている。
*
もうずいぶん前のことだが、「関口知宏のヨーロッパ鉄道の旅」という番組があり、その「ポルトガル編」の最後に、関口知宏はこうつぶやく。
「ポルトガルは大人の国だ。かつては日本でも、大人を感じることはあった。が、近頃はもうなくなってしまった。
いつか外国に住むことになったとしたら、僕はその地にポルトガルを選ぶと思う」
そのあと、彼が作った曲「訪秋」が流れた。まさしく哀愁を含んだファドだった。
*哀愁のリスボン
1974年、初めてパリを旅したとき、帰りにポルトガルのリスボンに立ち寄った。
何の知識も持っていなかったが、リスボンの街は日本の地方都市のような落ち着きを感じさせた。
夜になり、リスボンの下町の石畳を歩き、歌声が漏れる明かりが灯るレストラン酒場に入った。ファドを聴かせる店だった。
リスボンでは、「カザ・デ・ファド(Casa de Fado)」と呼ばれるファドを聴かせるレストランやバーが、夜ともなると灯りをともすのだった。
ファド(Fado)は、ポルトガルギターに合わせて歌う、ポルトガル独特の哀愁に充ち溢れた歌だった。
私は翌日、リスボンの街中の路上で「アマリア・ロドリゲス」のドーナツ盤レコードを買った。アマリア・ロドリゲスは、ポルトガルで最も有名な実力ファド歌手だった。
日本に帰ってからも、彼女の歌うファドはよく聴くことになった。
1995年、2度目のリスボンへ行ったときも、夜の街角でファドの店に入った。
フラリと入った店だったが、偶然にも20年前に行った店だった。その店の壁に、見覚えのある(写真にも残っている)絵を見つけて、かつてここに来た店だと気がついた。
その絵はファドの絵として象徴的なようで、酔った女性の横でポルトガルギターを弾きながら歌っているツバ広の帽子を被った男を描いた絵「ファド」(ジョゼ・マリョア画)である。(写真、「ファド」(ジョゼ・マリョア))
古いファドの店の雰囲気を表しているのだろう。
リスボンの街とファドは切り離せない。
ファドはポルトガルの歌である。
例えていえば、フランスのシャンソン、イタリアのカンツォーネのように。
*銀座でポルトガルの音楽、ファドを楽しむ
日本で、ポルトガル料理の店は少ないが、ファドを聴かせる「カザ・デ・ファド(Casa de Fado)」となると、そうあるものではない。
銀座のポルトガル・レストラン「ヴィラモウラ(VILAMOURA)銀座本店」で、6月21日にファドを聴かせるというので、夕食を兼ねて出かけた。
店は、泰明小学校の前にある。
食事はコースである。
ポルトガルは、海洋で栄えた国だけあって海産物の料理に特徴がある。
塩漬け干し鱈のバカリャウ、イワシ1尾のオーブン焼き(ポルトガルでは炭火焼き)。その他、ポルトガル料理らしい豚とアサリのスパイス煮込みのアレンテジャーナなど、堪能した。
本命のファドである。食事の合間に味わうことができた。
ファドは通常、歌い手のファディスタと、ポルトガルギター演奏者のギターラ、ギター演奏者のヴィオラで演奏されるそうである。
この日の出演は以下のとおりである。
ファディスタ:高柳卓也、安村今日子、ギターラ(ポルトガルギター):月本一史、ヴィオラ(ギター):小川皓史、伊代田大樹
ファドは悲恋や運命や人生を愁う哀しみを帯びた歌が主であるが、最近は明るい歌も多いようである。
2015年、東京国際フォーラムでの「ラ・フォル・ジュルネ」に、初めてのことだと思うが、ポルトガルのファッド歌手が出演するというので聴きに行った。アントニオ・ザンブージョという男性歌手で、それまでのファドの印象とは全く違った味を持つ歌い手だった。
今回、ファドを聴いて改めて感じたのは、ポルトガルギターの独特の音色である。
ポルトガルギターのギターラだけの演奏や、ギターラとクラシックギターのヴィオラだけの演奏もあり、それはそれで味わい深いものがあった。
ファドの歌の哀愁を醸し出すのは、この12弦の民族楽器ポルトガルギターの音色だと、今更ながら再発見した思いだった。
ポルトガルというと、海辺の夕日を思い浮かべる。暮れていく陽を見ている大人の後姿が重なる。
落日。晩秋。旅愁。孤影。矜持。
世知辛い競争世界から、少し離れたところで静かにゆっくりと自分の脚で歩いている大人の姿だ。
「俺も若いころはあんな(悪ガキの)時代があったなぁ」と、かつての若かりし頃を懐かしみながら、世界を斜に眺めているといった感じとでも言おうか。そこに、幾分の寂しさもあるかもしれないが。
1543年に種子島にポルトガル船が漂着し、日本に鉄砲を伝えた。ポルトガル人こそ、日本がヨーロッパと接触した最初の人種(国)で、やがて日本の南蛮貿易へと繋がっていった。
これより先、ポルトガル人のヴァスコ・ダ・ガマがインドに到達し、インドを目指したペドロ・アルヴァレス・カブラルがブラジルを見いだし、ポルトガルによるアメリカ大陸の植民地化が進んだ。
つまり、このころポルトガルはスペインと並び、大航海時代の世界の最先頭を走っていた。
そして、アフリカ大陸、南米大陸、それにアジアの各地に植民地を有するに至った。
しかし、広大な植民地を維持することができず、徐々に勢力が衰えていったポルトガルは19世紀にはブラジルを手放すに至った。
近代に入り、イギリス、アメリカはじめヨーロッパ各国が産業革命により国力と勢力を拡大化させたのに比し、ポルトガルの産業は成長させることができず、次第に勢力は衰えていった。
第2次世界大戦後は、世界が脱植民地化のなか、アジア・アフリカの植民地が次々と独立していく。
そんななか、1974年、ポルトガルは無血の内にそれまでの独裁体制を覆すカーネーション革命を達成する。
1975年中に、ポルトガルはマカオ以外の植民地を全面的に喪失した。1999年にはマカオも中華人民共和国に返還され、2002年には、名目上ポルトガルの植民地だった東ティモールが独立を果たした。
15世紀の大航海時代とともに生まれたポルトガル帝国は、21世紀の幕開けとともにその歴史を終えたといえる。
*
ポルトガルは、ヨーロッパの一国である。
イギリスほど高慢でない。
フランスほど洒落ていない。
ドイツほど自己主張しない。
イタリアほど派手でない。
スペインほど脂っぽくない。
ポルトガルは遠くを見つめている。
*
もうずいぶん前のことだが、「関口知宏のヨーロッパ鉄道の旅」という番組があり、その「ポルトガル編」の最後に、関口知宏はこうつぶやく。
「ポルトガルは大人の国だ。かつては日本でも、大人を感じることはあった。が、近頃はもうなくなってしまった。
いつか外国に住むことになったとしたら、僕はその地にポルトガルを選ぶと思う」
そのあと、彼が作った曲「訪秋」が流れた。まさしく哀愁を含んだファドだった。
*哀愁のリスボン
1974年、初めてパリを旅したとき、帰りにポルトガルのリスボンに立ち寄った。
何の知識も持っていなかったが、リスボンの街は日本の地方都市のような落ち着きを感じさせた。
夜になり、リスボンの下町の石畳を歩き、歌声が漏れる明かりが灯るレストラン酒場に入った。ファドを聴かせる店だった。
リスボンでは、「カザ・デ・ファド(Casa de Fado)」と呼ばれるファドを聴かせるレストランやバーが、夜ともなると灯りをともすのだった。
ファド(Fado)は、ポルトガルギターに合わせて歌う、ポルトガル独特の哀愁に充ち溢れた歌だった。
私は翌日、リスボンの街中の路上で「アマリア・ロドリゲス」のドーナツ盤レコードを買った。アマリア・ロドリゲスは、ポルトガルで最も有名な実力ファド歌手だった。
日本に帰ってからも、彼女の歌うファドはよく聴くことになった。
1995年、2度目のリスボンへ行ったときも、夜の街角でファドの店に入った。
フラリと入った店だったが、偶然にも20年前に行った店だった。その店の壁に、見覚えのある(写真にも残っている)絵を見つけて、かつてここに来た店だと気がついた。
その絵はファドの絵として象徴的なようで、酔った女性の横でポルトガルギターを弾きながら歌っているツバ広の帽子を被った男を描いた絵「ファド」(ジョゼ・マリョア画)である。(写真、「ファド」(ジョゼ・マリョア))
古いファドの店の雰囲気を表しているのだろう。
リスボンの街とファドは切り離せない。
ファドはポルトガルの歌である。
例えていえば、フランスのシャンソン、イタリアのカンツォーネのように。
*銀座でポルトガルの音楽、ファドを楽しむ
日本で、ポルトガル料理の店は少ないが、ファドを聴かせる「カザ・デ・ファド(Casa de Fado)」となると、そうあるものではない。
銀座のポルトガル・レストラン「ヴィラモウラ(VILAMOURA)銀座本店」で、6月21日にファドを聴かせるというので、夕食を兼ねて出かけた。
店は、泰明小学校の前にある。
食事はコースである。
ポルトガルは、海洋で栄えた国だけあって海産物の料理に特徴がある。
塩漬け干し鱈のバカリャウ、イワシ1尾のオーブン焼き(ポルトガルでは炭火焼き)。その他、ポルトガル料理らしい豚とアサリのスパイス煮込みのアレンテジャーナなど、堪能した。
本命のファドである。食事の合間に味わうことができた。
ファドは通常、歌い手のファディスタと、ポルトガルギター演奏者のギターラ、ギター演奏者のヴィオラで演奏されるそうである。
この日の出演は以下のとおりである。
ファディスタ:高柳卓也、安村今日子、ギターラ(ポルトガルギター):月本一史、ヴィオラ(ギター):小川皓史、伊代田大樹
ファドは悲恋や運命や人生を愁う哀しみを帯びた歌が主であるが、最近は明るい歌も多いようである。
2015年、東京国際フォーラムでの「ラ・フォル・ジュルネ」に、初めてのことだと思うが、ポルトガルのファッド歌手が出演するというので聴きに行った。アントニオ・ザンブージョという男性歌手で、それまでのファドの印象とは全く違った味を持つ歌い手だった。
今回、ファドを聴いて改めて感じたのは、ポルトガルギターの独特の音色である。
ポルトガルギターのギターラだけの演奏や、ギターラとクラシックギターのヴィオラだけの演奏もあり、それはそれで味わい深いものがあった。
ファドの歌の哀愁を醸し出すのは、この12弦の民族楽器ポルトガルギターの音色だと、今更ながら再発見した思いだった。











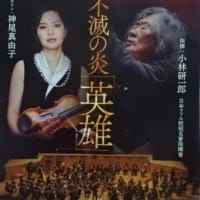

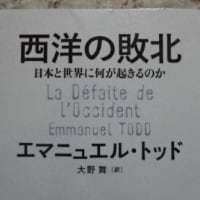











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます