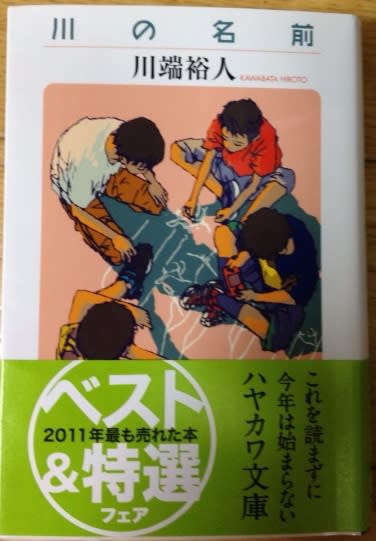本日、2013年3月29日をもって、豊田市矢作川研究所の研究員としての
5年間の勤めを終えることにしました。
この一週間、いやいや今月は
とにかく自分のやり残した仕事がないよう、
あちこち走り回りました。
そんな思いがつたわったのか、今日の午後、
『枝下用水120年史資料集』その2の印刷をお願いしている挙母印刷企画から
予定より一週間早く出来上がってきましたとの連絡があり、
夕刻、待ち切れず、受領してきました。
資料集の配布は枝下川神社始水式の16日を待たねばなりませんが、
出来上がりは落ち着いた色合いで、今回は10校まで進めていたため、
見たくないくらいに見てきたわけですが、
中身も改めてページをめくれば、これで良かったと自画自賛、
いい仕事が最後にできました。
そうこういうまもなく来週は4月1日、
月曜日は新年度初の編集ミーティングです。
この週末はすべてを忘れて
週明けから新たなスタートを頑張ろうと思います。
研究所の5年間を振り返れば、
研究所をとおして行ったからこそ信頼されてできたこともたくさんありました。
そして5年経ち、枝下用水史編集委員会として、信頼していただけるように
少しずつなってきたように思います。
これからは研究所の名前に頼らずに、
いろんなことをやってみようと思えるようになってきたことも事実です。
とにかく自分のこの選択を良かったと思えるよう、
いい仕事をしたいと思います。
今日はお昼に研究所のなかまたちとちょっと長めのやすみをとって
おいしいランチ。
ぐるぐるまきコースターを見つけて写真をとってもらいました。

週明け、新たな気持ちでがんばりたいと思います。
関係者の皆様、ありがとうございました。
5年間の勤めを終えることにしました。
この一週間、いやいや今月は
とにかく自分のやり残した仕事がないよう、
あちこち走り回りました。
そんな思いがつたわったのか、今日の午後、
『枝下用水120年史資料集』その2の印刷をお願いしている挙母印刷企画から
予定より一週間早く出来上がってきましたとの連絡があり、
夕刻、待ち切れず、受領してきました。
資料集の配布は枝下川神社始水式の16日を待たねばなりませんが、
出来上がりは落ち着いた色合いで、今回は10校まで進めていたため、
見たくないくらいに見てきたわけですが、
中身も改めてページをめくれば、これで良かったと自画自賛、
いい仕事が最後にできました。
そうこういうまもなく来週は4月1日、
月曜日は新年度初の編集ミーティングです。
この週末はすべてを忘れて
週明けから新たなスタートを頑張ろうと思います。
研究所の5年間を振り返れば、
研究所をとおして行ったからこそ信頼されてできたこともたくさんありました。
そして5年経ち、枝下用水史編集委員会として、信頼していただけるように
少しずつなってきたように思います。
これからは研究所の名前に頼らずに、
いろんなことをやってみようと思えるようになってきたことも事実です。
とにかく自分のこの選択を良かったと思えるよう、
いい仕事をしたいと思います。
今日はお昼に研究所のなかまたちとちょっと長めのやすみをとって
おいしいランチ。
ぐるぐるまきコースターを見つけて写真をとってもらいました。

週明け、新たな気持ちでがんばりたいと思います。
関係者の皆様、ありがとうございました。