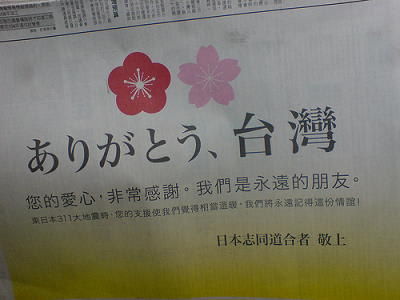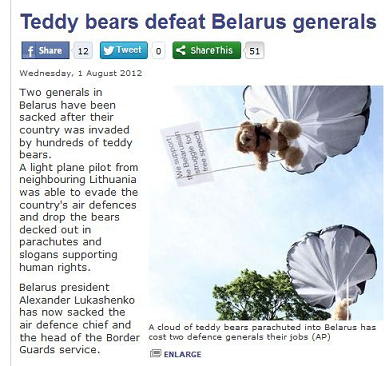(首都モガディシオのビーチの賑わい 100万人を超える難民とは結びつかない平和的光景です。ビーチの賑わいも難民も、ともにソマリアの現実です。“flickr”より By EvolvingPrimates http://www.flickr.com/photos/78850887@N07/7059761929/)
【議員275人は長老の推薦で決まる】
東アフリカのソマリアでは、内戦と実質的無政府状態、更には干ばつ被害のため難民が増え続け、すでに100万人を超えています。
****ソマリア難民100万人突破=10年間で3カ国目―国連****
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は17日、アフリカのソマリア難民がこれまでに100万人を突破したと明らかにした。深刻な干ばつや治安悪化により、隣国などに逃れる状況が依然続いている。
難民が100万人を超えたのはこの10年間でアフガニスタン、イラクに次ぎ3カ国目という。【7月17日 時事】
*******************
ソマリアには一応、05年から「暫定政府」が存在しますが、今日20日でその統治期限が終了します。
今年2月23日にロンドンで開催されたソマリアの安定化を協議する国際会議において、暫定政府の権限の延長は行わず、全土を代表する統一政府への移行を実現することで合意しています。
これについては、“「改革へ努力しないと国際社会は手を切る」(日本政府関係者)という暫定政府への通告、との見方もある”【2月25日 朝日】とのことです。
状況は、イスラム武装組織シャバブが首都モガディシオから撤退し、アフリカ連合(AU)平和維持部隊によってモガディシオの大統領府周辺のみがかろうじて守られていた頃に比較すると、若干は改善しています。
ただ、シャバブはソマリア中南部で依然広く影響力を保っており、首都モガディシオにおいても爆弾テロが繰り返されています。
国会議員選出の選挙も行えない状況ですが、とにもかくにも、ソマリアは正式政府発足を目指すことになります。
****ソマリア、希望の一歩 内戦21年、正式政府が発足へ****
21年間にわたって内戦が続き、無政府状態のソマリアで正式政府発足に向けた動きが活発化している。20日に暫定政府の期限が切れるのを前に国会議員の選定など国の形作りが大詰めを迎えている。新政府の成否は、近海の海賊問題の解決やテロ組織の温床化阻止など世界の安全保障にも関わる。
■国会議員の選定進む
8月上旬、首都モガディシオの集会場で、氏族に分かれた血縁集団の各長老が国会議員のリストを持ち寄っていた。議員275人は長老の推薦で決まる。首都などを除き、中南部で広範囲に実効支配するイスラム武装勢力シャバブとの戦闘が続いており、全国での選挙が行えないためだ。
議員の選定規定は学歴などのほか、女性を3分の1にするとある。長老の一人バシルさん(66)は「女性の社会参加はいいことだ。厳選している」と話す。だが選定で長老とのコネや脅し、買収の横行も指摘されており、難航している。
新大統領は議員選定の後に議員の投票で選ばれる。新大統領の下で20日の正式政府発足を目指しているが、議員選定の利害対立で行程がずれ込んでいる。
大統領候補は約50人。大半が欧米などから戻った人々だという。街には大統領候補の陣営が「政治腐敗と戦う」「農漁業の振興を」などと投票を訴えて回る選挙カーの姿も見られた。
一方、新政府発足を巡り、関連会議を狙った自爆テロも発生した。12日には議員選定を取材した記者ら2人が殺害された。シャバブの犯行とみられる。
無政府状態とシャバブの存在は、アデン湾など近海での海賊の隆盛を許した。年間約1万8千隻の商船が航行する海の要所が危険にさらされている。日本の自衛隊や世界各国の海軍が広大な海上で警戒するが、海賊の拠点がある陸地での対策がほぼ手つかずできた。
北西部のソマリランドが91年に一方的に独立を宣言、北東部のプントランドも98年に自治を宣言している。プントランドは新政府に参加する意向だが、ソマリランドは難色を示し、分離する可能性もある。
暫定政府のアフメド大統領は取材に「全土の結束が必要だ。中央政府ができ、秩序を取り戻せばシャバブや海賊が存在できる場所がなくなる」と話した。
■残骸残る海、笑顔戻る
新政府誕生を前に街の雰囲気は変わりつつある。
モガディシオ郊外にあるリドビーチ。白い砂浜とエメラルドグリーンの海が広がる。週末の午前、地元の親子連れや若者ら数百人が海水浴を楽しんでいた。色とりどりの服を着た女性も目立つ。20年以上見られなかった光景だ。内戦で人々は海岸に近寄れなかった。
周辺はかつてホテルやレストランが立ち並び、ヨーロッパ人観光客であふれる国内最大の観光地だった。今、石造りの建物は破壊され、古代遺跡のような残骸をさらしている。カラフルな看板だけが面影を残す。
一帯はシャバブの根城になっていた。
シャバブは自由な服装、海水浴、魚釣りなどを禁じた。違反者は打ち首になった。近くに住む中学生アウィエスさん(20)は、漁に出た漁師が処刑されるのを見た。「恐怖の中に住んでいた。誰も海に近づこうとしなかった」という。自身も学校に行けなくなった。
漁師のアブディさん(30)は半年前に漁を再開した。「ロブスターやサワラ。海には何でもいる」と笑う。以前は常に家の中で過ごし、援助の食糧が来るのを待った。「海があるのに食べ物に困った。馬鹿げていた」
アフリカ連合(AU)軍がシャバブとの戦闘の末にこの地域を奪取したのは昨年8月。ここ数カ月で人々が戻ってきた。ただ、シャバブの脅威は消えていない。治安部隊の装甲車が警戒にあたる中、外国人の姿は皆無だ。
AU軍の掃討作戦にもかかわらず、シャバブはソマリア中南部で広く影響力を保ったままだ。街を去ってもゲリラ的に自爆テロを繰り返している。
アブディさんは、新政府に期待する。「街を再建し、外国人が来られる国にして欲しい」と話した。
■「教育は紛争防ぐ手段」
内戦にたびたび妨げられていた学校教育は一部で元に戻りつつある。
モガディシオ南部のブスタレ小中等学校は激戦で閉鎖を余儀なくされた。シャバブの撤退により昨年11月に再開にこぎ着け、約250人が学んでいる。
多くの子どもがシャバブによってかり出され、約50人は戦闘に加わったとみられる。教員のジャワヒールさん(45)は「子どもは心に傷を負っている。シャバブに言及することは避けている」と話した。
中心街にあるイムラ小中等学校は、AU軍とシャバブが激しく交戦する地域にあった。生徒のアブディさん(18)は「授業中にいきなり戦闘が始まった。通学も銃撃の間を縫うことがあった」と話す。学校がシャバブの基地として使われた時期もあった。AU軍が学校を攻撃しないと見て入り込み、学校から攻撃した。
別の学校の教員フセインさん(45)は、平和を訴える教材を持っていたところ、シャバブの戦闘員に銃を突きつけられ尋問されたことがある。「聖戦はすばらしいと教えるように言われた。人権なんて存在しなかった」と話した。
暫定政府教育省のムーサ局長は「長年、統一された教育がなかった。教育は紛争を防ぐ手段だ。無知が一番恐ろしい」という。
教員養成機関もなければ、学校も足りない。「国民の85%が読み書きができない。国際社会は戦闘だけでなく、教育にも関心を持って欲しい」と話した。【8月19日 朝日】
********************
モガディシオ郊外のビーチで“週末の午前、地元の親子連れや若者ら数百人が海水浴を楽しんでいた。色とりどりの服を着た女性も目立つ”・・・というのは、これまでのソマリアのイメージからすると、意外な感もありました。
以前のブログでやや懐疑的に取り上げた“(モガディシオのビーチが)「立入危険区域」から「見逃せない観光スポット」に生まれ変わった”“ソマリア政府の広報担当者アブディラマン・オマール・オスマンは楽観的だ。今のモガディシュは、イラクのバグダッドやアフガニスタンのカブールよりは安全になったし、観光客誘致のため観光大臣も任命するかもしれないという。”【6月14日 Newsweek】という“ソマリア・リゾート”も、あながち嘘ではないのかも。
【正式政府発足は遅れる見通し】
正式政府に向けて、8月1日には暫定憲法案が採択されましたが、会議場近くでは自爆テロも起きています。
****国連、ソマリア暫定憲法案の採択を歓迎****
パン・ギムン国連事務総長は1日声明を発表し、同日、ソマリア全国憲法制定会議で暫定憲法案が採択されたことに歓迎の意を表明すると共に、会場近くで発生した自爆テロを強く非難しました。
憲法制定会議は1日、暫定憲法案について投票を行い、圧倒的多数で承認しました。しかし、投票が始まる前、会場入り口付近で、自爆テロが2回発生し、警察官2名が負傷しています。【8月2日 China Radio Internatinal】
*******************
結局、国会議員・新大統領の選出は、期限切れの20日には間に合いませんでした。
各氏族に分断され対立を繰り返すソマリア社会、これまでの経緯を考えると、正式政府発足まではひと山もふた山もありそうに思えます。
****ソマリア暫定統治期限が終了…政府発足は遅れる****
1991年から内戦状態が続くソマリアで20日、2004年に発足した暫定政府の統治期限が終了した。
当初の予定では、同日までに各部族によって選ばれた国会議員275人が大統領を選出することになっていたが、AP通信によると、汚職疑惑などで国会議員選出が遅れており、新大統領選出も遅れる見通しだ。
事実上の無政府状態が続くソマリアは海賊やイスラム武装勢力の一大拠点となっている。8月1日には、暫定憲法が採択されるなど正式政府発足に向けた進展もあり、国連やアフリカ連合などは「国際社会はこれまでの重要な進展を歓迎する」とする共同声明を19日に発表した。
新大統領候補としては、暫定政府のアハメド大統領やアリ首相、暫定議会のアデン議長らの名前が挙がっている。【8月20日 読売】
*********************
“議員275人は長老の推薦で決まる”とのことですから、コネ・脅し・買収が横行するのはやむを得ないところですが、正式政府発足前からこんな状況で大丈夫だろうか・・・という不安も感じます。
【武装した海外の民間警備会社の警備員が日本船籍に乗船】
なお、日本はソマリア沖で行っている海賊対策を1年延長して続行しています。
****海自:海賊対策活動を1年延長****
政府は13日午前の安全保障会議と閣議で、23日に期限が切れるアフリカ東部ソマリア沖・アデン湾での海上自衛隊の海賊対策活動を1年間延長することを決定した。森本敏防衛相は記者会見で「海賊事案は昨年より減少しているが引き続き予断を許さない状況だ」と延長理由を述べた。
自衛隊の活動拠点がある隣国ジブチに各国部隊などと活動を調整する現地調整所を新設し、自衛官3人を配置。上空から警戒監視に当たるP3C哨戒機2機、民間船舶を警護する護衛艦2隻の態勢は維持する。
ソマリア沖での海賊対策活動は09年3月、自衛隊法に基づき海上警備行動として開始。同年7月からは根拠法を海賊対処法に切り替えて継続している。同法に基づく活動延長は3回目。【7月13日 毎日】
*********************
しかし、海賊の活動範囲を自衛隊だけでカバーするのは困難なため、武装した海外の民間警備会社の警備員が日本船籍に乗船できるよう法整備を行う方向で検討がなされています。
****ソマリア沖:海賊対策に民間警備員 政府が法整備検討****
政府はアフリカ・ソマリア沖や周辺海域での海賊対策を強化するため、武装した海外の民間警備会社の警備員が日本船籍に乗船できるよう法整備を行う方向で検討に入った。
現在は海賊対処法に基づき、海上自衛隊がソマリア沖のアデン湾に護衛艦などを派遣して民間船舶を護衛している。しかし、海賊行為の発生地域がアラビア海からインド洋まで広がり、自衛隊だけでは対処できないと判断。来年の通常国会への関連法案提出を目指している。(後略)【8月14日 毎日】
*********************