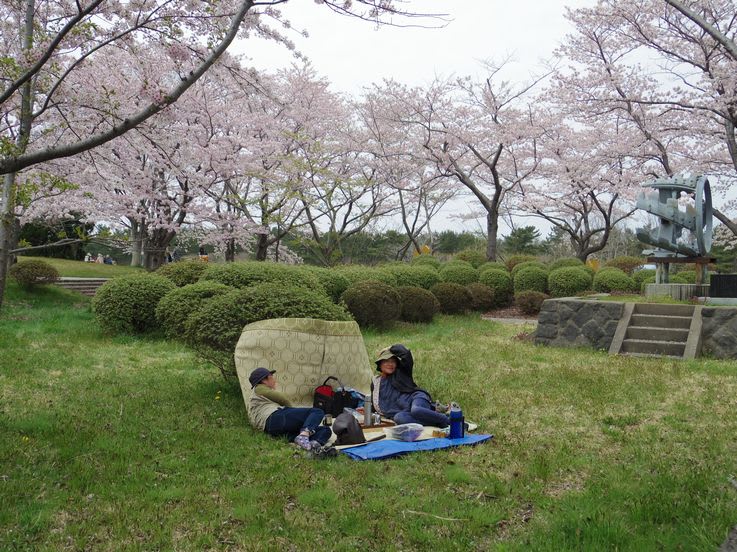40代以上の人で、日本で「エマニエル夫人」を知らない人はいないでしょう。興業収入でゴッドファーザーⅡと007を2倍近く離して、15億6千万を稼いだ名作です。名作?そう。ヒットするからには理由があるのです。
当時街角のポスターに女性の裸が貼られるなんて、あり得なかった時代です。それなのに映画館の前に並んだのは、若い女性。女性が堂々と見られるポルノ映画。それが「エマニエル夫人」だったのです。

映像はあくまで美しく、自然光の逆光で捉えた官能的なショットが多く使われ、原作のイメージだけを伝えるよう工夫されました。
視点の1はプロデューサーのイヴ・ルーセ=ルアール。CM制作が専門だった彼は飛行機の機内で恋人がじゃれ合うシーンを思い浮かべました。それが発端です。こういうのを人々は見たいんじゃないか。同じく映画製作の経験はないが、女性の美しさを見抜く目なら自信のあったカメラマン、ジュスト・ジャガン。そしてオーディションで見つけた、オランダ出身のシルビア・クリステル。原作ではグラマーなアジア人だったのが、女性が見て美しいと思う、細身だがぜい肉の無い裸体。全編を通じて女性目線のソフトなタッチを決めた撮影監督リシャール・スズキ。

こうやって目指す映画は完成しましたが、当時の大統領は超保守派で有名なポンピドー。上映は禁止する。政治家たちには単なるポルノにしか映りませんでした。1974年5月。若いジスカール・デスタン大統領が就任すると状況は一変しました。表現の自由を訴え、検閲を廃止すると発表しました。ぎりぎり夏のバカンス前の6月、公開が許可されました。この論争があったおかげで、人々は映画館に足を運びました。インテリ批評家たちの、くだらない映画だとの論評もなんのその。1年間で400万人以上の観客動員を達成しました。

しかし日本ではこれは流行らないだろうと、映画関係者の誰もが考えていました。ただ一人、博打好きの宣伝マン山下健一郎だけは違いました。フランスで公開された時のポスターは、なんとも地味な絵でした。

これを例の籐椅子の大胆な裸に変えたのが彼です。この写真は著名な写真家によるもので、当時100万円したそうです。フィルムの貸付料が同じく100万円でしたから、いかに無謀なチャレンジだったか分かろうというものです。しかしご存じのとおり、この椅子のインパクトは絶大で、おかげで日本では女性まで含めて関心を呼びました。

シルビア・クリステルは1952年生まれで、だいたい私と同じ年代です。彼女は晩年ガンを患い、脳卒中で2012年他界しました。あのヒットのあと、ハリウッドに移り何本か主演したようですが、鳴かず飛ばずの成績でした。元々女優の素質は無かったのです。フランス語も流暢に話せない彼女を、吹き替えを使ってまで仕上げたエマニエル夫人こそ、彼女の成長過程そのものであり、しかしそれは彼女自身の私生活とはかけ離れたものでした。亡くなる数年前、一般人に混じって地下鉄に乗る彼女には、スターの面影はありませんでした。

最後の4年を過ごしたアムステルダムのボート小屋。介護施設で働くピーターと一緒でした。「いつもここに座って、絵を描いていたよ。」

彼女が生きた2つの人生。捨てたかったのは、どちらの人生だったのか。
親に捨てられ、長女として生活のために選んだ女優の道。片やCM広告収入では生計が立てられず、一発逆転を狙ったプロデューサー。案外そんなところから、映画のストーリーは始まったりするものです。