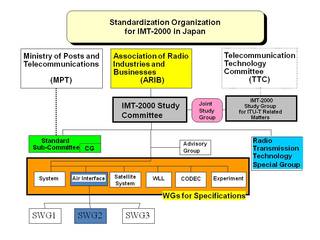1998年末に、ヨーロッパ、日本、アメリカ、韓国が集まって第3世代移動通信の標準化を行う組織3GPPが設立された。参加資格はそれぞれの地域標準化団体にメンバー登録している企業である。それぞれETSI(欧州)、ARIB(日本)TTC(日本)、ATIS(US)、TTA(韓国)となっている。これらの5団体が集まって議論をするが具体的な技術論は個別企業間で行う。当初から私は日本だけ2団体になっていることに違和感を持っていたが、この状態は今でも続いている。1年後に中国のCCSAが加入して現在は6団体での運営になっている。
3GPPは現在では世界の移動体通信の標準を牛耳る大変重要な団体であるが、この団体は任意団体で法律的には存在しない事になっている。つまり会費を集めたりすることはできない団体である。会費集めや事務局職員の派遣、ホームページの作成や、仕様書のメンテナンス、広報活動などは最大の参加母体であるETSIが扱っており、他のメンバーに図って意思決定をしている。ルールも大部分がETSIで使っていたルールが採用された。
こうして、WCDMAの標準化を行う3GPPが結成され1999年に入って実際の活動が始まった。この頃から私に無線グループの初代議長をやらないか、という話が下りてきた。3GPPの組織は無線ネットワーク、コアネットワーク、サービス、端末をそれぞれ審議する4グループが構成され、それぞれのグループの下にいくつかのワーキンググループが構成されて、技術仕様書を作成する。しかし、承認はすべて親会議で行う、という構造になっている。無線グループの扱う範囲はそれまで日本で私が議長をしていたグループよりもはるかに広く、無線伝送方式だけでなく、プロトコル、基地局間の連携などを含むものだった。
私自身は無線伝送方式の方に興味があったのでワーキンググループの方をやりたいと思っていたが、日本勢として親会議の議長を取る事も政府へのアピールなどで重要ということで、無線伝送方式のワーキンググループの仮議長を少しやってから親会議の議長に立候補することにした。3GPPでは2回会議に出席しないと投票権ができないというルールにしており、第1回目は議長選挙をすることができない。第2回目の親会議は1999年3月と決まっていたので、それまでの間、無線伝送方式のワーキンググループの仮議長をすることにしたのである。
第1回目の仮議長のワーキンググループは私にとって悲惨なものだったが、お陰で多くの事を学び、本議長に対する準備をすることができた。