万葉雑記 色眼鏡 百五一 仙柘枝歌と柘枝舞
今回もまた、ひどく脱線をします。まず、まともな万葉集の鑑賞ではありませんの、そこのところは、よろしく、お願いいたします。
さて、万葉集巻三に次のような歌があります。この集歌385の歌の標題と左注から「柘枝傳」と云う書物が注目を浴びています。
仙柘枝謌三首
標訓 仙(やまひと)柘枝(つみのえ)の謌三首
集歌385 霰零 吉美我高嶺乎 險跡 草取可奈和 妹手乎取
訓読 霰降り吉美(よしみ)が岳(たけ)を険(さが)しみと草(かや)取りかなわ妹し手を取る
私訳 霰が降り、「吉美が岳(よしみがたけ)」、その言葉に似た響きの「さがしみ(=険しい)」からとその山で草を刈ることが出来ないが、代わりに貴女の手を抱き取った。
右一首。或云、吉野人味稲与柘枝媛謌也。但、見柘枝傳無有此謌
注訓 右は一首。或は云はく「吉野の人味稲(うましね)の柘枝媛(つみのえひめ)に与へし謌なり」といへる。但し、柘枝傳(つみのえでん)を見るに、此の謌有ることなし。
集歌386 此暮 柘之左枝乃 流来者 楔者不打而 不取香聞将有
訓読 この暮(ゆふべ)柘(つみ)しさ枝の流れ来(こ)ば梁(やな)は打たずに取らずかもあらむ
私訳 この夕暮れに柘の小枝が流れ来たら、川に梁を張ることなく、その小枝を取らないでいるでしょうか。(やはり拾い上げるでしょう)
右一首
注訓 右は一首
集歌387 古尓 楔打人乃 無有世伐 此間毛有益 柘之枝羽裳
訓読 古(いにしへ)に梁(やな)打つ人の無かりせば此処(ここ)もあらまし柘(つみ)し枝(えだ)はも
私訳 昔、川に梁を張る人が居なかったら、今でもここにあるでしょう、柘の枝は。
右一首、若宮年魚麿作
注訓 右は一首、若宮年魚麿(あゆまろ)の作れり
集歌385の歌に付けられた左注は、弊ブログでの推定では紀貫之の時代ごろに付けられたと考えています。まず、「但、見柘枝傳無有此謌」と云う文章からしますと原万葉集の載る歌々が詠われた時代ではありませんし、原万葉集の第二次編纂時期となる天平勝宝年間でもないと考えます。もう少し、後の時代での左注です、同時代性はありません。
では、文中のその『柘枝傳』はどのようなものであったかと云うと一切が不明のものです。そのため、『懐風藻』や『風土記』の記事から次のように内容を推定するようです。
漁師の味稲(うましね)(美稲あるいは熊志祢とも)が吉野川に梁を仕掛けて漁をしていた。そこへ柘(つみ)の枝(え)が流れて来て梁にかかり、仙女と化した。二人は結婚するが、譴めを蒙って山野に逃げ、二人は手を取り合って険しい岳を登る。最後には領巾衣(ひれころも)を着て飛び去る。
その推定される柘枝傳の主人公は川を流れ来た柘枝が梁にかかって女と化した仙人であり、その仙女を『懐風藻』に載る藤原史の漢詩などを下に「柘媛」と呼ぶようです。そうしたとき、その「柘枝傳」の「柘枝」と云う言葉から、古く、大唐での「柘枝舞」との関連を探っています。今日の日本では奈良時代には存在したであろう「柘枝傳」を探ることは困難ですが、「柘枝舞」については中国に残る賦や漢詩などからおよその姿が示されています。
まず、中唐時代となりますが、盧肇(818-882)が『湖南觀雙柘枝舞賦』と云う作品を為しており、その賦から「柘枝舞」は「古也郅支之伎、今也柘枝之名」と示され、もともとは西域胡族の男性が踊る舞踏の一つであったとします。それらの胡族の舞踏などの歌舞が北方民族国家である隋や唐の成立から中国中原に紹介され「健舞(現在では漢族舞踏に分類)」と称されます。ここで、「郅支」と云う地域や胡族のある部族長の名前であったものが唐時代にはその地域の中心地の名前に由来して「柘枝」と表記されるようになり、舞踏の名もまた「郅支之伎」から「柘枝舞」へと移り変わりました。ただし、ここまでは面白くもおかしくもありません。その時の「柘枝舞」は、胡族の服装を着た男性による胡の楽奏に乗った「胡旋舞」とも称される片足を軸に旋回して踊るものですし、剣の舞です。単なる異国情緒のある男舞です。今日ですと同類のものとして、トルコの「セマー」と云う旋舞が有名で、インターネットから簡単に鑑賞することが出来ます。
ところがところが、唐初の時代、大変化が起きます。
その「胡旋舞」の一つである「柘枝舞」を、胡服を着た女性が踊るようになります。それも胡服の中でも軍装を女性が着て踊ります。それまでの時代の、うら若き宮中の舞踊を専門にするような女性の装いの中に、男装、益して、軍装を身に纏うというようなファッションは有りませんでした。歴史で初めての場面としての男装した女性の登場です。それまでは宮中の舞踊を専門にするような女性のファッションは薄物の衣に胸高にスカートを着た、いかにも柔らかでふんわりとした、それでいて体の線を隠すような姿が基本です。それが体の線も明らかになる軍装の男装ファッションでの登場です。さらに、半袖の丈の短いボレロのような上着を衣の上に身に着ける男装胡服を女性が纏います。軍装ですが、上半身が下着となる胸当てとボレロのような上着だけであるがために踊りの最中にボレロのような上着の紐が緩めば胸元の素肌があらわになるというアンバランスな装いなのです。そして、唐から宋の時代にはこのファッションが大流行し、「柘枝舞」と云う舞踏は男装の美女集団による集団舞踏へと発展していきます。(日本ですと、男踊りがベースのある種のよさこい踊りのような雰囲気でしょうか) 「柘枝舞」とはそのような歴史を持つ、ファッション革命をも伴った舞踏なのですし、場合によっては性的嗜好の変化も伴うものなのです。一説には楊貴妃も「胡旋舞」の名手であったと云いますから、時に宝塚歌劇団の男役トップスター以上の雰囲気を持つ人であったかもしれません。さらに、ご存知のように楊貴妃は「私、脱げばもっとすごいんです」と云う女性々々した人でもありました。唐時代とはそのような嗜好の時代であったようです。
さて、唐初の時代には大流行をしたと云うこの「柘枝舞」を無視して、日本の「柘枝傳」が単独に成立したでしょうか。弊ブログの立場からしますと、疑問です。
則天武后に大歓迎されたという粟田真人を大使とする第七次遣唐使の帰国が慶雲元年(704)です。天平勝宝四年(752)の東大寺開眼法要では「唐女舞(施袴二十人)」と云う隊舞が披露されていますから、ほぼ、この時代以前に大唐で大流行した「胡旋舞」が到来していたことは確かでしょう。従いまして「柘枝舞」を無視して日本の「柘枝傳」を探るのは困難ではないでしょうか。
すると、『湖南觀雙柘枝舞賦』を中心に「柘枝傳」を探るのが正しい方向かもしれません。例えば『懐風藻』に藤原史が詠う吉野に遊ぶという作品がありますが、旧来、「柘媛接魚通」の句から「柘枝傳」の関連を探っています。一方、『湖南觀雙柘枝舞賦』には「何彼妹之婉孌、媚戎服之豪侠。司樂以魚符發詠、侍兒以蘭膏薦潔」と云う一節がありますから、漢詩を作詞するときは先行する詩や賦などの中国古典を引用するルールからしますと、盧肇が参照したものと同じような「柘枝舞」に関する中国古典を引用した可能性はあります。ここで「魚符」とは通行許可書のような割符です。従って、「柘媛接魚通」は「柘媛は通行許可書を与えられて男の許に通う」とも解釈すべき内容の句です。
ただし、藤原史の漢詩には彼独特の作風があり、その「漆姫控鶴舉」の一節は場合により中国古典の「神仙故事 控鶴仙人」か、「漆」を同音字である「謀」の隠し字として則天武后の「控鶴府」を暗示する可能性もありますが、古典文学の専門家が指摘するように日本民話を彼流に漢字文字「漆姫」と云う風にアレンジしたのではないかと云う疑いもあります。そのため、藤原史のものを、中国古典を参照し、また、内容や題詞を下に歴史資料として使うのは難しい面があります。ただ、『懐風藻』の研究家の指摘とは違いますが、個人的には「漆姫控鶴舉」の一節は「謀姫である則天武后は男妾のために控鶴府を創った」と訳するが面白いと思うのですが。
なお参考として中国古典では「乗鶴仙人」と云う神話があるように、古典一般には鶴は仙女のシンボルであり、仙人や仙人となった男を天上の仙人界へと運ぶ役目を果たします。後、この「乗鶴仙人」の説話が日本に入って、いつしか、仙女もまた鶴に乗るようになりました。なお、黄鶴楼が遊郭を示すように、古典において鶴が男性を体の上に乗せる美人のシンボルであるなら「控鶴舉」とは「隊舞」の美人を意味しているのかもしれません。
<懐風藻 藤原史>
五言 遊吉野 二首 吉野に遊ぶ
飛文山水地 文を飛ばす山水の地
命爵薜蘿中 爵を命ずる薜蘿の中
漆姫控鶴舉 漆姫 鶴を控きて舉り
柘媛接魚通 柘媛 魚に接して通ず
煙光巖上翠 煙光 巖上に翠
日影漘前紅 日影 漘前に紅
翻知玄圃近 翻つて知る 玄圃の近きを
對翫入松風 對して翫す 松に入る風を
こうした時、日本の「柘枝の話」が気になります。「柘枝の話」では神の領域の川上から流れて来た「柘の枝」が美人となります。また、最後の昇天では羽衣や領巾によって行われますから、背景には羽衣伝説の変形があるのかもしれません。
平安時代末期から鎌倉時代に仏教では九想観と云うものが流行し、この流行の下、檀林皇后や小野小町などの九想観図が作られました。この九想観図は絶世の美女が死、仏教徒として野に捨てられると、やがて体は獣に食われ、虫にたかられ最後には白骨になるという場面を順に描くもので、差し障りの無いところの「絶世の美女=小野小町」と云うことで彼女の名前が借用されました。それと同じように異国や異郷からの美人と云うことで「柘媛」という名前が借用された可能性もあるのではないでしょうか。万葉時代では大和の美人の代表として「石川郎女」と云う名前を与えていますから、一概に無視はできないと考えます。
ただ一方、「柘」と云う漢字は現代では「やまくわ」、「つげ」ですし、『説文解字』では「桑」や「甘蔗」を意味すると云います。すると、奈良時代には甘い果実を付ける「やまくは=山桑」に対して「柘」と云う文字を与えていた可能性を否定できません。
こうした時、「山桑」は非常に有用な高木樹です。その樹皮は黄色系の染料となり、樹木自体は堅く木目の美しさから高級家具や将棋・呉盤の材料となります。また、果実は甘く食用になりますし、根皮は漢方薬の桑白皮(そうはくび)と呼ばれるもので利尿やせき止めなどの効用を持つ生薬として服用します。さらに繊維は強靭なので和紙に混用されるとします。このように古代では代表的な恵みの樹木なのです。それを「山の恵み=山の媛」として、この樹木に敬意を示したかもしれません。なお、養蚕に使う「くは」は中国から朝鮮半島に繁殖し輸入植物である「桑」であって、漢字では「桑」と記しますが、国内で古から繁殖する「やまくわ」とは違う植物です。そのため、「やまくわ」の漢字表記は「柘」であり「山桑」です。
そうしますと、歌の標題「仙柘枝謌三首」と歌中の「柘之左枝」とが同じものを示しているのかが問題となります。ご存知のように万葉集での標題のつけようからしますと、歌と標題が一致することは必ずしも保証されません。歌が先に詠われ、後に万葉集の編纂に合わせて編集者の判断で標題を与えた可能性があります。そうしますと、平安時代後期以降では『湖南觀雙柘枝舞賦』や「遊吉野(藤原史)」などの漢詩文作品群から「仙柘枝」は仙女をイメージして「やまひと、つみのえ」と訓じますが、本来ですと「やまひと、くわのえ」と訓じるべきなのかもしれません。
例えば、集歌385の歌では左注の「右一首或云、吉野人味稲与柘枝媛謌也」の文章でもって「柘枝媛」との関連を示唆しますが、歌自体には柘枝媛は詠われていません。「妹手」として、恋歌の中で年頃の女性を示唆するだけです。さらに集歌386の歌では「柘之左枝」ですし、集歌387の歌でも「柘之枝」だけです。直接の鑑賞からしますと「山桑の枝」であっても良いのですから、歌自体には「柘枝媛」の姿はないのです。ただ、比喩として受け止められるだけです。
実に不思議です。
時に、万葉集の編集者はこれら、全て、承知の上で標題「仙柘枝謌三首」を付けたのかもしれません。「遊吉野(藤原史)」が遅く大宝二年(702)の作品としましても藤原史は「柘枝舞」のようなものを知らない可能性があります。およそ、第七次遣唐使の帰国が慶雲元年(704)以前の作品では「仙柘枝謌」を「やまひと、つみのえ」として歌を詠うかと云うことです。やはり、編集者は遊びとして後年に「やまひと、くはのえ」と「やまひと、つみのえ」との二通りに読ませるつもりだったのかもしれません。ちゃんと判っているよねって。
今回もまた、ひどく脱線をします。まず、まともな万葉集の鑑賞ではありませんの、そこのところは、よろしく、お願いいたします。
さて、万葉集巻三に次のような歌があります。この集歌385の歌の標題と左注から「柘枝傳」と云う書物が注目を浴びています。
仙柘枝謌三首
標訓 仙(やまひと)柘枝(つみのえ)の謌三首
集歌385 霰零 吉美我高嶺乎 險跡 草取可奈和 妹手乎取
訓読 霰降り吉美(よしみ)が岳(たけ)を険(さが)しみと草(かや)取りかなわ妹し手を取る
私訳 霰が降り、「吉美が岳(よしみがたけ)」、その言葉に似た響きの「さがしみ(=険しい)」からとその山で草を刈ることが出来ないが、代わりに貴女の手を抱き取った。
右一首。或云、吉野人味稲与柘枝媛謌也。但、見柘枝傳無有此謌
注訓 右は一首。或は云はく「吉野の人味稲(うましね)の柘枝媛(つみのえひめ)に与へし謌なり」といへる。但し、柘枝傳(つみのえでん)を見るに、此の謌有ることなし。
集歌386 此暮 柘之左枝乃 流来者 楔者不打而 不取香聞将有
訓読 この暮(ゆふべ)柘(つみ)しさ枝の流れ来(こ)ば梁(やな)は打たずに取らずかもあらむ
私訳 この夕暮れに柘の小枝が流れ来たら、川に梁を張ることなく、その小枝を取らないでいるでしょうか。(やはり拾い上げるでしょう)
右一首
注訓 右は一首
集歌387 古尓 楔打人乃 無有世伐 此間毛有益 柘之枝羽裳
訓読 古(いにしへ)に梁(やな)打つ人の無かりせば此処(ここ)もあらまし柘(つみ)し枝(えだ)はも
私訳 昔、川に梁を張る人が居なかったら、今でもここにあるでしょう、柘の枝は。
右一首、若宮年魚麿作
注訓 右は一首、若宮年魚麿(あゆまろ)の作れり
集歌385の歌に付けられた左注は、弊ブログでの推定では紀貫之の時代ごろに付けられたと考えています。まず、「但、見柘枝傳無有此謌」と云う文章からしますと原万葉集の載る歌々が詠われた時代ではありませんし、原万葉集の第二次編纂時期となる天平勝宝年間でもないと考えます。もう少し、後の時代での左注です、同時代性はありません。
では、文中のその『柘枝傳』はどのようなものであったかと云うと一切が不明のものです。そのため、『懐風藻』や『風土記』の記事から次のように内容を推定するようです。
漁師の味稲(うましね)(美稲あるいは熊志祢とも)が吉野川に梁を仕掛けて漁をしていた。そこへ柘(つみ)の枝(え)が流れて来て梁にかかり、仙女と化した。二人は結婚するが、譴めを蒙って山野に逃げ、二人は手を取り合って険しい岳を登る。最後には領巾衣(ひれころも)を着て飛び去る。
その推定される柘枝傳の主人公は川を流れ来た柘枝が梁にかかって女と化した仙人であり、その仙女を『懐風藻』に載る藤原史の漢詩などを下に「柘媛」と呼ぶようです。そうしたとき、その「柘枝傳」の「柘枝」と云う言葉から、古く、大唐での「柘枝舞」との関連を探っています。今日の日本では奈良時代には存在したであろう「柘枝傳」を探ることは困難ですが、「柘枝舞」については中国に残る賦や漢詩などからおよその姿が示されています。
まず、中唐時代となりますが、盧肇(818-882)が『湖南觀雙柘枝舞賦』と云う作品を為しており、その賦から「柘枝舞」は「古也郅支之伎、今也柘枝之名」と示され、もともとは西域胡族の男性が踊る舞踏の一つであったとします。それらの胡族の舞踏などの歌舞が北方民族国家である隋や唐の成立から中国中原に紹介され「健舞(現在では漢族舞踏に分類)」と称されます。ここで、「郅支」と云う地域や胡族のある部族長の名前であったものが唐時代にはその地域の中心地の名前に由来して「柘枝」と表記されるようになり、舞踏の名もまた「郅支之伎」から「柘枝舞」へと移り変わりました。ただし、ここまでは面白くもおかしくもありません。その時の「柘枝舞」は、胡族の服装を着た男性による胡の楽奏に乗った「胡旋舞」とも称される片足を軸に旋回して踊るものですし、剣の舞です。単なる異国情緒のある男舞です。今日ですと同類のものとして、トルコの「セマー」と云う旋舞が有名で、インターネットから簡単に鑑賞することが出来ます。
ところがところが、唐初の時代、大変化が起きます。
その「胡旋舞」の一つである「柘枝舞」を、胡服を着た女性が踊るようになります。それも胡服の中でも軍装を女性が着て踊ります。それまでの時代の、うら若き宮中の舞踊を専門にするような女性の装いの中に、男装、益して、軍装を身に纏うというようなファッションは有りませんでした。歴史で初めての場面としての男装した女性の登場です。それまでは宮中の舞踊を専門にするような女性のファッションは薄物の衣に胸高にスカートを着た、いかにも柔らかでふんわりとした、それでいて体の線を隠すような姿が基本です。それが体の線も明らかになる軍装の男装ファッションでの登場です。さらに、半袖の丈の短いボレロのような上着を衣の上に身に着ける男装胡服を女性が纏います。軍装ですが、上半身が下着となる胸当てとボレロのような上着だけであるがために踊りの最中にボレロのような上着の紐が緩めば胸元の素肌があらわになるというアンバランスな装いなのです。そして、唐から宋の時代にはこのファッションが大流行し、「柘枝舞」と云う舞踏は男装の美女集団による集団舞踏へと発展していきます。(日本ですと、男踊りがベースのある種のよさこい踊りのような雰囲気でしょうか) 「柘枝舞」とはそのような歴史を持つ、ファッション革命をも伴った舞踏なのですし、場合によっては性的嗜好の変化も伴うものなのです。一説には楊貴妃も「胡旋舞」の名手であったと云いますから、時に宝塚歌劇団の男役トップスター以上の雰囲気を持つ人であったかもしれません。さらに、ご存知のように楊貴妃は「私、脱げばもっとすごいんです」と云う女性々々した人でもありました。唐時代とはそのような嗜好の時代であったようです。
さて、唐初の時代には大流行をしたと云うこの「柘枝舞」を無視して、日本の「柘枝傳」が単独に成立したでしょうか。弊ブログの立場からしますと、疑問です。
則天武后に大歓迎されたという粟田真人を大使とする第七次遣唐使の帰国が慶雲元年(704)です。天平勝宝四年(752)の東大寺開眼法要では「唐女舞(施袴二十人)」と云う隊舞が披露されていますから、ほぼ、この時代以前に大唐で大流行した「胡旋舞」が到来していたことは確かでしょう。従いまして「柘枝舞」を無視して日本の「柘枝傳」を探るのは困難ではないでしょうか。
すると、『湖南觀雙柘枝舞賦』を中心に「柘枝傳」を探るのが正しい方向かもしれません。例えば『懐風藻』に藤原史が詠う吉野に遊ぶという作品がありますが、旧来、「柘媛接魚通」の句から「柘枝傳」の関連を探っています。一方、『湖南觀雙柘枝舞賦』には「何彼妹之婉孌、媚戎服之豪侠。司樂以魚符發詠、侍兒以蘭膏薦潔」と云う一節がありますから、漢詩を作詞するときは先行する詩や賦などの中国古典を引用するルールからしますと、盧肇が参照したものと同じような「柘枝舞」に関する中国古典を引用した可能性はあります。ここで「魚符」とは通行許可書のような割符です。従って、「柘媛接魚通」は「柘媛は通行許可書を与えられて男の許に通う」とも解釈すべき内容の句です。
ただし、藤原史の漢詩には彼独特の作風があり、その「漆姫控鶴舉」の一節は場合により中国古典の「神仙故事 控鶴仙人」か、「漆」を同音字である「謀」の隠し字として則天武后の「控鶴府」を暗示する可能性もありますが、古典文学の専門家が指摘するように日本民話を彼流に漢字文字「漆姫」と云う風にアレンジしたのではないかと云う疑いもあります。そのため、藤原史のものを、中国古典を参照し、また、内容や題詞を下に歴史資料として使うのは難しい面があります。ただ、『懐風藻』の研究家の指摘とは違いますが、個人的には「漆姫控鶴舉」の一節は「謀姫である則天武后は男妾のために控鶴府を創った」と訳するが面白いと思うのですが。
なお参考として中国古典では「乗鶴仙人」と云う神話があるように、古典一般には鶴は仙女のシンボルであり、仙人や仙人となった男を天上の仙人界へと運ぶ役目を果たします。後、この「乗鶴仙人」の説話が日本に入って、いつしか、仙女もまた鶴に乗るようになりました。なお、黄鶴楼が遊郭を示すように、古典において鶴が男性を体の上に乗せる美人のシンボルであるなら「控鶴舉」とは「隊舞」の美人を意味しているのかもしれません。
<懐風藻 藤原史>
五言 遊吉野 二首 吉野に遊ぶ
飛文山水地 文を飛ばす山水の地
命爵薜蘿中 爵を命ずる薜蘿の中
漆姫控鶴舉 漆姫 鶴を控きて舉り
柘媛接魚通 柘媛 魚に接して通ず
煙光巖上翠 煙光 巖上に翠
日影漘前紅 日影 漘前に紅
翻知玄圃近 翻つて知る 玄圃の近きを
對翫入松風 對して翫す 松に入る風を
こうした時、日本の「柘枝の話」が気になります。「柘枝の話」では神の領域の川上から流れて来た「柘の枝」が美人となります。また、最後の昇天では羽衣や領巾によって行われますから、背景には羽衣伝説の変形があるのかもしれません。
平安時代末期から鎌倉時代に仏教では九想観と云うものが流行し、この流行の下、檀林皇后や小野小町などの九想観図が作られました。この九想観図は絶世の美女が死、仏教徒として野に捨てられると、やがて体は獣に食われ、虫にたかられ最後には白骨になるという場面を順に描くもので、差し障りの無いところの「絶世の美女=小野小町」と云うことで彼女の名前が借用されました。それと同じように異国や異郷からの美人と云うことで「柘媛」という名前が借用された可能性もあるのではないでしょうか。万葉時代では大和の美人の代表として「石川郎女」と云う名前を与えていますから、一概に無視はできないと考えます。
ただ一方、「柘」と云う漢字は現代では「やまくわ」、「つげ」ですし、『説文解字』では「桑」や「甘蔗」を意味すると云います。すると、奈良時代には甘い果実を付ける「やまくは=山桑」に対して「柘」と云う文字を与えていた可能性を否定できません。
こうした時、「山桑」は非常に有用な高木樹です。その樹皮は黄色系の染料となり、樹木自体は堅く木目の美しさから高級家具や将棋・呉盤の材料となります。また、果実は甘く食用になりますし、根皮は漢方薬の桑白皮(そうはくび)と呼ばれるもので利尿やせき止めなどの効用を持つ生薬として服用します。さらに繊維は強靭なので和紙に混用されるとします。このように古代では代表的な恵みの樹木なのです。それを「山の恵み=山の媛」として、この樹木に敬意を示したかもしれません。なお、養蚕に使う「くは」は中国から朝鮮半島に繁殖し輸入植物である「桑」であって、漢字では「桑」と記しますが、国内で古から繁殖する「やまくわ」とは違う植物です。そのため、「やまくわ」の漢字表記は「柘」であり「山桑」です。
そうしますと、歌の標題「仙柘枝謌三首」と歌中の「柘之左枝」とが同じものを示しているのかが問題となります。ご存知のように万葉集での標題のつけようからしますと、歌と標題が一致することは必ずしも保証されません。歌が先に詠われ、後に万葉集の編纂に合わせて編集者の判断で標題を与えた可能性があります。そうしますと、平安時代後期以降では『湖南觀雙柘枝舞賦』や「遊吉野(藤原史)」などの漢詩文作品群から「仙柘枝」は仙女をイメージして「やまひと、つみのえ」と訓じますが、本来ですと「やまひと、くわのえ」と訓じるべきなのかもしれません。
例えば、集歌385の歌では左注の「右一首或云、吉野人味稲与柘枝媛謌也」の文章でもって「柘枝媛」との関連を示唆しますが、歌自体には柘枝媛は詠われていません。「妹手」として、恋歌の中で年頃の女性を示唆するだけです。さらに集歌386の歌では「柘之左枝」ですし、集歌387の歌でも「柘之枝」だけです。直接の鑑賞からしますと「山桑の枝」であっても良いのですから、歌自体には「柘枝媛」の姿はないのです。ただ、比喩として受け止められるだけです。
実に不思議です。
時に、万葉集の編集者はこれら、全て、承知の上で標題「仙柘枝謌三首」を付けたのかもしれません。「遊吉野(藤原史)」が遅く大宝二年(702)の作品としましても藤原史は「柘枝舞」のようなものを知らない可能性があります。およそ、第七次遣唐使の帰国が慶雲元年(704)以前の作品では「仙柘枝謌」を「やまひと、つみのえ」として歌を詠うかと云うことです。やはり、編集者は遊びとして後年に「やまひと、くはのえ」と「やまひと、つみのえ」との二通りに読ませるつもりだったのかもしれません。ちゃんと判っているよねって。













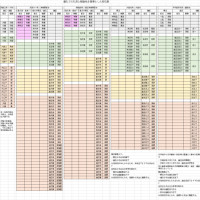






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます