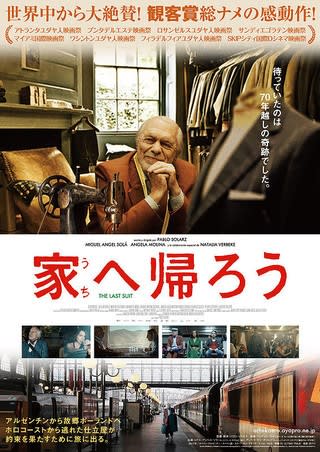・ 20年後、再びヴィクトリア女王になり切ったJ・デンチを楽しむ。
「Queen Victoria 至上の恋」(97)に続いて、ジュディ・デンチが晩年のヴィクトリア女王に扮し、インド人従者との交流を描いた事実をもとにしたドラマ。
シャラバニ・バスの原作を「リトルダンサー」のリー・ホールが脚本化、「クイーン」(06)、「あなたを抱きしめる日まで」(13)のスティーヴン・フリアーズが監督、「英国王のスピーチ」のダニーコールマンが撮影。
1887年、ヴィクトリア女王在位50周年記念式典で記念硬貨の贈呈役として選ばれたアブドゥル(アリ・ファザル)は、英国領インドから英国へやってくる。
決して目を合わせてはいけないと忠告されたアブドゥルだったが、思わず目を合わせ微笑んでしまう。最愛の夫アルバート公、心から気を許す従僕ジョン・ブラウンを相次いで亡くし、心を閉ざしてしまった女王にとってインドからきたのっぽの若者が心を開かせるものとなった。
従者として連れのモハメドとともに引き止められたアブドラル。インド皇女でもある女王は、いきなりつま先に口づけする大胆な行動や、母国を熱く語る物おじしない態度にすっかり魅せられてしまい、インドの文化・歴史を教える先生(ムンシ)として傍に置くようになる。
やがて王室を揺るがす大騒動へと発展することに・・・。
息子エドワード7世により歴史から抹殺された事実が2010年明らかになり、ほぼ実話をもとにしたストーリーとして映画化された。
女王の肖像画を見る限り大柄で豊満な感じだが、小柄なデンチが演じるとこんなだったと納得してしまう。
王宮の慣習を覆し多様な人生を歩んできたヴィクトリア。儀式にはほとんど興味がなく、侍従たちをひやひやさせるただの老女の姿をさらす。
ところがアブドゥルを観る瞳は少女のようでチャーミングな表情になる。孤独だった権力者にとって彼は異国から来た息子のようで、まだ観ぬ領国は興味の的だった。
アブドゥルにとって英国は観るもの聴くもの新鮮な驚きの連続で、観光気分から女王の庇護の元居心地の良い環境だった。
フリアーズ監督は前半は文化の違いをコミカルに中盤以降はシリアスに描くことで女王への敬意を忘れていない。女王の愛した離宮オズボーンズ・ハウスでのロケや衣装・勲章など細部へのこだわりも流石!
皇太子バーディ(エディ・イザート)を敵役に、首相のソールズベリー(マイケル・ガンボン)を堅物で面白みがない男に、秘書のホンソンビー(ティム・ピゴット=スミス)をイエスマンにさせたのも、女王の引き立て役にする演出だった。
お気に入りの刑務所書記官のインド人から教わった歴史には嘘もあり、爵位を授けたいという女王の行き過ぎた行為も描くことで彼らの差別主義者だけでない危機意識も伝わってくる。
微笑ましい逸話を感動の物語にするだけでなく、大英帝国の栄華と植民地の現実が描かれた宮廷劇だった。