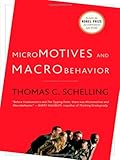ソーシャルメディア研究ワークショップ(SMWS)が、箱根湯本で開かれた。文理様々な分野の研究者や実務家が、ソーシャルメディアについて縦横に議論することを目的に設立され、今回で5回目になる。これまでの歴史を振り返ると・・・
第1回 鳥取大学
第2回 湯村温泉
第3回 松島温泉
第4回 道後温泉
第5回 箱根湯本温泉
うーむ・・・なぜか温泉ばかりだ・・・

今回の参加者は、マーケティング系5人、社会学・社会心理学系2人、コンピュータサイエンス系3人、物理学系5人、という分布。基本的にはどなたも、データ分析や事例分析を通じて、ソーシャルメディアの諸側面を切り取ろうとしていた。
発表テーマを分類すると、最も多かったのが、何らかの意味で、ソーシャルメディア上の発言の時系列パタンを分析した研究だ。タイトルを列挙すると、以下のようになる。そのほとんどが、物理学系の研究者が取り組んでいる研究だ。
■ソーシャルメディアにおける集合現象
■ソーシャルネットワーク上での話題の拡散を推定する
■ヒット現象の数理モデルによるAKB選抜総選挙予測
■最新アニメ映画のヒット~ソーシャルメディアによるヒット要因分析
■大規模ブログデータを用いた書き込み数の予測手法の開発
■大規模ブログデータからの感情抽出
一方、ネットワーク構造に注目したものには、以下の2つがあり、いずれもコンピュータサイエンスの研究者の手による。ただし、そこでも時系列変化は扱われているし、上のグループに分類した研究でもネットワークを扱ったものはある。
■社会的イベント発生時のソーシャルメディアにおける反応の分類
■ニコニコ動画の創作ネットワークからみえてくるもの
一方、社会学・社会心理学系の発表では、サーベイ調査の分析結果が報告された。物理学者が、データに現れる規則性をできるだけシンプルな数理モデルで表現しようするのに対し、社会科学者は、社会的に有意味な仮説の検証を試みる。
■東日本大震災後の情報環境・情報行動が1年半後の適応に何をもたらすか
別の次元でいえば、今回参加されていた実務家による報告では、ソーシャルメディアに関わるビジネスの現場での問題意識が吐露された。数理モデルの対極としてこういう発表があることも、このワークショップの1つの特徴といえる。
■ソーシャルデータのビジネス環境
■顧客クラスタをベースとしたメールマガジンの出し分けと、その反応(結果)のご報告
狭い意味でマーケティング研究者といえる3人は、今回新たに提案された「自著を語るセッション」に登壇した。華麗なるデータ分析と地を這うような事例研究の狭間で、それらをつなぐ役割を果たすべきなのは、おそらく彼らだろう。
以下が、今回「著者によって語られた」著作:
なお、私事になるが、今回で私はこのワークショップの世話人を退任した。自分より百倍優秀な後任を得て、この会の今後の飛躍が楽しみだ。その一方で、自分のソーシャルメディア研究は今後どうなるのか、という問題に直面している。
第1回 鳥取大学
第2回 湯村温泉
第3回 松島温泉
第4回 道後温泉
第5回 箱根湯本温泉
うーむ・・・なぜか温泉ばかりだ・・・

今回の参加者は、マーケティング系5人、社会学・社会心理学系2人、コンピュータサイエンス系3人、物理学系5人、という分布。基本的にはどなたも、データ分析や事例分析を通じて、ソーシャルメディアの諸側面を切り取ろうとしていた。
発表テーマを分類すると、最も多かったのが、何らかの意味で、ソーシャルメディア上の発言の時系列パタンを分析した研究だ。タイトルを列挙すると、以下のようになる。そのほとんどが、物理学系の研究者が取り組んでいる研究だ。
■ソーシャルメディアにおける集合現象
■ソーシャルネットワーク上での話題の拡散を推定する
■ヒット現象の数理モデルによるAKB選抜総選挙予測
■最新アニメ映画のヒット~ソーシャルメディアによるヒット要因分析
■大規模ブログデータを用いた書き込み数の予測手法の開発
■大規模ブログデータからの感情抽出
一方、ネットワーク構造に注目したものには、以下の2つがあり、いずれもコンピュータサイエンスの研究者の手による。ただし、そこでも時系列変化は扱われているし、上のグループに分類した研究でもネットワークを扱ったものはある。
■社会的イベント発生時のソーシャルメディアにおける反応の分類
■ニコニコ動画の創作ネットワークからみえてくるもの
一方、社会学・社会心理学系の発表では、サーベイ調査の分析結果が報告された。物理学者が、データに現れる規則性をできるだけシンプルな数理モデルで表現しようするのに対し、社会科学者は、社会的に有意味な仮説の検証を試みる。
■東日本大震災後の情報環境・情報行動が1年半後の適応に何をもたらすか
別の次元でいえば、今回参加されていた実務家による報告では、ソーシャルメディアに関わるビジネスの現場での問題意識が吐露された。数理モデルの対極としてこういう発表があることも、このワークショップの1つの特徴といえる。
■ソーシャルデータのビジネス環境
■顧客クラスタをベースとしたメールマガジンの出し分けと、その反応(結果)のご報告
狭い意味でマーケティング研究者といえる3人は、今回新たに提案された「自著を語るセッション」に登壇した。華麗なるデータ分析と地を這うような事例研究の狭間で、それらをつなぐ役割を果たすべきなのは、おそらく彼らだろう。
以下が、今回「著者によって語られた」著作:
 | 類似性の構造と判断 --他者との比較が消費者行動を変える |
| 澁谷 覚 | |
| 有斐閣 |
 | キーパーソン・マーケティング: なぜ、あの人のクチコミは影響力があるのか |
| 山本 晶 | |
| 東洋経済新報社 |
 | マーケティングは進化する -クリエイティブなMaket+ingの発想- |
| 水野 誠 | |
| 同文舘出版 |
なお、私事になるが、今回で私はこのワークショップの世話人を退任した。自分より百倍優秀な後任を得て、この会の今後の飛躍が楽しみだ。その一方で、自分のソーシャルメディア研究は今後どうなるのか、という問題に直面している。