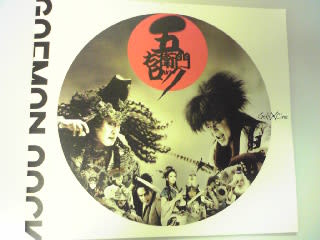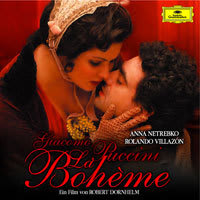3/1に観た「チェンジリング」でクリント・イーストウッド監督作品を初めて観た。その時の予告編で次回作として主演・監督作品の「グラン・トリノ」が出ていて是非とも観たいと思っていたのだが、母親は字幕を嫌がるし私は吹替えは嫌だし洋画はダメで後回しになっていてMOVIXさいたまの上映最終日、5時過ぎに職場を飛び出してようやく滑り込んだ。

【グラン・トリノ】
「@ 映画生活」のサイトの作品情報は以下の通り(このサイトにはユーチューブでエンドロールのテーマ曲の一部を歌うクリントのかすれたような歌声のリンクがあって早速聞いてしみじみしてしまう)。
朝鮮戦争の帰還兵ウォルト・コワルスキー(クリント・イーストウッド)はフォード社を退職し、妻も亡くなりマンネリ化した生活を送っている。彼の妻はウォルトに懺悔することを望んでいたが、頑固な彼は牧師(神父に要訂正)の勧めも断る。そんな時、近所のアジア系移民のギャングがウォルトの隣に住むおとなしい少年タオ(ビー・ヴァン)にウォルトの所有する1972年製グラン・トリノを盗ませようとする。タオに銃を向けるウォルトだが、この出会いがこの二人のこれからの人生を変えていく…。

ウォルトの妻の葬式の場面から始まり、新米のヤノビッチ神父(クリストファー・カーリー)の懺悔のすすめに毒づき、二人の息子とその家族たちと心が通わない頑固爺ぶりがすごい。けれども葬式にへそピアス露出ルックで参列して最中に携帯を平気で使ったりする孫にウォルトが唸るのには共感。一人残ったウォルトの財産をねらうさもしい家族の姿と孤りで自分のスタイルで残りの人生を生きようとするウォルトの姿の明らかな対照!

葬式後にウォルトの家で参会者にふるまいをしていると空き家だった隣に黄色人種が引っ越してきた。母子と祖母のロー一家だ。露骨に嫌な顔をするウォルト。
さらに隣家の息子タオが夜中に車泥棒にやってくる。母子が謝罪に来るが母親は英語をしゃべれずに姉娘が通訳。息子に償いをさせて欲しいとの申し出なのだがウォルトは拒否。さらに姉のスー(アーニー・ハー)が拒否は侮辱されたことになるとたたみかけるので渋々受け入れる。誇り高いウォルトは堂々と誇り高く主張する相手を認めざるを得ない。
ウォルトの誕生日にやってきた息子夫婦は親切ごかしに施設行きを勧めるのでブチ切れて追い返す。そこにスーが親族でいっぱいのホームパーティに隣人を誘いにくる。誕生日の孤独からついに隣家に足を踏み入れると白い目が囲むが、手づくりの民族料理の美味しさに心がなごみ、なぜこんな所=アメリカ中西部のデトロイト近郊にアンタたち=アジアの少数民族が来たのかをスーに質問。

私も冒頭からの疑問だったので聞いてびっくりだった。ベトナム戦争でアメリカ側についたモン族が戦後に亡命してきているのだという。社会主義国家ではなくなるはずの民族問題も解決できていないのは歴史が証明していて、ベトナムでも少数民族への多数派の民族の圧力があるのを利用してアメリカ側が抱き込んだわけだ。そういう歴史の不幸の結果がここにあった。
同じような広さの敷地に同じようなデザインの家が古くなって並んでいるウォルトの住む一帯はサブプライムローンの対象になるような住宅街という感じ。さらにアメリカ自動車産業の凋落と高齢化により住民が入れ替わり、低所得層が流入してきているのだ。

父親を早くに亡くした隣家は女たちが気丈なのに一人息子のタオだけがいつも自信なげである。スーは隣の白人の頑固爺にも臆せずに話しかけ、ウォルトは彼女の賢さとウィットにも富んだ人柄に心の壁を溶かされていく。償いの家事手伝いに通うタオの真面目さも見直し、彼を一人前にするために一肌脱ぐことになっていく。多様な人種が混在するアメリカ社会での男同士の会話も教え(かな~り乱暴だが微妙な距離感!)、仕事も紹介し、50年かけて集めた工具も貸してやる。
血のつながっているだけの身内よりも徐々に心が通うようになった隣家の姉弟を慈しむ心がウォルトの表情も変えていく。しかし彼の心の底には大きな傷も横たわっていているのも明らかになっていく。朝鮮戦争で十数名を殺し部隊でただ一人生還して勲章ももらっているが、人を殺してしまった罪悪感をずっと抱き続け、彼は他の多くの帰還兵のように教会で懺悔をして赦しを乞うことも潔しとしてこなかったのだ。そのことも突きつけられた神父も悩む。

そんな中でウォルトは喀血を繰り返すようになり、死期の近づいたことを知る。さらにスーとタオの従兄が不良グループのリーダーで執拗にウォルトのヴィンテージカーを盗んでこいと脅す。タオが傷めつけられたことでウォルトが不良グループにヤキを入れるが、その報復が凄まじかった。家に機関銃が打ち込まれスーはレイプされてボロ雑巾のようになって戻ってきた。

ウォルトは報復を決意し、タオは命をかけても報復をといきりたち、「左の頬を打たれたら・・・・・・」というはずの新米神父でさえウォルトを止めない。神父は警察に流血を止めてもらおうとするがいつ起こるかわからない事件のための予防出動は打ち切られる。タオはなんとウォルトに地下室に閉じ込められ、単身で不良たちの家に向かったウォルトは・・・・・・。相打ちに持ち込む作戦かな?それにしても多勢に無勢だよとドキドキ・・・・・・。
エエ~っ!!!
ちょっとしたしぐさで誤解させた不良たちの弾丸で蜂の巣になるウォルト。丸腰の自分を殺させることで一網打尽にさせて長期に服役させて姉弟を守るって・・・・・・。自分が死ぬことで誰かを守るって・・・・・・。
もうぐしょ泣きだ~(T-T)なんか武士道じゃん。「五右衛門ロック」のクガイじゃん。「グスコーブドリの伝記」じゃん。仏教の「捨身飼虎」じゃん。頑固爺も温かい心をもった人間に変われたという姿が嬉しかった。そして最後は心意気を貫いて死んでいくなんて・・・・・・。






2日前に観た「ミルク」のハーヴィーもそうだった!人間の生き様・死に様を考えさせられる映画が続いている。アメリカは好きな国ではないが、こういう作品を生み出す力があるというところに希望を感じる。

ウォルトの葬儀には教会の右のブロックをモン族の参列者が埋めつくす。スーは暴行を受けた顔を隠さずに民族衣装に身を包み堂々と最前列でウォルトへの謝意と敬意を表していた。ヤノビッチ神父のウォルトから学んだ胸が熱くなる説教にも涙。一方の左ブロックの親族は無感動の表情。弁護士が遺言書を読み上げるのを期待して聞くが、ウォルトの家は教会にグラン・トリノは友人のタオに遺贈された・・・・・・。何たる痛烈なしっぺ返しだろう。「アホの身内め、思い知ったか~」と溜飲が下がる。

エンドロールのクリントの歌声の流れる中をグラン・トリノが水辺を走っていく。運転するタオの表情には自信の溢れ、ウォルトの友情を前向きに受け入れた様子がうかがえた。

観終わって魂が持っていかれた感じがした。ハイ、やられました。蜷川幸雄といい、井上ひさしといい、クリント・イーストウッドといい、70過ぎのお爺様たちのクリエイティブな素晴らしい仕事にねじふせられっぱなしだ。目が離せない巨匠の一人にイーストウッドを加えさせていただくことにする。
写真はこの作品の宣伝画像。


















 ←→
←→