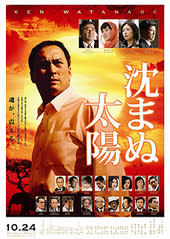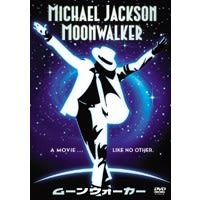1/1~2と妹2の家に新年会に行き、一泊して帰る際、母と一緒にMOVIXさいたまに行って「釣りバカ日誌20ファイナル」を観てきた。けっこう親孝行な私(^^ゞ感謝価格1000円だし、気軽につきあえる(笑)

原作の漫画は昔は読む機会もあったが、このシリーズを映画館で観るのは実は初めて。TVではよくチラ見していたけれど。
Wikipediaの「釣りバカ日誌」の項はこちら
【釣りバカ日誌20ファイナル】
公式サイトはこちら
監督:朝原雄三 脚本:山田洋次、朝原雄三
原作:やまさき十三、北見けんいち
出演:西田敏行、浅田美代子、吹石一恵、塚本高史、松坂慶子、谷啓、三國連太郎、加藤武、小野武彦、鶴田忍、中村梅雀、益岡徹、中本賢、笹野高史、奈良岡朋子、岸部一徳、六平直政、平田満、角替和枝、かとうかず子、高畑淳子
あらすじは以下、goo 映画の「釣りバカ日誌20ファイナル」の作品情報より引用。
「近年の不況の波はゼネコン業界にも訪れ、鈴木建設も例外ではなく、業績悪化の一途をたどっていた。そんな中、会長の一之助(スーさん)が無期限の給料全額返還を実行すると宣言、その噂は社内外に広まり大騒ぎになる。そんな中、スーさんのために一肌脱ごうと奮起した伝助(ハマちゃん)は、得意の釣り人脈から思いがけない大型受注に成功する。そのご褒美に釣り休暇をもらった伝助は、スーさんと共に北海道へ釣り旅行に出掛けた・・・・・。」

社会風刺も効いていて思いっきり笑いをとるシーンに大笑いし、しみじみもできて見ごたえがあった。エンドロールで脚本に山田洋次とあったので、しっかりとこのシリーズを把握することにしてプログラムを買ってしっかり読む。
3社が映画化を申し入れ、人情ものが得意な会社ということと脚本に山田洋次という条件で松竹が映画化の権利を獲得したらしい。渥美清さんの死去でシリーズが終る「男はつらいよ」との併映で始まり、好評で次の代表シリーズとして続いてきたという。
山田洋次や朝原雄三監督の文章で基本構造がよくわかった。作品のテーマは企業の創業者スーさんの苦労や悩みであり、その周囲でハマちゃんが楽しくからんでいく。山田洋次のメッセージがスーさんの台詞にこめられ、だから三國連太郎というキャスティングが生きるのだ!
三國連太郎の文章でも「ファイナルにしてこの作品がよくわかった」というようなことが書いてあった。だからファイナルだけでも映画館で観て正解だった。

北海道ロケも風景、幻のイトウ釣りの場面も自然が楽しめるし、松坂慶子と吹石一恵の母子家庭の母娘のドラマに主人公二人がからむのもよかった。
スーさんが脳梗塞で倒れて息を吹き返すまでの霊界ミュージカルが楽しいのだ。芝居も歌もうまいという西田敏行を活かしきっている。
生還を果たした上で役員勇退を宣言するスーさんの社員への言葉が圧巻。今の世の中の経営者たちには是非ここだけでも観てほしいくらいだ。
企業というものはそこで働く全ての人たちのもので、経営が傾いてもしも辞めてもらうような選択をする時は、役員からそうしなくてはいけないと、残りの役員たちに釘を刺した!!
その姿勢にホールを埋めた職員たちの拍手が、映画のシリーズのカーテンコールと重なっていくという手法に脱帽だ。そこで今は登場しなくなっていた谷啓も登場させるというのが憎い。
ただのお笑い映画だと思っている方も、こういうテーマ性もあり、上質なエンターテインメントにも仕上がっていることをお知らせしたいので、気合を入れて書いてみた。

写真はこの作品の宣伝画像。お正月らしくていいねぇ。


映画を観た後は、さいたま新都心駅ビルに直結できる「日本海庄屋」で母娘ふたりでお茶ではなくオチャケにした。
海鮮サラダがお刺身たっぷりで実に食べ応えあり(写真はこちら)。カルパッチョも食べたいと母が言うのをこれが来てから考えようといって正解。あんこうの小鍋も美味しかったし、海のお魚の映画を見てお魚料理を楽しんだのも大正解。
食事の後、母を妹2の家方面の電車に乗せてツレアイくんに駅まで車で迎えを頼み、自分は帰宅。親孝行の一日も無事終了(^^ゞ