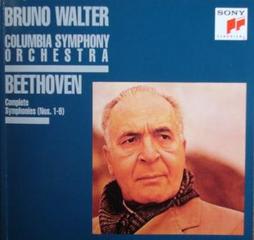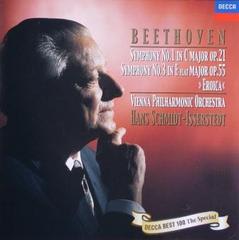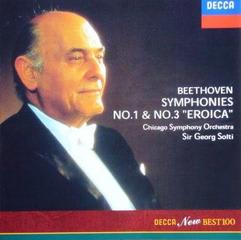ふくよかでやわらかいベートーベンのヴァイオリン協奏曲
ユーディ・メニューイン(1916年-1999年)はアメリカ合衆国出身のヴァイオリン奏者。イギリスでも活躍した。80歳を超えるまで現役として活動を続けた。
1953年にイギリスで録音したモノーラルCD。37歳のメニューインの生き生きとした演奏。ロンドンの名門、フィルハーモニア管弦楽団が、ドイツの巨匠、ウィルヘルム・フルトヴェングラー(1886年-1954年)が亡くなる1年前、67歳というまさに親子ほどの違う2人の演奏である。
ベートーベンを弾くならフルトヴェングラー先生だ、と公言はばからなかったというメニューン。第2次世界大戦後にスイスに隠遁していたフルトヴェングラーと初めて協演したのも、この協奏曲であった。
管弦のスケールの大きさは、さすが、フルトヴェングラー。そして、メニューインの澄んだ、ふくよかな音色。フルトヴェングラーは、この若手のヴァイオリニストを、まさにお釈迦様の手のように、ゆったりと、じっくりと歌わせている。
Total 44:06 ①24:01②9:42③10:23
ユーディ・メニューイン(1916年-1999年)はアメリカ合衆国出身のヴァイオリン奏者。イギリスでも活躍した。80歳を超えるまで現役として活動を続けた。
1953年にイギリスで録音したモノーラルCD。37歳のメニューインの生き生きとした演奏。ロンドンの名門、フィルハーモニア管弦楽団が、ドイツの巨匠、ウィルヘルム・フルトヴェングラー(1886年-1954年)が亡くなる1年前、67歳というまさに親子ほどの違う2人の演奏である。
ベートーベンを弾くならフルトヴェングラー先生だ、と公言はばからなかったというメニューン。第2次世界大戦後にスイスに隠遁していたフルトヴェングラーと初めて協演したのも、この協奏曲であった。
管弦のスケールの大きさは、さすが、フルトヴェングラー。そして、メニューインの澄んだ、ふくよかな音色。フルトヴェングラーは、この若手のヴァイオリニストを、まさにお釈迦様の手のように、ゆったりと、じっくりと歌わせている。
Total 44:06 ①24:01②9:42③10:23