
バルテュス(Balthus)は文学的な画家だ。
想像、妄想を抱かせ、物語を勝手に作らせてしまう。
彼の描く、少女に開脚、立て膝をさせて、無邪気とも妖しいともとれる雰囲気を醸し出した絵は、一度見たら忘れられないほど刺激的であり、スキャンダラスであったはずだ。
“20世紀最後の巨匠”と称される「バルテュス展」を上野の東京都美術館に見に行った。
彼の代表作は、多くが少女を主人公にしたものである。それも、まだ大人になっていない少女の性的匂いのするものである。風景画も描いているのだが、それは先入観のためか個性的とも魅力的とも思えない。
1934年にパリで開催されたバルテュスの最初の個展で、予めスキャンダルを引き起こすために「エロチックな場面」を挑発的に描いたという「ギターのレッスン」は、女教師が折檻している少女の下半身は剥き出しだ。最も有名な絵である、両手を頭にあげて目をつむって椅子に座っている少女像の「夢見るテレーズ」(1938年)は、少女は脚を開いて立て膝で、下着をのぞかせている。
薪を燃やしている男がいる暖炉の前で、手鏡を覗きながら長椅子に横たわる少女は、右胸を半分のぞかせ、やはり膝を立てて脚を伸ばしている。(写真、「美しい日々」1944‐1946)
バルテュスは若い時から年老いてまで、執拗に女性、なかでも少女を描いてきた。巧妙に計算された絵は、具象的のようでいて創作的、文学的だ。少女、もしくは少女のいる空間から、大人ではない性的な香りを漂わせる。
「ここで私は、次のような考えを披露したいと思う。それは、少女は九歳から十四歳の間に、自分より何倍も年上のある種の魅せられた旅人に対して、人間らしからぬ、ニンフのような(つまり悪魔的な)本性をあらわすことがあるという考えだ。私は、この選ばれたものたちを、「ニンフェット」と呼ぶことにしよう。」(「ロリータ」ナボコフ著、大久保康雄訳)
バルテュスからウラジーミル・ナボコフの「ロリータ」は容易に想像できよう。
ナボコフのいうところのニンフェット像は、今ではロリータ、ロリータ・コンプレックス、ロリコンと、わが国では独り歩きしている。
のちに「2001年宇宙の旅」を作ったスタンリー・キューブリックの監督による映画「ロリータ」(1962年)のスー・リオンは映画出演時には14、15歳だったというが、蠱惑的だ。
「美しい日々」にもあるように、バルテュスの絵にしばしば出てくる少女の持つ鏡は、ルイス・キャロルの「鏡の国のアリス」を示唆するものだろうか。最初の個展の時に出品した、胸をはだけ性器を見せながら髪を梳る女の絵のタイトルは、「鏡の中のアリス」(1933年)だ。
「アリス」も、しばしば少女の象徴、それも特別な雰囲気を持つ少女として表現される。沢渡朔の「少女アリス」(1973年出版)は出色の写真集である。
ちなみに、「ロリータ」のナボコフは、若い時にルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」をロシア語に翻訳している。
ロリータとアリス、バルテュスの絵は、別のところに秘かに道を伸ばす。
想像、妄想を抱かせ、物語を勝手に作らせてしまう。
彼の描く、少女に開脚、立て膝をさせて、無邪気とも妖しいともとれる雰囲気を醸し出した絵は、一度見たら忘れられないほど刺激的であり、スキャンダラスであったはずだ。
“20世紀最後の巨匠”と称される「バルテュス展」を上野の東京都美術館に見に行った。
彼の代表作は、多くが少女を主人公にしたものである。それも、まだ大人になっていない少女の性的匂いのするものである。風景画も描いているのだが、それは先入観のためか個性的とも魅力的とも思えない。
1934年にパリで開催されたバルテュスの最初の個展で、予めスキャンダルを引き起こすために「エロチックな場面」を挑発的に描いたという「ギターのレッスン」は、女教師が折檻している少女の下半身は剥き出しだ。最も有名な絵である、両手を頭にあげて目をつむって椅子に座っている少女像の「夢見るテレーズ」(1938年)は、少女は脚を開いて立て膝で、下着をのぞかせている。
薪を燃やしている男がいる暖炉の前で、手鏡を覗きながら長椅子に横たわる少女は、右胸を半分のぞかせ、やはり膝を立てて脚を伸ばしている。(写真、「美しい日々」1944‐1946)
バルテュスは若い時から年老いてまで、執拗に女性、なかでも少女を描いてきた。巧妙に計算された絵は、具象的のようでいて創作的、文学的だ。少女、もしくは少女のいる空間から、大人ではない性的な香りを漂わせる。
「ここで私は、次のような考えを披露したいと思う。それは、少女は九歳から十四歳の間に、自分より何倍も年上のある種の魅せられた旅人に対して、人間らしからぬ、ニンフのような(つまり悪魔的な)本性をあらわすことがあるという考えだ。私は、この選ばれたものたちを、「ニンフェット」と呼ぶことにしよう。」(「ロリータ」ナボコフ著、大久保康雄訳)
バルテュスからウラジーミル・ナボコフの「ロリータ」は容易に想像できよう。
ナボコフのいうところのニンフェット像は、今ではロリータ、ロリータ・コンプレックス、ロリコンと、わが国では独り歩きしている。
のちに「2001年宇宙の旅」を作ったスタンリー・キューブリックの監督による映画「ロリータ」(1962年)のスー・リオンは映画出演時には14、15歳だったというが、蠱惑的だ。
「美しい日々」にもあるように、バルテュスの絵にしばしば出てくる少女の持つ鏡は、ルイス・キャロルの「鏡の国のアリス」を示唆するものだろうか。最初の個展の時に出品した、胸をはだけ性器を見せながら髪を梳る女の絵のタイトルは、「鏡の中のアリス」(1933年)だ。
「アリス」も、しばしば少女の象徴、それも特別な雰囲気を持つ少女として表現される。沢渡朔の「少女アリス」(1973年出版)は出色の写真集である。
ちなみに、「ロリータ」のナボコフは、若い時にルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」をロシア語に翻訳している。
ロリータとアリス、バルテュスの絵は、別のところに秘かに道を伸ばす。











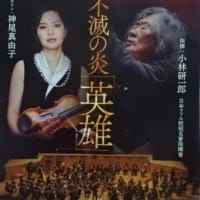

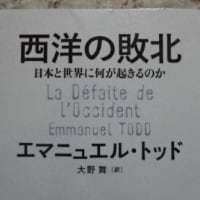











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます