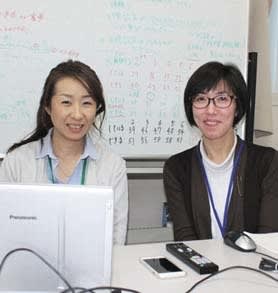第61号の特集は「病気はひとりで悩まないで。患者会活動で明日を生きる」。
病気はひとりで悩まずに、病気を正しく理解することが大切だ。同じ病気を抱える患者同士が話をすることで、悩みは半分になる。不安や悩みがあれば、患者会へ電話をすること。同じ不安や悩みを共有することで、そこから笑いも明日を生きる勇気も生まれてくる。高次脳機能障害や人工透析、リウマチ、がん、脊髄小脳変性症・多系統萎縮症、パーキンソン病の6つの患者会を紹介した。
◎高次脳機能障害
交通事故やスポーツ、転落での脳外傷、脳血管障害などの脳の病気などによる脳の損傷が原因で、言語障害や記憶障害、社会的行動障害などが起こる病気を「高次脳機能障害」と呼んでいる。外見からは病気がわからず、社会的支援も受けにくい状況にあった。
このような高次脳機能障害を負った当事者や家族が集まり、交流や情報交換をする患者会が「日本脳外傷友の会」で全国43都道府県に支部がある。脳外傷友の会「コロポックル」は、子供の高次脳機能障害に悩む母親達が平成11年2月に立ち上げた家族会だ。全国ネットの中で高次脳機能障害の実態を訴え、支援体制の確立を目指している。「脳外傷友の会コロポックル道南支部」が設立したのは同14年。翌15年に代表に就任したのが村上峯子さんだ。

脳外傷友の会コロポックル道南支部代表の村上峯子さん。
◎函館地方腎友会
腎臓の働きが10%以下になると、血液の濾過が充分に行えず、水分や老廃物のコントロールができなくなるが、さまざまな原因により腎臓の働きが不十分になった状態が腎不全だ。腎不全の末期症状で、低下した腎機能の代わりの役割を果たすのが「透析療法」である。このような腎臓病患者の医療と生活の向上を目的として、1971年に結成した腎臓病患者の患者会組織が一般社団法人全国腎臓病協議会(略称・全腎協)だ。設立以来、全腎協は全国の腎臓病患者の代弁者として行政・医療団体へ要望を申し入れるなど、医療や福祉に関する問題提起や政策提言を行ってきた。現在、全国の会員数は約9万人で、日本最大の患者会といわれている。
函館地方腎友会(館由紀子会長)は昭和59年に設立された。道南の透析患者数は渡島地区1142人、檜山地区104人の合計1246人。腎友会の会員は約160人で緩やかな減少傾向が続いている。事務局長の河村紳司さん(67歳)は「腎友会の歴史は、腎臓病患者の命を守る医療制度や福祉制度をつくるように、国や地方行政へ働きかける運動から始まった」と話す。

函館地方腎友会事務局長の河村紳司さん。
◎リウマチ
関節の滑膜に炎症が起こり、その結果、痛みと変形を残す病気が難病の一つと言われている「関節リウマチ」だ。長期の療養生活の中で、精神的、経済的、社会的に多くの問題を抱えた患者同士が「リウマチに関する正しい知識を広め、リウマチ対策の確立と推進を図り、リウマチ性疾患を有する者の福祉の向上に努める」という目的を持って発足したのが「日本リウマチ友の会」で、全国都道府県に47支部がある。
リウマチ治療は研究の成果により大きく進展し、薬による治療法が確立、治療の目的が「寛解」を目指せるようになった。友の会は患者が一番に望んでいる「原因解明と治療法の確立」が一日も早くなることを願って活動している。日本リウマチ友の会の北海道支部道南地区の幹事を担当してるのが宮澤生雄さんだ。宮澤さんは約20年前の40代の頃、右肩が上がらない症状に悩まされて整骨院で治療を受けていた。

日本リウマチ友の会北海道支部道南地区幹事の宮澤生雄さん。
◎がん
現在、日本人の2人に1人ががんになり、3人に1人はがんで亡くなるといわれている。職場や学校、医療機関などでの検診による早期発見の取り組み、化学療法や放射線治療などのがん医療の進歩によって、がんと診断された人の生存率も向上している。その一方で、がんを告知されたときや、再発を言われたときには、誰もが大きな精神的ダメージを受ける。
患者が悩みを打ち明け合い、孤独を解消するための「出会いの場」が患者会だ。がん患者の患者会は全国各地に誕生しているが、函館では、すべてのがんを対象に、がん患者同士が不安や悩みを語り合うことで、交流を深めながら精神的な支えを目指した患者会がある。函館がん患者家族会「元気会」で、道南地区では様々ながんの垣根を超えた初めての患者会として積極的な活動を続けている。元気会は代表の斉藤佐知子さんら3人が中心となって2008年7月に設立された。患者会を立ち上げるきっかけとなったのは2005年に乳がん手術を受けた斉藤さんの闘病体験だった。

函館がん患者家族会「元気会」代表の斉藤佐知子さん。
◎脊髄小脳変性症
「であい友の会」は脊髄小脳変性症を対象としている患者会だ。脊髄小脳変性症は多くの病気からなるが、全体の約70%が遺伝性のない弧発性で、約30%が遺伝性と言われている。弧発性は皮膚性小脳萎縮症と多系統萎縮症に大別され、多系統萎縮症はさらにオリーブ橋小脳変性症、線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群の3つの疾患が含まれる。運動失調を主症状とする脊髄小脳変性症は、小脳・脊髄及びその関連領域がいろいろな組み合わせで変性する症候群で、病変部位により発病年齢や症状の特徴はさまざまだが、最初に体の異常に気づくのは本人よりも家族や職場の同僚など、まわりの人々からの指摘による場合が多いようだ。歩行時のふらつきによって「酔っぱらっているようだ」と言われたり、物を持った時に手が震える、言葉が途切れ途切れになり、ろれつが回らないというような症状から病気が発見されることが多い。
「であい友の会」の道南地区連絡会が誕生したのは平成26年。3人で始めた会員数は現在10数人までになった。道南地区連絡会の運営委員を担当するのは山岸良童さん(61歳)。友の会では講演会のほか、難病医療費助成制度などに関する勉強会などを開催したり、会員同士が療養生活や経験談について話をする交流会を開催している。

「であい友の会」道南地区連絡会運営委員の山岸良童さん。
◎パーキンソン病
手のふるえや動作が遅くなったり、筋肉が固くなる、姿勢を保つことが困難になるといった四大症状で知られるパーキンソン病は、その他にも、すり足や小刻み歩行、小声などの運動症状、便秘や頻尿などの生活関連症状、あるいは精神症状などの苦しい状態が一生続く病気だ。
年をとるにしたがって、脳のすべての神経細胞は徐々に減少していくが、パーキンソン病では普通以上に中脳の神経細胞が減少する。中脳にはドパミンという化学物質を作る黒質と呼ばれる部分がある。ドパミンは姿勢を保持したり、運動の速さを調整する役目を果たしているが、パーキンソン病ではこのドパミンが減少することで、脳からの運動指令がうまく伝わらないために、手足のふるえなどの症状がおこる。ドパミンが減少する理由はわかっていないが、現在では、ドパミンの中にαシヌクレインというタンパク質が凝集して蓄積することで、ドパミンが減少すると考えられている。そのためαシヌクレインが増加しないようにすることが、新しい治療薬開発の大きな目標となっている。
昨年4月、全国パーキンソン病友の会北海道支部函館ブロックの新しい代表に就任したのが、小松悟さん(68歳)だ。小松さんが発病したのは15年前の53歳。「小学校の教員でしたが、黒板に字を書く際にチョークを落とす回数が多くなったことが気になるようになりました」。

全国パーキンソン病友の会北海道支部函館ブロック代表の小松悟さん。