市立函館病院と高橋病院との間でネットワークのテスト運用を繰り返している「道南地域医療連携システム」は、インターネットを介するIT技術であるVPNを利用したもので、ソフトウエア設計・開発のエスイーシー(本社・函館市末広町)医療システム事業部がそのシステムを開発している。
「この地域医療連携ネットワークシステムをインフラとして、道南地域全体の病院や診療所が有機的なつながりを持つことで安全で効率的な医療を目指したい」(市立函館病院の下山則彦副院長)との考えから、4月21日に市立函館病院講堂を会場として道南地域医療連携のフォーラムが開催された。フォーラムには道南の病院関係者や開業医など約130人もの参加があり、医療情報を共有するためのネットワークへシステムの関心の高さがうかがえた。
今回のフォーラムは急性期病院、がん拠点病院、回復期病院、在宅医療それぞれの立場から各医師が地域連携の必要性を発表、さらに後半のパネルディスカッションでは「あたらしい道南地域医療連携をめざして」をテーマに、函館おしま病院の福徳雅章理事長が司会を担当。地域医療連携に対する様々な要望を拾い上げる場としパネリストの様々な観点からの意見に対して、会場の参加者からの質問、意見を交えながら熱心な議論が交わされた。
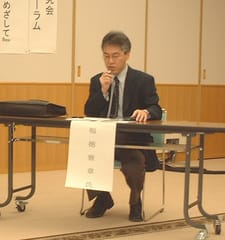 パネルディスカッションの司会をする函館おしま病院の福徳雅章理事長
パネルディスカッションの司会をする函館おしま病院の福徳雅章理事長
演題および演者は下記の通り
●道南地域医療連携ネットワークシステム構築の現在
下山則彦(市立函館病院地域医療連携室長)
●地域医療連携:地域がん診療連携拠点病院の立場から
木村 純(市立函館病院がん診療の向上に関する実務委員会委員長)
●地域医療連携:回復期病院の立場から
高橋 肇(高橋病院理事長)
●地域医療連携:在宅医療の立場から
岡田晋吾(北美原クリニック理事長)


パネルディスカッションのパネリスト、写真左から市立函館病院の木村純副院長、市立函館病院の下山則彦副院長、北美原クリニックの岡田晋吾理事長、高橋病院の高橋肇理事長
「この地域医療連携ネットワークシステムをインフラとして、道南地域全体の病院や診療所が有機的なつながりを持つことで安全で効率的な医療を目指したい」(市立函館病院の下山則彦副院長)との考えから、4月21日に市立函館病院講堂を会場として道南地域医療連携のフォーラムが開催された。フォーラムには道南の病院関係者や開業医など約130人もの参加があり、医療情報を共有するためのネットワークへシステムの関心の高さがうかがえた。
今回のフォーラムは急性期病院、がん拠点病院、回復期病院、在宅医療それぞれの立場から各医師が地域連携の必要性を発表、さらに後半のパネルディスカッションでは「あたらしい道南地域医療連携をめざして」をテーマに、函館おしま病院の福徳雅章理事長が司会を担当。地域医療連携に対する様々な要望を拾い上げる場としパネリストの様々な観点からの意見に対して、会場の参加者からの質問、意見を交えながら熱心な議論が交わされた。
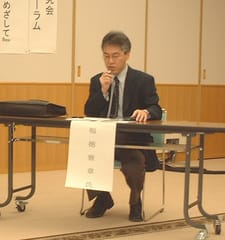 パネルディスカッションの司会をする函館おしま病院の福徳雅章理事長
パネルディスカッションの司会をする函館おしま病院の福徳雅章理事長演題および演者は下記の通り
●道南地域医療連携ネットワークシステム構築の現在
下山則彦(市立函館病院地域医療連携室長)
●地域医療連携:地域がん診療連携拠点病院の立場から
木村 純(市立函館病院がん診療の向上に関する実務委員会委員長)
●地域医療連携:回復期病院の立場から
高橋 肇(高橋病院理事長)
●地域医療連携:在宅医療の立場から
岡田晋吾(北美原クリニック理事長)


パネルディスカッションのパネリスト、写真左から市立函館病院の木村純副院長、市立函館病院の下山則彦副院長、北美原クリニックの岡田晋吾理事長、高橋病院の高橋肇理事長
























