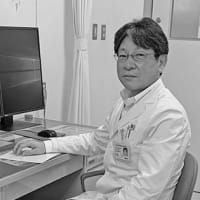「妻が余命宣告されたとき、 僕は保護犬を飼うことにした」(風鳴舎)の著者、小林孝延さんは1967年福井県出身の編集者。月刊誌ESSE、天然生活ほか料理と暮らしをテーマにした雑誌の編集長などを務め、プロデュースした料理や暮らし関連の書籍は「料理レシピ本大賞」で入賞・部門賞などを多数獲得している。
 「妻が余命宣告されたとき、 僕は保護犬を飼うことにした」(小林孝延著、日経メディカル)
「妻が余命宣告されたとき、 僕は保護犬を飼うことにした」(小林孝延著、日経メディカル)
小林さんの妻、薫さんは小林さんと結婚してすぐに乳がんを発症した。乳房とリンパ節を切除し、長期間のホルモン療法でがんを抑えていた。2015年11月、薫さんの様子が明らかにおかしくなった。
ずっと変な咳もとまらない。検査の結果、腫瘍マーカーの数値は高く、モニターには肺と肝臓に転移した白い大きな影があった。「2010年に乳がんが再発、肝臓や気管前リンパ節、肺などに遠隔転移して以降もホルモン療法で5年間封じ込めていたが、その乳がんがついに牙を剥いたのだった」
抗がん剤パクリタキセルと併用してアメリカの新薬を投与する治験に参加できることになった。
「新しくて効果絶大な薬に違いないから、絶対よくなるに決まっている。そう思うと僕たちは明るい気持ちになった」。しかし実際に投薬を開始すると抗がん剤の副作用は想像を遥かに超えるものだった。
薫さんは症状が悪化した頃から、精神のバランスが不安定になっていく。抗うつ剤を使用しながら、現実から逃避するように飲酒量が増えていった。小林さんはお酒の飲み過ぎを強く注意するが、どんどん言い方がきつくなり自分を止められなくなる。大学生の息子と高校生の娘はビクビクしながら過ごすようになり、家はいつのまにか殺伐とした空間に変わり果ててしまった。
「終わりの見えない日々。いったい、いつまで続くのか。でもこの苦しみが終わるということは、同時に薫が死を迎えることを意味する。ときどき、僕自身、自分がなにを望んでいるのかわからなくなってしまうことがたびたびあった」。パクリタキセルと治験薬の併用投与から3カ月が経過。検査で骨の病変に変化がみられるようになり、同時に腫瘍マーカも上昇していた。
現在の薬は終了し、抗がん剤が変更される。「抗がん剤が効かなくなったことにショックを受けたものの、まだ選択肢はある。希望を捨てる必要はない。そう言いながら帰路についたが、その晩、薫はひどく泣いていた」。薫さんが席を外したときに小林さんが主治医から聞いたのは「目標は半年」。つまり余命6カ月という通告だった。
家族の心はバラバラになっていた。そんな時、知人から「犬を家族に迎えてみたら? 犬を飼うと毎日が絶対楽しくなるはず」と言われた。
小林さんは保護犬を選択することを考えた。保護施設で人が訪ねて来ても全然出てこない子犬がいた。いつも隠れているから、里親を希望する人たちにも気付いてもらえない。誰にも気付いてもらえないうちにどんどん大きくなるので、家族に迎え入れてくれる人は現れない。
大きくなった犬は「売れ残る」傾向にあるのだ。小林さんはこの犬を飼うことにした。名前は小林家に福がやってくるように「福」と名付けられた。家族4人はいつまでもみんなで飽きることなく「福」の様子を眺めた。2016年の年末。夜が静かにふけていった。
ぎくしゃくしていた家族関係の中でなんとか踏ん張ろうとして息が詰まりそうになっていた小林さんの生活にもゆっくりと変化が訪れた。
小林さんは滑りが悪くなっていた家族の間を仕切っていた扉が滑らかに大きく開き、お互いへの思いやりが風のように心地よく吹き抜けるのを感じた。「福」の心も柔らかく溶けていった。
気がつけば薫さんにも家族にも笑顔が戻っていた。余命半年はすでに過ぎていて、あれはきっと何かの間違いだったのではと思われた。3カ月使用してきた抗がん剤ゼローダは効果があると考えていたが、検査結果を見た主治医からは「次に使う抗がん剤はどれにするか」と提案された。
小林さんはいろいろな思いで気持ちが揺れた。迷いを払拭すべく予約が取れない名医として有名なK医師を訪ねてセカンドオピニオンを受けることにした。待ち合わせに指定されたのは東京駅構内のコーヒーショップ。K医師は出張の待ち時間を割いてくれた。黙って資料に目を通したK医師を固唾を飲んで見守る。一体どんな状態なのか。
「ゼローダはぜんぜん効いてないですね。奥様に残された時間はあまり長くないと思います。次に選ぶ抗がん剤もおそらくそれほど効果は期待できないでしょう。まして新しい療法を試すとかそういう段階ではすでにないです」。予想以上に厳しい言葉で、小林さんには静かな森の中にいるような不思議な感覚が襲ってきた。「奥様はなにがお好きですか。趣味とか、なにか大好きなことはありませんか」。予想外の質問にはっと我にかえった小林さんは考えれば考えるほどわからない。なんだろう。なにが好きだったのだろう。その後の話はほとんど覚えていなかった。
どうしていいかわからないまま、小林さんは以前読んだ「抗がん剤のやめどき」という本をさりげなくリビングに置いた。それから夫婦はこれからの楽しみについて、これまで以上に話し合うようになった。残された時間を丁寧に味わっていこうと改めて心に誓った。
リビングが薫さんの居場所になり、1日のほとんどの時間をそこで過ごすようになると、いつしか「福」は薫さんにぴたりとつくようになった。「ときどき確かめるように手を伸ばして、枕元で丸くなっている福に触れると薫は安心するようだった。
触れている薫の表情はとてもやわらかくなる。人に触れられるのが好きではない福だけど、薫がなでることは全面的に受け入れているようだった。
その様子はまるで福が自ら果たすべき役割を理解しているように思えた」
 「妻が余命宣告されたとき、 僕は保護犬を飼うことにした」(小林孝延著、日経メディカル)
「妻が余命宣告されたとき、 僕は保護犬を飼うことにした」(小林孝延著、日経メディカル)小林さんの妻、薫さんは小林さんと結婚してすぐに乳がんを発症した。乳房とリンパ節を切除し、長期間のホルモン療法でがんを抑えていた。2015年11月、薫さんの様子が明らかにおかしくなった。
ずっと変な咳もとまらない。検査の結果、腫瘍マーカーの数値は高く、モニターには肺と肝臓に転移した白い大きな影があった。「2010年に乳がんが再発、肝臓や気管前リンパ節、肺などに遠隔転移して以降もホルモン療法で5年間封じ込めていたが、その乳がんがついに牙を剥いたのだった」
抗がん剤パクリタキセルと併用してアメリカの新薬を投与する治験に参加できることになった。
「新しくて効果絶大な薬に違いないから、絶対よくなるに決まっている。そう思うと僕たちは明るい気持ちになった」。しかし実際に投薬を開始すると抗がん剤の副作用は想像を遥かに超えるものだった。
薫さんは症状が悪化した頃から、精神のバランスが不安定になっていく。抗うつ剤を使用しながら、現実から逃避するように飲酒量が増えていった。小林さんはお酒の飲み過ぎを強く注意するが、どんどん言い方がきつくなり自分を止められなくなる。大学生の息子と高校生の娘はビクビクしながら過ごすようになり、家はいつのまにか殺伐とした空間に変わり果ててしまった。
「終わりの見えない日々。いったい、いつまで続くのか。でもこの苦しみが終わるということは、同時に薫が死を迎えることを意味する。ときどき、僕自身、自分がなにを望んでいるのかわからなくなってしまうことがたびたびあった」。パクリタキセルと治験薬の併用投与から3カ月が経過。検査で骨の病変に変化がみられるようになり、同時に腫瘍マーカも上昇していた。
現在の薬は終了し、抗がん剤が変更される。「抗がん剤が効かなくなったことにショックを受けたものの、まだ選択肢はある。希望を捨てる必要はない。そう言いながら帰路についたが、その晩、薫はひどく泣いていた」。薫さんが席を外したときに小林さんが主治医から聞いたのは「目標は半年」。つまり余命6カ月という通告だった。
家族の心はバラバラになっていた。そんな時、知人から「犬を家族に迎えてみたら? 犬を飼うと毎日が絶対楽しくなるはず」と言われた。
小林さんは保護犬を選択することを考えた。保護施設で人が訪ねて来ても全然出てこない子犬がいた。いつも隠れているから、里親を希望する人たちにも気付いてもらえない。誰にも気付いてもらえないうちにどんどん大きくなるので、家族に迎え入れてくれる人は現れない。
大きくなった犬は「売れ残る」傾向にあるのだ。小林さんはこの犬を飼うことにした。名前は小林家に福がやってくるように「福」と名付けられた。家族4人はいつまでもみんなで飽きることなく「福」の様子を眺めた。2016年の年末。夜が静かにふけていった。
ぎくしゃくしていた家族関係の中でなんとか踏ん張ろうとして息が詰まりそうになっていた小林さんの生活にもゆっくりと変化が訪れた。
小林さんは滑りが悪くなっていた家族の間を仕切っていた扉が滑らかに大きく開き、お互いへの思いやりが風のように心地よく吹き抜けるのを感じた。「福」の心も柔らかく溶けていった。
気がつけば薫さんにも家族にも笑顔が戻っていた。余命半年はすでに過ぎていて、あれはきっと何かの間違いだったのではと思われた。3カ月使用してきた抗がん剤ゼローダは効果があると考えていたが、検査結果を見た主治医からは「次に使う抗がん剤はどれにするか」と提案された。
小林さんはいろいろな思いで気持ちが揺れた。迷いを払拭すべく予約が取れない名医として有名なK医師を訪ねてセカンドオピニオンを受けることにした。待ち合わせに指定されたのは東京駅構内のコーヒーショップ。K医師は出張の待ち時間を割いてくれた。黙って資料に目を通したK医師を固唾を飲んで見守る。一体どんな状態なのか。
「ゼローダはぜんぜん効いてないですね。奥様に残された時間はあまり長くないと思います。次に選ぶ抗がん剤もおそらくそれほど効果は期待できないでしょう。まして新しい療法を試すとかそういう段階ではすでにないです」。予想以上に厳しい言葉で、小林さんには静かな森の中にいるような不思議な感覚が襲ってきた。「奥様はなにがお好きですか。趣味とか、なにか大好きなことはありませんか」。予想外の質問にはっと我にかえった小林さんは考えれば考えるほどわからない。なんだろう。なにが好きだったのだろう。その後の話はほとんど覚えていなかった。
どうしていいかわからないまま、小林さんは以前読んだ「抗がん剤のやめどき」という本をさりげなくリビングに置いた。それから夫婦はこれからの楽しみについて、これまで以上に話し合うようになった。残された時間を丁寧に味わっていこうと改めて心に誓った。
リビングが薫さんの居場所になり、1日のほとんどの時間をそこで過ごすようになると、いつしか「福」は薫さんにぴたりとつくようになった。「ときどき確かめるように手を伸ばして、枕元で丸くなっている福に触れると薫は安心するようだった。
触れている薫の表情はとてもやわらかくなる。人に触れられるのが好きではない福だけど、薫がなでることは全面的に受け入れているようだった。
その様子はまるで福が自ら果たすべき役割を理解しているように思えた」