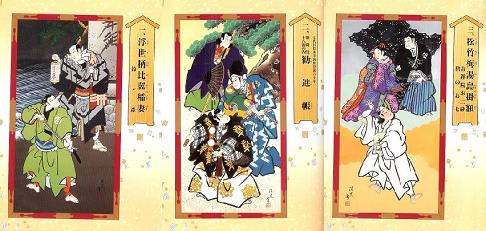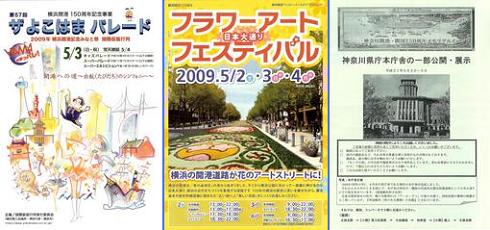kan-haru blog 2009 浜名湖花博
< 総合INDEX へ
首都圏での宇宙科学博覧会
1970年の万国博が開催されてから、首都圏での地方博が1978年に東京埋め立て地の有明13号地で「宇宙科学博覧会」(宇宙博 SPACE EXPO’78&’79)が宇宙博覧会協会の主催、財団法人日本船舶振興会(日本財団)の特別援助で開催され、会期は第1期が「宇宙-人類の夢と希望」をテーマにして1978年(昭和53年)7月16日から翌年の1月15日間と、第2期は国際児童年に当り「宇宙-人類の夢と希望、わが子への愛を世界のどの子にも」をテーマにして同年3月24日から9月2日まで行われました。
戦後初めて東京で開かれた博覧会であるので、父と子、孫の3代で揃って見に行きましたが、出かけたのは何時の時期かは記憶に残っていません。アポロ宇宙船やロケットの展示を見て、宇宙時代への進展(「ITと技術 筑波宇宙センターとサイエンス・スクエアつくば見学 その1」参照)に関心を持ちました。

宇宙科学博覧会が開かれた埋立13号付近の1979年の航空写真(国交省オルソ化空中写真システムを活用)
博覧会のパビリオン(宇宙科学博覧会Wikipedia参照)は、日本館、アメリカ館、アポロ劇場、宇宙博ホールの4館と船の科学館(イベント 船に関する知識の宝庫 「船の科学館」参照)3階展示ホールの展示場に、ロケット広場にサターンIB、レッドストーン、アトラスなどのロケットが展示されました。また、日本万国博覧会で人気のあった月の石や月面活動の道具などが展示され、画面の展示はアポロ館で360度のパノラマスクリーンでアポロ月面着陸の再現画面と、宇宙博ホールで高さ23m、幅30mのスクリーンに「人は大空へ」の映画が表示されました。
博覧会の入場者数は第1期が550万人、第2期が570万人(日本財団公表)で、予想をはるかに上回りました。

宇宙科学博覧会(日本財団出典)
国際科学技術博覧会
国際科学技術博覧会(つくばEXPO’85)は、茨城県のつくば市で1985年(昭和60年)3月17日から9月16日までの期間開催された国際博覧会です。博覧会の組織は、皇太子明仁親王(今上天皇)を名誉総裁に、土光敏夫会長の組織で財団法人国際科学技術博覧会協会が主催し、「人間・居住・環境と科学技術」を統一テーマとして開催されました。
博覧会の会場(国際科学技術博覧会Wikipedia参照)は、つくば市御幸が丘のメイン会場と同吾妻のサブ会場の102ヘクタールに展開し、メインの第1会場はAブロックからGブロックに区分けして国内パビリオンは28館と、その他外国館や関連機関のパビリオンや広場・遊園地などの52の展示場が造られました。

つくばEXPO’85の見学1985年6月
会場へのアクセスとして、国鉄常磐線の牛久駅と荒川沖駅間に臨時の万博中央駅が設置されましたが、13年後の1998年にひたち野うつくし駅が開設されました。また、HSST方式のリニアモーターカーのデモ運行が行われました。
博覧会の総入場者数は、2033万4727名を記録しました。博覧会には個人で出かけ、そのひとつは開催前の3月に所属する団体で、開催準備中の万博会場を見学しました。

つくばEXPO’85の施設見学1985年3月
横浜博覧会
横浜博覧会YES’89は、横浜みなとみらい21地区(69ヘクタール)で1989年に横浜市制100周年と開港100周年を記念し、横浜博覧会協会の主催でテーマを「宇宙と子供たち」(21世紀の展望)と掲げて、1989年3月25日から10月1日間にわたり開催され、総入場数は1,333万人でした。

みなとみらい地図
博覧会場へのアクセスは、桜木町駅からは動く歩道で桜木町ゲートまで約3分で着き、山下公園から1911年に開通の貨物線を利用して桜木町ゲートに近い日本丸駅まで気道車が運転されました。また、横浜そごうからゴンドラが運行してゴンドラゲートまで往復していました。その他、各地からのシーバスやシャトルバスが運行されていました。さらに、HSSTが日本初の磁気浮上式鉄道の営業運転や、羽田空港からヘリコプターの定期便就航など各種の交通手段が動員されました。
博覧会のパビリオン(横浜博覧会Wikipedia参照)は、YES’89宇宙館(横浜博覧会協会)、横浜館(横浜市)など30館を数えます。
横浜博覧会には、九州からお客さんが来て案内して、現在の観覧車のある付近を歩いたとの微かな記憶があるのですが、横浜博に関しては写真などが見当たらずそれ以上は想いだせません。
浜名湖花博
浜名湖花博は、浜名湖ガーデンパーク(現浜松市西区村櫛町)の約56ヘクタールの会場で秋篠宮文仁親王が総裁を務められ、日本花博の3回目で次項の日本国際博覧会の宣伝の役割も持って、2004年4月8日から10月11日まで開催して約544万人が来場して成功をおさめました。

浜名湖花博会場地図
博覧会の会場(浜名湖花博Wikipedia参照)は3つのゾーンがあり、1つは「花の街」でワールドガーデンコンベディション、KANSAI SUPER GARDENNなどの11の庭園やパピリオンがあり、2つ目は「水の園」できらめきタワーや水辺の劇場などの展示場があり、3つ目は「緑の里」で昭和天皇自然館や花の美術館などの7展示館があります。
花博の見学は、5月23日に行きましたが、新幹線に乗っている間じゅう雨が降り続いていましたが、浜圧駅からのシャトルバスで会場につくと雨は殆ど止んで何とか博覧会会場内を歩いて廻りました。印象に残った展示は、フランス・ジヴェルーにあるクロード・モネの家と庭園の再現が花博にマッチしていました。

浜名湖花博会場
日本国際博覧会
日本国際博覧会は、略称は「愛知万博」、愛称が「愛・地球博」の国内2回目の国際博覧会です。会場は、愛知県愛知郡長久手町の長久手会場(約173ヘクタール 愛・地球博記念公園地図参照)と瀬戸市の瀬戸会場(約15ヘクタール)の2会場で財団法人2005年日本国際博覧会協会の主催で、テーマは「人と自然が如何に共存していくか」を掲げて開催されました。入場者は、2,204万9,544人で目標の1,500万人を大きく上回りました。
愛・地球博への参加国は日本を含めて121カ国、4つの国際機関には国連本部と国連関係機関33が参加しました。
日本国際博覧会には、孫夫婦と2家族で6月15日に新幹線で日帰りの見学をしてきました。当然のことながら、日本万国博覧会と同様に人気パビリオンには待ち時間が2時間を越えるのがざらでそこは避け、121カ国も参加していますので比較的空いているパビリオンに入り、いろいろな国の人と展示品に触れてきました。

日本国際博覧会パビリオン
< 総合INDEX へ
毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(10月分掲Indexへ)
・カテゴリー別Index イベント総目次 2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ
<前回 イベント 横浜・開国博Y150 これまで見た博覧会と比較して見る(その1) へ
次回 イベント 横浜・開国博Y150 これまで見た博覧会と比較して見る(その3) へ
< 総合INDEX へ
首都圏での宇宙科学博覧会
1970年の万国博が開催されてから、首都圏での地方博が1978年に東京埋め立て地の有明13号地で「宇宙科学博覧会」(宇宙博 SPACE EXPO’78&’79)が宇宙博覧会協会の主催、財団法人日本船舶振興会(日本財団)の特別援助で開催され、会期は第1期が「宇宙-人類の夢と希望」をテーマにして1978年(昭和53年)7月16日から翌年の1月15日間と、第2期は国際児童年に当り「宇宙-人類の夢と希望、わが子への愛を世界のどの子にも」をテーマにして同年3月24日から9月2日まで行われました。
戦後初めて東京で開かれた博覧会であるので、父と子、孫の3代で揃って見に行きましたが、出かけたのは何時の時期かは記憶に残っていません。アポロ宇宙船やロケットの展示を見て、宇宙時代への進展(「ITと技術 筑波宇宙センターとサイエンス・スクエアつくば見学 その1」参照)に関心を持ちました。

宇宙科学博覧会が開かれた埋立13号付近の1979年の航空写真(国交省オルソ化空中写真システムを活用)
博覧会のパビリオン(宇宙科学博覧会Wikipedia参照)は、日本館、アメリカ館、アポロ劇場、宇宙博ホールの4館と船の科学館(イベント 船に関する知識の宝庫 「船の科学館」参照)3階展示ホールの展示場に、ロケット広場にサターンIB、レッドストーン、アトラスなどのロケットが展示されました。また、日本万国博覧会で人気のあった月の石や月面活動の道具などが展示され、画面の展示はアポロ館で360度のパノラマスクリーンでアポロ月面着陸の再現画面と、宇宙博ホールで高さ23m、幅30mのスクリーンに「人は大空へ」の映画が表示されました。
博覧会の入場者数は第1期が550万人、第2期が570万人(日本財団公表)で、予想をはるかに上回りました。

宇宙科学博覧会(日本財団出典)
国際科学技術博覧会
国際科学技術博覧会(つくばEXPO’85)は、茨城県のつくば市で1985年(昭和60年)3月17日から9月16日までの期間開催された国際博覧会です。博覧会の組織は、皇太子明仁親王(今上天皇)を名誉総裁に、土光敏夫会長の組織で財団法人国際科学技術博覧会協会が主催し、「人間・居住・環境と科学技術」を統一テーマとして開催されました。
博覧会の会場(国際科学技術博覧会Wikipedia参照)は、つくば市御幸が丘のメイン会場と同吾妻のサブ会場の102ヘクタールに展開し、メインの第1会場はAブロックからGブロックに区分けして国内パビリオンは28館と、その他外国館や関連機関のパビリオンや広場・遊園地などの52の展示場が造られました。

つくばEXPO’85の見学1985年6月
会場へのアクセスとして、国鉄常磐線の牛久駅と荒川沖駅間に臨時の万博中央駅が設置されましたが、13年後の1998年にひたち野うつくし駅が開設されました。また、HSST方式のリニアモーターカーのデモ運行が行われました。
博覧会の総入場者数は、2033万4727名を記録しました。博覧会には個人で出かけ、そのひとつは開催前の3月に所属する団体で、開催準備中の万博会場を見学しました。

つくばEXPO’85の施設見学1985年3月
横浜博覧会
横浜博覧会YES’89は、横浜みなとみらい21地区(69ヘクタール)で1989年に横浜市制100周年と開港100周年を記念し、横浜博覧会協会の主催でテーマを「宇宙と子供たち」(21世紀の展望)と掲げて、1989年3月25日から10月1日間にわたり開催され、総入場数は1,333万人でした。

みなとみらい地図
博覧会場へのアクセスは、桜木町駅からは動く歩道で桜木町ゲートまで約3分で着き、山下公園から1911年に開通の貨物線を利用して桜木町ゲートに近い日本丸駅まで気道車が運転されました。また、横浜そごうからゴンドラが運行してゴンドラゲートまで往復していました。その他、各地からのシーバスやシャトルバスが運行されていました。さらに、HSSTが日本初の磁気浮上式鉄道の営業運転や、羽田空港からヘリコプターの定期便就航など各種の交通手段が動員されました。
博覧会のパビリオン(横浜博覧会Wikipedia参照)は、YES’89宇宙館(横浜博覧会協会)、横浜館(横浜市)など30館を数えます。
横浜博覧会には、九州からお客さんが来て案内して、現在の観覧車のある付近を歩いたとの微かな記憶があるのですが、横浜博に関しては写真などが見当たらずそれ以上は想いだせません。
浜名湖花博
浜名湖花博は、浜名湖ガーデンパーク(現浜松市西区村櫛町)の約56ヘクタールの会場で秋篠宮文仁親王が総裁を務められ、日本花博の3回目で次項の日本国際博覧会の宣伝の役割も持って、2004年4月8日から10月11日まで開催して約544万人が来場して成功をおさめました。

浜名湖花博会場地図
博覧会の会場(浜名湖花博Wikipedia参照)は3つのゾーンがあり、1つは「花の街」でワールドガーデンコンベディション、KANSAI SUPER GARDENNなどの11の庭園やパピリオンがあり、2つ目は「水の園」できらめきタワーや水辺の劇場などの展示場があり、3つ目は「緑の里」で昭和天皇自然館や花の美術館などの7展示館があります。
花博の見学は、5月23日に行きましたが、新幹線に乗っている間じゅう雨が降り続いていましたが、浜圧駅からのシャトルバスで会場につくと雨は殆ど止んで何とか博覧会会場内を歩いて廻りました。印象に残った展示は、フランス・ジヴェルーにあるクロード・モネの家と庭園の再現が花博にマッチしていました。

浜名湖花博会場
日本国際博覧会
日本国際博覧会は、略称は「愛知万博」、愛称が「愛・地球博」の国内2回目の国際博覧会です。会場は、愛知県愛知郡長久手町の長久手会場(約173ヘクタール 愛・地球博記念公園地図参照)と瀬戸市の瀬戸会場(約15ヘクタール)の2会場で財団法人2005年日本国際博覧会協会の主催で、テーマは「人と自然が如何に共存していくか」を掲げて開催されました。入場者は、2,204万9,544人で目標の1,500万人を大きく上回りました。
愛・地球博への参加国は日本を含めて121カ国、4つの国際機関には国連本部と国連関係機関33が参加しました。
日本国際博覧会には、孫夫婦と2家族で6月15日に新幹線で日帰りの見学をしてきました。当然のことながら、日本万国博覧会と同様に人気パビリオンには待ち時間が2時間を越えるのがざらでそこは避け、121カ国も参加していますので比較的空いているパビリオンに入り、いろいろな国の人と展示品に触れてきました。

日本国際博覧会パビリオン
< 総合INDEX へ
毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(10月分掲Indexへ)
・カテゴリー別Index イベント総目次 2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ
<前回 イベント 横浜・開国博Y150 これまで見た博覧会と比較して見る(その1) へ
次回 イベント 横浜・開国博Y150 これまで見た博覧会と比較して見る(その3) へ